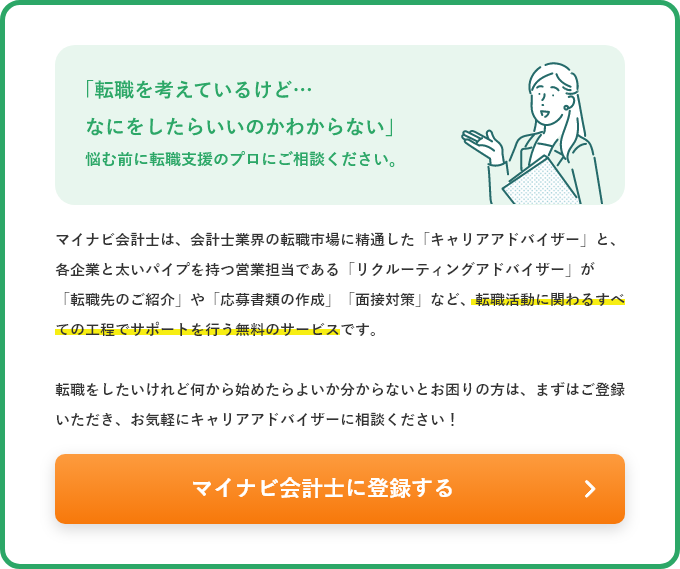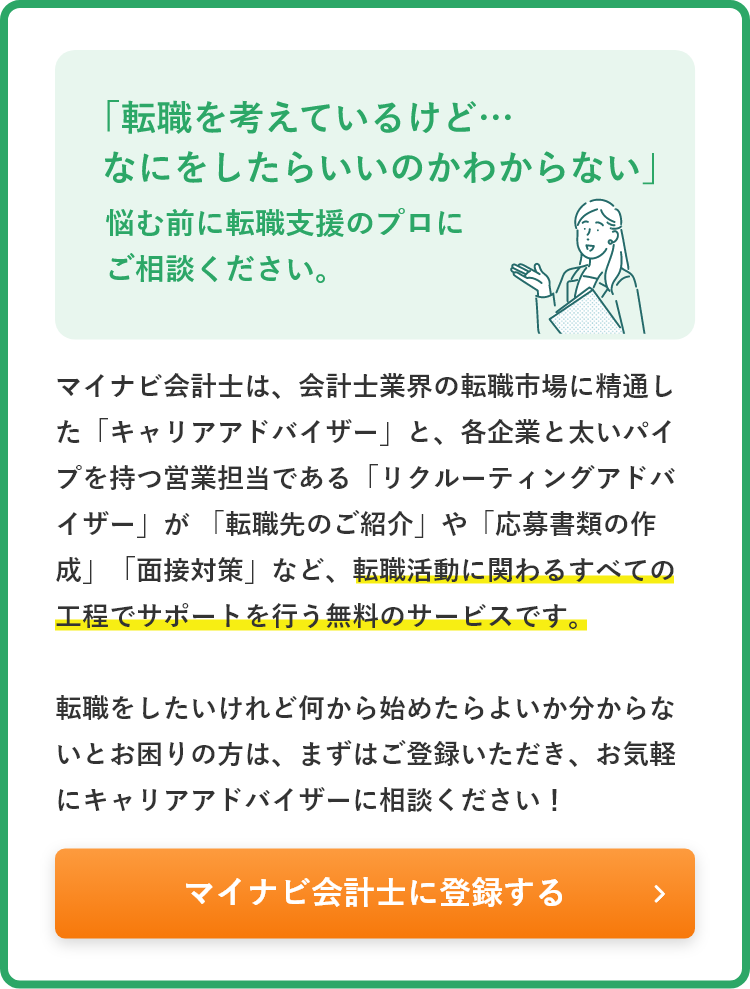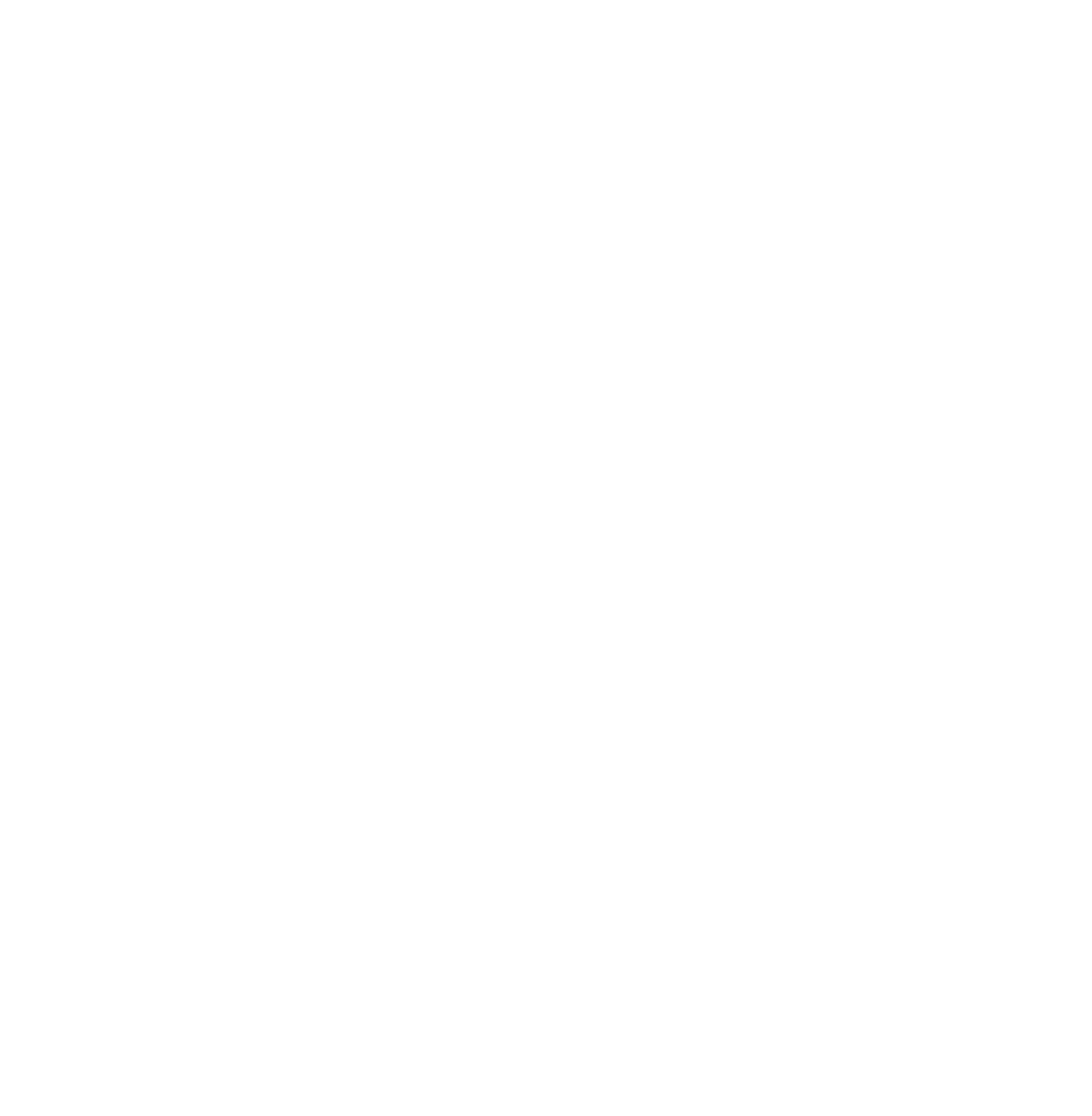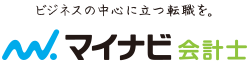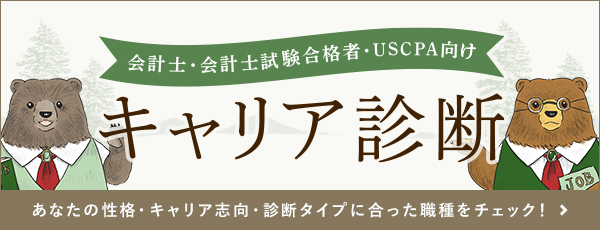公認会計士の難易度はどれくらい?|合格率や他職業との比較で確認
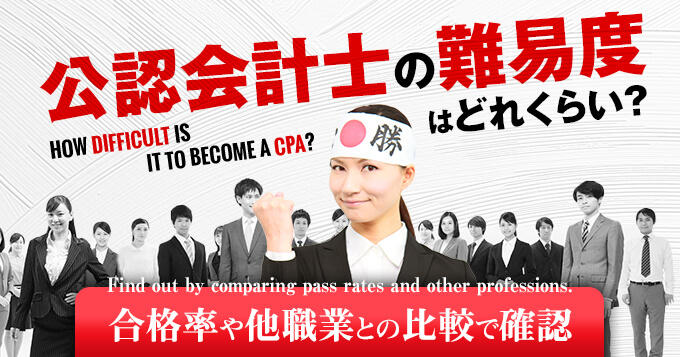
公認会計士は、医師・弁護士(法曹資格)と並ぶ三大国家資格のひとつに挙げられる難易度の高い職業です(文脈によっては公認会計士・弁護士・不動産鑑定士の三者を三大国家資格としてカウントする場合もあります)。
そこで今回は、これから公認会計士試験突破を目指して勉強をスタートしようとしている人のために、公認会計士試験の難易度や受験ハードルを詳しく解説します。
また、税理士・司法書士・弁護士などの資格と比較し、難易度が高いと言われる理由や、高難易度の公認会計士試験にチャレンジするメリット、公認会計士試験とほかの資格試験の難易度比較にも触れるため、ぜひ最後までご一読ください。
公認会計士試験を目指すスケジュールで、実現性の高いキャリアプランに悩んでいる方は、ぜひ一度マイナビ会計士にご相談ください。
関連まとめ記事
会計士試験情報まとめ 受験資格・申し込み手順

マイナビ会計士編集部
マイナビ会計士は、公認会計士・試験合格者・USCPAの方の転職サポートを行なう転職エージェント。業界専門のキャリアアドバイザーが最適なキャリアプランをご提案いたします。Webサイト・SNSでは、公認会計士・公認会計士試験合格者・USCPAの転職に役立つ記情報を発信しています。
目次
公認会計士試験の難易度は高い?
公認会計士は、受験資格が不要な一方で、短答試験・論述試験の二段階選抜方式が採用されており、どちらも合格した場合の合格率は『約7〜11%』と厳しい水準です。
また、医師・弁護士(法曹資格)と並ぶ三大国家資格であり、税理士より難易度は高いと考えられます。一方で、司法書士や弁護士と比べると難易度は低いです。
| 項目 | 合格率(令和6年) |
|---|---|
| 公認会計士 | 7.4% |
| 税理士 | 13.5% |
| 司法書士 | 5.2% |
| 弁護士(司法試験) | 42.1% |
公認会計士の難易度が高い理由は、膨大な量の知識を求められる学習範囲の広さと、それを補うために長期間にわたる厳しい学習量などが理由として挙げられます(後述します)。
【推移】公認会計士試験の最終合格率は約9.4%
公認会計士試験の「最終合格率の推移は約7〜11%(平均値9.4%)」です。試験を単独の推移で見ると「短答式は10〜30%(平均値17.0%)」、「論文式は30〜35%(平均値35.9%)」と2〜5人に1名は合格できる計算となります。
| 年別 | 願書提出者数 | 最終合格者数 | 短答式試験 | 論文式試験 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 21,573人 | 1,456人 | 11.9% | 36.8% | 7.4% |
| 令和5年 | 20,317人 | 1,544人 | 11.5% | 36.3% | 7.6% |
| 令和4年 | 18,789人 | 1,456人 | 11.8% | 35.8% | 7.7% |
| 令和3年 | 14,192人 | 1,360人 | 16.7% | 34.1% | 9.6% |
| 令和2年 | 13,231人 | 1,335人 | 16.0% | 35.9% | 10.1% |
| 令和元年 | 12,532人 | 1,337人 | 17.1% | 35.3% | 10.7% |
| 平成30年 | 11,742人 | 1,305人 | 25.3% | 35.5% | 11.1% |
| 平成29年 | 11,032人 | 1,231人 | 28.2% | 37.2% | 11.2% |
| 平成28年 | 10,256人 | 1,108人 | 17.3% | 35.3% | 10.8% |
| 平成27年 | 10,180人 | 1,051人 | 27.4% | 34.1% | 10.3% |
| 平成26年 | 10,870人 | 1,102人 | 15.1% | 36.8% | 10.1% |
| 平成25年 | 13,224人 | 1,178人 | 15.0% | 35.9% | 8.9% |
| 平成24年 | 17,894人 | 1,347人 | 8.1% | 38.0% | 7.5% |
参照:「令和6年公認会計士試験 合格者調」公認会計士・監査審査会
※短答式試験の合格率×論文式試験の合格率=最終合格率
参照:「過去の試験結果等」公認会計士・監査審査会
※詳細数値は各年別のリンク先を参照
短答式試験の出題傾向は一般的に広くそして浅いとされており、細かく学んで覚えておかなければならないことから、論文式と比べて低い傾向にあります。ただ、単純に最終合格率である約10%より、合格率が高いことはおわかりいただけたはずです。
では、よく比較される資格と比較するとどうなるのでしょうか。次では、税理士・司法書士・弁護士と比較した結果も見てみましょう。
関連記事
公認会計士の短答式試験とは?合格率からボーダーや推移まで詳しく解説
公認会計士の論文式試験とは?合格率や対策・試験前からしておくべき準備も解説
令和6年(2024年)公認会計士試験(論文式)合格発表速報|傾向と受験後の流れ
わかりやすく例えるなら?公認会計士と3つの資格で難易度を比較
これから公認会計士試験を目指そうという人のなかには、公認会計士試験とほかの資格試験の難易度に違いがあるのか気になる人もいるでしょう。以下に、各試験における合格率を比較した表をまとめました。
| 項目 | 合格率(令和6年) | 例え |
|---|---|---|
| 公認会計士 | 7.4% | ゴールまで前半・後半に分けて挑める |
| 税理士 | 13.5% | ゴールまでを5科目を分けて挑める |
| 司法書士 | 5.2% | スタートから一気にゴールを目指す |
| 弁護士(司法試験) | 42.1% | 別の予選を終えてからゴールを目指す |
参照:令和6年度(第74回)税理士試験結果発表|国税庁
参照:令和6年度司法書士試験の最終結果について|法務省
参照:令和6年司法試験の結果について|法務省
単純に合格率で難易度を比較すると司法書士が難しく、弁護士が簡単に見えます。しかし実際には、公認会計士試験は司法試験と司法書士より簡単で、税理士より難しい試験です。
そこで、公認会計士と以下の職種と比べるとなぜこのような難易度になるのかそれぞれの資格ごとに、例えも交えながらどちらの合格難易度が高いのかを解説します。
公認会計士は税理士より難易度が『高い』
| 項目 | 合格率(令和6年) |
|---|---|
| 公認会計士 | 7. 4% |
| 税理士 | 13.5% |
税理士と公認会計士を比較した場合、一般的には税理士よりも公認会計士の方が難易度は高いと言われています。
その理由は、次の4点です。
- 公認会計士資格を取得するだけで税理士業務にも携われる(別途、税理士登録は必要)
- 税理士試験は「有効期限なしの科目合格制度」で地道に時間をかければ合格するのは難しくない
- 「公認会計士試験の方が上位資格だ」という考え方により公認会計士試験の受験者層レベルが高い
- 税理士試験は公認会計士試験と比べて最終合格率が高い傾向にある(毎年15%~20%程度)
わかりやすく例えるなら、公認会計士5kmを前半2.5kmと後半2.5kmに分けて走る一方で、税理士は1kmごと5区間に分けて走れて、1区間ずつクリアするだけでよいということです。
「できるだけ早期に経理・会計業界の資格を取得して働くチャンスが欲しい」という希望を最優先にする受験生は、公認会計士試験よりも難易度の低い税理士試験を目指すことでその可能性を高められると考えられます。
公認会計士は司法書士より難易度が『低い』
| 項目 | 合格率(令和6年) |
|---|---|
| 公認会計士 | 7.4% |
| 司法書士 | 5.2% |
公認会計士と司法書士の仕事内容・試験内容はまったく異なるため単純に比較するのは簡単ではありません。しかし、一般的には公認会計士試験と比べて、以下の4つの理由から司法書士試験は難易度が高いと言われています。
- 司法書士試験の最終合格率は毎年約5%の低水準で推移している
- 司法書士試験は年1回の一発勝負(公認会計士試験は短答式試験に限り年2回)
- 司法書士試験には一部合格による免除制度が設けられていない
- 公認会計士試験は「短答式試験のみ合格」「論文式試験一部合格」でも就職・転職市場でニーズが高い
司法書士をわかりやすく例えるなら、年1回の一発勝負で給水所なし、休憩不可の状態で5kmを一気に走破するということです。前半・後半にわけて挑めて、前半は年2回チャレンジできる公認会計士のほうが難易度が低いでしょう。
「資格取得までのハードルをできるだけ低くしたい」「受験期間中でも習得した知識をいかして業界で仕事がしたい」という希望を最優先にする受験生には、司法書士試験よりも公認会計士試験が向いていると考えられます。
公認会計士と弁護士より難易度が『低い』
| 項目 | 合格率(令和6年) |
|---|---|
| 公認会計士 | 7.4% |
| 司法書士 | 42.1% |
弁護士といった法曹資格を取得するためには「司法試験」という国家試験に合格しなければいけません。
「司法試験の最終合格率は20%~40%の推移で、公認会計士試験よりも簡単だ」と言われることがありますが、これは誤解です。
なぜなら、司法試験には次の3点のような特殊性が存在するからです。
- 司法試験を受験するためには、司法試験予備試験に合格するか、法科大学院の卒業資格を要する(最低2年は通学する必要がある)
- 法曹三者になるための司法試験の難易度は、同じく法律系専門資格である司法書士試験とは比べ物にならないくらい難しい
- 司法試験の試験範囲は司法書士試験よりも広い
わかりやすく例えた場合、5kmマラソンであっても参加には「2km予選レース」の完走が必須で、受験するだけでも厳しい過程を経なければならないということです。そのうえ、厳しい競争を経てきた人たちだけで構成されるハイレベルな受験者層での合格率であっても「2~4割」にとどまるのが実情です。
「法学部を卒業している」「一般事業企業の法務部でのキャリアがある」などの例外的な事情があれば別ですが、基本的には受験資格を問われずにだれでも一発合格を狙える公認会計士試験は司法試験より難易度が低いと言えるでしょう。
公認会計士は難しすぎるからやめたほうがいい?
公認会計士は、確かに合格率約10%という数字だけを見ると非常に難しい試験に思えます。しかし、適切な学習計画と継続的な努力で乗り越えられる課題であり、「やめとけ」と言われる本質的な理由にはなりません。
むしろ、「やめとけ」という声の背景には、業界特有の働き方や環境に関する懸念があります。典型的なものとしては、2月から5月にかけての決算期における激務です。深夜まで働くことも珍しくありませんし、クライアント企業の問題点を指摘するときにはときとして緊張感が生まれることもあります。
そのほかにも理由はありますが、試験の難易度ではなく、職業特性や働き方が自分に合っているかどうかで判断したほうが賢明だといえるでしょう。理由を含めて詳しくは、下記ページをご覧ください。
公認会計士は受験資格がないことで難易度が下がりやすい
公認会計士の難易度は、非常に高く感じるかもしれません。ただ、司法試験・司法書士試験などの国家試験とは異なり、公認会計士試験には受験資格が設けられていないという特徴があります。
| 医師 | ①学校教育法に基づく大学で医学の正規の課程を修めて卒業した者 ②医師国家試験予備試験に合格して1年以上の診療および公衆衛生に関する実地修練を得た者 |
|---|---|
| 弁護士 | ①法科大学院へ入学して2〜3年間学んだ者 ②規定の予備試験に合格した者 |
| 公認会計士 | 受験資格なし (2005年以前の旧試験は大学もしくは短大卒業資格保有者のみ) |
医師や弁護士は試験前に一定の知識を保有している状態が整えられている一方で、専門学校や独学を含めてだれでも受験できる公認会計士試験では「だれでも公認会計士試験に挑戦できる」というメリットに惹かれて、公認会計士への転職を検討している人も少なくないでしょう。
それでもなぜ、難易度が高い・難しいと言われているのか。次では主な3つの理由を紹介します。なお、受験資格について詳しくは、下記ページからご覧いただけます。
公認会計士試験の難易度が高い・難しいと言われる3つの理由
公認会計士試験の難易度が高いと言われる「合格率以外の要因」には、以下の3つが挙げられます。
- 試験科目数の多く相応の努力が必要だから
- 勉強時間が最短でも1年以上かかるから
- すべての科目を1回で合格しなければならないから
受験科目数が多く相応の努力が必要だから
公認会計士試験の受験科目は次のとおりです。科目数が多いことは学習範囲の広さを意味し、その難易度を高めていると考えられます。
- 短答式試験の試験科目:財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の4科目
- 論文式試験の試験科目:会計学・監査論・租税法・企業法・選択科目(経営学・経済学・民法・統計学のうち1科目を選択)の5科目
仮に、社会人となって働きながらこれだけの範囲を学ぶとなると、相応の努力が必要となることがおわかりいただけるはずです。なお、公認会計士試験には免除制度も設けられています。詳しくは、下記ページをご覧ください。
勉強時間が最短でも1年以上かかるから
公認会計士試験で問われる試験内容は難易度が高いため、どれだけ効率的に学習を進めたとしても最低1年は「勉強だけ」の生活が続きます。
一般的に、公認会計士試験に最終合格できるまでの習熟度に達するためには、合計約3,000〜6,000時間の勉強量が必要と考えられています。仮に、6,000時間だとすると1日10時間ずつ勉強しても1年半~2年、1日5時間ずつなら約4年程度の期間が必要になる計算です。
モチベーションを維持しながら厳しい受験生活をつづけるためには、いくつもの我慢に耐えなければいけないため、公認会計士試験にチャレンジする場合は「相当の覚悟」が必要です。気になる方は、ぜひ下記ページもご覧ください。
すべての科目を1回で合格しなければならないから
さいごに、公認会計士試験の難易度を高める要因の1つとして、すべての科目を同時に受験しなければならない点も挙げられます。税理士試験のように1科目ずつの合格を積み重ねることはできず、短答式試験(財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の4科目)と論文式試験(必須4科目+選択1科目)をそれぞれ一度に受験しなければなりません。
また、短答式試験に合格しても、免除期間は2年間のみです。つまり、2年以内に論文式試験に合格しなければ、再度短答式試験から受験し直さなければならないのです。
難易度の高い公認会計士に合格しやすい人の特徴
難易度の高い公認会計士に合格しやすい人の特徴には、以下の4つが挙げられます。あくまでも一般的な傾向であり、「なれない人」は存在しません。
- 忍耐力と継続力がある人
- ロジカルな思考力を持つ人
- 地道な作業を継続できる人
- 正義感のある人
試験の最終合格率は約10%と低く、科目合格制度にも有効期限があります。時間管理が得意で多科目を満遍なく学習でき、効率的な学習計画を立てられる強い意志が必要です。
また、働きながら勉強するという選択肢もあり、実務経験を積みながら試験に挑戦することも可能です。より詳しくは、ぜひ下記ページもチェックしてください。
独学で合格できる?
独学での合格は不可能ではありませんが、相当な覚悟と計画性が必要です。合格には最低3,000時間の勉強が必要となるほか、すでにお伝えしたように試験の最終合格率も10%前後と低いためです。
多くの合格者は大手予備校を活用したり、働きながら実践で知識を補ったりしていることを踏まえても『簡単』とはいえません。とはいえ、独学には費用面を抑えられること、そして学習の自由度が高いメリットもあります。どちらが良いか悩んだ際には、ぜひ下記ページもご覧ください。
公認会計士試験の難易度を乗り越えて合格する4つのメリット
公認会計士試験に合格するためには努力が求められますし、受験勉強期間に生じる家計への不安にも耐え抜かなければいけません。
ただ、このような厳しい状況を突破して公認会計士試験に合格できれば、それまで課されていた厳しいデメリットをはるかに超える以下のメリットがあります。
- 年収が高くなる可能性が高い
- 専門職従事者としての社会的地位・ステータスを獲得できる
- 難関資格取得者としてキャリアパスが広がる
- 男女・年齢関係なく研鑽を積める
年収が高くなる可能性が高い
公認会計士試験の高い難易度を克服して合格することは、高い年収につながります。公認会計士の平均年収は746万円(2023年時点)であり、日本における一般的な年収の461万円を超える水準です。
もちろん、非常に専門性が高く、担う社会的責任の重さも年収に比例して高くなります。とはいえ、さらに経験を積むことで年収を高めることができますし、専門性を高めて新たなキャリアパスを開くことも可能です。
このことから、「できるだけ年収の高いキャリアを歩みたい」という人には公認会計士はおすすめの職業です。また、「公認会計士として働くならばできるだけ高収入を得たい」と希望する場合は、いわゆる「BIG4」と呼ばれる大規模ファームに就職・転職するのが適していると言えるでしょう。
公認会計士の年収の最新情報や年齢別の推移について、より詳しく知りたい方はぜひ下記ページもご覧ください。
参照:平均給与|国税庁
専門職従事者としての社会的地位・ステータスを獲得できる
公認会計士は、医師、弁護士と並ぶ三大国家資格として社会的に広く認知されており、最難関の国家資格という評価を確立しています。企業の財務諸表監査を行う権限を持つ独占業務は、経済社会における役割として認識され、非常に高い社会的地位とステータスを得られる専門職です。
- 大監査法人のパートナー
- コンサルティングファームの経営者
- 上場企業のCFO
上記のようにトップレベルのポジションにつく機会も得られ、キャリアを通じて社会的影響力を持つ立場も狙えます。企業経営者や他の専門職からも対等なビジネスパートナーとして認識され、確かな社会的地位とステータスを得られる職業だといえるのです。
難関資格取得者としてキャリアパスが広がる
公認会計士の資格取得は確かに難関ですが、その後のキャリアの可能性は非常に広いのもメリットです。一般的なのは大手監査法人(Big4)での監査業務からスタートし、経験を積んでシニアスタッフ、マネージャー、さらにはパートナーへとステップアップしていくキャリアパスでしょう。
一方で、監査法人での経験を活かして、コンサルティングファームでM&Aや経営管理のアドバイザーとして活躍したり、税理士事務所や会計事務所で実務のスペシャリストとして従事したりする道も選べます。そのほかのキャリアパスについては、ぜひ下記ページもチェックしてください。
男女・年齢関係なく研鑽を積める
公認会計士の資格試験には年齢制限がなく、20代から60代まで幅広い年齢層で合格者が出ています。主に企業のガバナンス強化や国際会計基準への対応など、常に新しい知識が求められる分野です。そのため、若手からベテランまで継続的な学びの機会があり、経験を重ねるほど価値も高まる職業といえます。
また、女性については日本公認会計士協会が女性特有の課題に対応するためのキャリアサポートや研修制度、ネットワーキングの機会を提供しており、職場環境も整備されつつあります。育児休暇や短時間勤務制度なども活用しやすくなっているのです。より詳しくは、下記ページでお伝えしています。
働きながら公認会計士を目指すことも可能
近年では「監査トレーニー制度」を導入している監査法人もあり、実務経験を積みながら試験対策ができる環境が整っていることで、働きながらの公認会計士資格取得は可能です。
働きながら学習を進める場合は、オンライン講座の活用で学習コストを抑えられるほか、勤務先の支援制度を利用できる可能性もあります。また、複数年かけて段階的に学習を進めることで、仕事との両立も実現しやすくなります。興味があれば、ぜひ下記ページもご覧ください。
公認会計士以外に取得をおすすめできる資格
ここまで読み進めた方のなかには、公認会計士の高い難易度に気押されているケースもあるはずです。そのようなときには、以下に挙げた2つの資格も検討できます。
- 日商簿記
- 税理士
日商簿記
公認会計士の代わりに検討したいのが、日商簿記検定です。公認会計士の試験と共通する項目があり、簿記1級レベルの知識を目指すのは前段階のステップとして有効な手段です。
また、事業会社の経理部門や会計事務所への転職を考えている場合には、日商簿記の資格が評価されやすいのもメリットです。そのほか、税理士補助や経理職としてのキャリアを視野に入れている方にも役立ちます。詳しくは、ぜひ下記ページもご覧ください。
税理士
税理士の資格は、公認会計士試験の「財務会計論」と税理士試験の「簿記論」「財務諸表論」が共通しています。もし、すでに学習をはじめていたという方であっても、これまでの努力が無駄にならない選択肢です。
公認会計士とは異なる専門性を持ち、税理士は主に税務申告や税務相談を行い、公認会計士は主に会計監査を行います。科目合格制度があることで、公認会計士よりも取得しやすいほか、1科目だけでも転職の際にアピールできることも魅力です。気になる方は、ぜひ下記ページもご覧ください。
高難易度の資格を取得後に公認会計士になるには
どの仕事についても当てはまることですが、当然ながら「公認会計士試験に合格しただけで安泰」というわけではありません。
難易度の高い試験に合格した後は、就職・転職活動を経てファームに所属したうえで、さらに専門性を高める努力を継続しながら自分なりのキャリアを築いていく必要があります。
ただ、2008年のリーマンショックの煽りを受けて2012年頃は一時的に買い手市場でしたが、現在の公認会計士業界は売り手市場の傾向があります。
業界全体の高齢化に歯止めをかけるために若手人材を採用する動きが強くなっていますし、コロナによる不況から再生を目指す企業側からコンサルティングサービスを求める声も増加傾向にあるでしょう。
そのため、「公認会計士試験に合格したのに就職先がない」「難しい試験に合格したのに年収が低いままだ」という理不尽な状況には追い込まれませんし、自分が希望するキャリアを目指しやすい状況とも考えられます。
とはいえ、公認会計士業界にもデジタル化の波が押し寄せている点には注意しなければいけません。なぜなら、AI化による業務効率化指向の高まりによって公認会計士の仕事が少なくなり、結果として業界全体が買い手市場に再転換する可能性も否定できないからです。
したがって、向こう数年、数十年先のキャリアを見据えるのなら、従来の公認会計士の姿をそのまま踏襲するのではなく、「AIに淘汰されない公認会計士」「AIを駆使する公認会計士」というように、これからの新しい時代に通用する自分なりのキャリアを具体化して邁進できるかがポイントになるでしょう。
公認会計士の難易度で気になるQ&A
さいごに、これから公認会計士を目指す人が抱くよくある疑問点をQ&A形式で紹介します。
- 公認会計士とUSCPA(米国公認会計士)の違いは?
- 公認会計士と税理士はどちらが良いですか?
- 公認会計士試験に合格するには学歴・偏差値は関係ありますか?
- 公認会計士の将来性は?
- 公認会計士の合格に必要な勉強時間は1日何時間?
公認会計士とUSCPA(米国公認会計士)の違いは?
最大の違いは、公認会計士は日本で監査業務などの独占業務ができるのに対し、USCPAは日本では監査業務はできない点です。USCPAは英語でビジネスができる国際的な会計のプロとしての証明となり、外資系企業やグローバル企業でのキャリアに強みを発揮します。
試験もすべて英語で実施されるため、専門知識と英語力の両方が求められます。気になる方は、ぜひ下記ページからご覧ください。
公認会計士と税理士はどちらが良い?
「資格試験の難易度」という点だけで比較すると、「公認会計士試験の方が税理士試験よりも難しい」というのが実際のところです。なぜなら、公認会計士と税理士では基本的な業務内容がまったく異なるからです。
- 税理士の独占業務:税務代理・税務書類の作成・税務相談
- 公認会計士の独占業務:監査業務
良い・悪いという観点で資格の選別をするのではなく、「自分がどのような仕事をしたいのか」という観点で公認会計士・税理士のどちらを目指すのかを決めるのが大切です。詳しくは、下記ページをご覧ください。
公認会計士に学歴や偏差値は関係する?
公認会計士試験は、だれでも受験できる資格試験です。学歴・偏差値・国籍・性別など、いかなる観点においても不平等な取扱いを受けることはありません。
試験に合格しさえすれば、「低学歴だから就職できない」「高卒だから転職面接に落とされる」などという不条理な目に合うことは考えにくいでしょう。「低学歴だから難易度の高い公認会計士試験は無理だ」というように勉強をスタートする前から諦める必要はありません。詳しくは、下記ページをご覧ください。
公認会計士の将来性は?
公認会計士は、企業や個人事業主に必要な人材であり、将来性があると言えます。好景気の影響を受け、監査料が上がったり、非監査業務の依頼が増えたりするなどで需要が高まっているためです。
また、AIに代替されるのではという心配もあるかもしれませんが、企業や個人事業主に対して会計の専門家として「会計状況を見極め、サポートする」という点に真の価値があると考えましょう。詳しくは、下記ページもチェックしてください。
公認会計士の合格に必要な勉強時間は1日何時間?
公認会計士試験に合格するためには、一般的に合計約3,000〜6,000時間の勉強が必要とされています。1日10時間ずつ勉強すると1年半〜2年、1日5時間ずつ勉強すると約4年が必要になります。
ただし、受験者の学習進捗度や環境によって、合格までのスケジュール感や1日あたりの勉強時間は異なるのも実情です。公認会計士試験は難易度が高いため、効率的に学習を進めても、最低でも1年間は勉強だけの生活が続くことになるでしょう。
まとめ
公認会計士は三大国家資格に名を連ねる難関資格です。合格水準に達するためには最低でも年単位で受験勉強を継続する必要があるので、安易な気持ちでは合格できません。
ただ、そのような厳しい受験生活をクリアして無事に「公認会計士試験合格」という成果を得られると、高い年収・幅広いキャリア選択肢・社会的地位が手に入ります。これらのメリットは、厳しい受験生生活で強いられるいくつもの我慢をはるかに上回るものです。
とはいえ、難易度の高さだけに注目するとやる気を奪われるだけです。公認会計士試験合格を目指すのなら、試験の難易度を冷静に分析したうえで、自分に合ったスタイルを確立して、戦略的・効率的に学習を進めましょう。
マイナビ会計士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
マイナビ会計士とは?
マイナビ会計士は会計士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。