あなたが理想の会計士になるまで、
私たちは全力でサポートいたします。
蓄積された実績や、非公開の企業情報などから条件にマッチした求人をご紹介いたします。
面接・応募書類対策・スケジュール調整など、転職成功へ導くため、
マイナビ会計士は転職をサポートいたします。

マイナビ会計士に申し込む
受験資格・申し込み手順
目次
公認会計士は、監査や税務、コンサルティングなどの会計に関連する業務に幅広く携わっています。 特に、監査業務は公認会計士だけが行える独占業務です。
公認会計士になるためには、司法試験と並ぶ難関国家資格試験として知られる公認会計士試験を突破する必要があります。
では、この公認会計士試験とは一体どのような試験内容なのでしょうか。公認会計士試験について、試験概要を解説します。
▼最新情報はこちらをご確認ください。
公認会計士・監査審査会

短答式試験の合否判定については、科目ごとの判定ではなく4科目の総合得点で判定します。
合格ラインとしては、全科目の総点数の70%を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率をクリアすることで合格となります。
ただし、1科目につき、その満点の40%に満たないものがあると、不合格となる場合があります。
| 試験科目 | 試験時間 | 問題数 | 合格基準/配点 | |
|---|---|---|---|---|
| 短答式試験 | 財務会計論 | 120分 | 40問以内 | 80点以上/200点 |
| 管理会計論 | 60分 | 20問以内 | 40点以上/100点 | |
| 監査論 | 60分 | 20問以内 | 40点以上/100点 | |
| 企業法 | 60分 | 20問以内 | 40点以上/100点 | |
| 総点数 350点以上/500点 | ||||
| 論文式試験 | 会計学 | 300分 | 大問5問 | 120点以上/300点 |
| 監査論 | 120分 | 大問2問 | 40点以上/100点 | |
| 企業法 | 120分 | 大問2問 | 40点以上/100点 | |
| 租税法 | 120分 | 大問2問 | 40点以上/100点 | |
| 選択科目 | 120分 | 大問2問 | 40点以上/100点 | |
| 52%の得点比率を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率 | ||||
19,500円
| 試験区分 | 時間 | 科目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短答式試験 | 9:30〜10:30 (60分) | 必須科目 | 企業法 | |
| 11:30〜12:30 (60分) | 管理会計論 | |||
| 14:00〜15:00 (60分) | 監査論 | |||
| 16:00〜18:00 (120分) | 財務会計論 | |||
| 論文式試験 | 1日目 | 10:30〜12:30 (120分) | 必須科目 | 監査論 |
| 14:30〜16:30 (120分) | 租税法 | |||
| 2日目 | 10:30〜12:30 (120分) | 財務会計論 | ||
| 14:30〜17:30 (180分) | 管理会計論 | |||
| 3日目 | 10:30〜12:30 (120分) | 企業法 | ||
| 14:30〜16:30 (120分) | 選択科目 (1科目) |
経営学 経済学 民法 統計学 |
||
旧公認会計士試験制度においては、2次試験に受験資格の制限が設けられていました。
現在は改正されており、公認会計士試験に受験資格の制限はありません。
よって、学歴等のバックグラウンドにかかわらず、誰でも試験に挑戦できるようになっています。
また、平成22年試験からは短答式試験の実施回数が年2回実施されるようになり、より挑戦しやすい方向へ改正が行われているといえます。
短答式試験に合格し、論文式試験は不合格となった場合
| 免除科目 | 対象者 |
|---|---|
| 会計学および経営学 | 大学等において3年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者または商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 |
| 企業法および民法 | 大学等において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者または法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 |
| 経済学 | 大学等において3年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者または経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 |
| 企業法および民法 | 司法試験合格者 |
| 租税法 | 税理士となる資格を有する者 |
| 経済学または民法 | 不動産鑑定士試験合格者および旧鑑定評価法の規定による不動産鑑定士試験第2次試験合格者 |
論文式試験全体では合格基準に達していないが、一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者は、その科目の論文式試験が翌年と翌々年の2年間免除されます。
免除を受ける場合は「公認会計士試験免除申請書」による免除申請を行う必要があります。
ただし、受験願書に免除通知書のコピー等を添付する必要があるため、希望する試験日程の受験願書の受け付け日に間に合うよう申請する必要があります。
なお、職歴や資格等による免除申請は通年で受け付けています。

受験の申し込みは、まず受験願書を入手することから始まります。
受験願書は財務局理財課等および公認会計士・監査審査会事務局にて配布されます。
配布時間は平日の午前9時から午後5時となっており、直接取りに行くことができない場合は、郵送により請求することもできます。
郵送による請求の場合は、直接取りに行く場合よりも期限が早めになっているので注意が必要です。
受験願書を入手し、必要事項の記入・必要書類の準備を終えれば、次は受験願書の提出です。
提出の際は、受験願書および必要書類を、受験を希望する試験地を管轄する財務局理財課等に提出します。
この際、財務局理財課等に直接願書を持参しても受付けてもらえません。
必ず簡易書留または書留にして郵送する事とされています。
また、当然ながら受付期間を過ぎた場合の受験願書は受理されませんので、余裕をもって提出することが重要です。

| 持ち物・準備する物 | 受験票 |
|---|---|
| 写真票 (インターネット出願をした者のみ) | |
| 筆記用具 |
| その他 | 算盤又は電卓 …… 1台 ※プログラム入力・記憶機能や関数電卓機能、紙に記録する機能、漢字・カナ・英字入力機能を有していないもの |
|---|---|
| 時計又はストップウォッチ (音を発しない計時機能のみを有するものに限る) …… 1個 | |
| ホッチキス | |
| 定規 | |
| 耳栓 | |
| ふた付ペットボトル飲料(500ml 以下のもの1本。アルミ缶は不可。) |

合格発表は短答式試験・論文式試験ともに、予定日に各財務局等および公認会計士・監査審査会ウェブサイトに「受験番号」が掲載されるとともに、官報にも公告されます。また、合格通知書が送付されることで通知されます。
論文式試験の合格発表は例年11月に実施されますが、各監査法人の説明会等は論文式試験後から随時開始されるため、就職を予定している場合は早めに情報を集めておくことが望ましいです。
公認会計士試験に合格した場合、公認会計士を名乗るためのステップとして2年以上の実務経験、原則3年間の実務補習の受講および修了考査の合格という要件を満たす必要があります。
実務経験は試験合格後に監査法人に就職して経験するのが一般的ですが、実務補習は公認会計士となるのに必要な技能の修習を目的として、実務補習所というところで行われます。
実務補習の方法としては、以下のものがあります。
このような講義や実地演習への出席、考査の受験等によって実務補習の単位が付与され、決められた単位を取得することで修了考査の受験資格が与えられます。
修了考査の内容は、以下5科目の筆記試験となっています。

公認会計士試験合格、実務補習受講および修了考査まで修了し、かつ2年以上の実務経験要件を満たしていれば、日本公認会計士協会に備える公認会計士名簿に登録を受けることで、公認会計士として業務を行う事ができるようになります。
この登録のためには、日本公認会計士協会に公認会計士開業登録申請書類を提出しなければなりません。
開業登録申請書類が受理されると、申請者が公認会計士となる資格を有するかどうか、申請書および添付書類が完備しているかどうか等を登録審査会で審査することになります。
審査の結果、登録申請が適法であると認められた場合には、公認会計士名簿に登録されると共に、官報に公告され、登録申請者に対しても登録年月日および登録番号が通知されます。
この登録に必要となる要件は以下の3点です。
平成18年からの公認会計士試験合格者の場合、登録申請の際に、この要件を満たしていることを示す書類として以下の書類の写しが必要となります。
また、これらを含め申請に必要となる書類は次のとおりです。
登録申請の際は、円滑に進められるよう早めに準備しておく事をおすすめします。

ここまで、公認会計士試験合格から公認会計士登録までのステップを確認してきました。
ところで、公認会計士試験に合格した状態である、いわゆる「試験合格者」と「公認会計士」では何が異なるのでしょうか。当然さまざまな違いがあるのですが、特に業務面で大きな違いがあります。
それは、公認会計士には、公認会計士にしかできない独占業務があることです。
具体的には、企業等に対する財務諸表監査がその独占業務にあたり、財務諸表監査を実施できるかどうかが公認会計士と試験合格者を分ける一つのポイントとなります。
ただし、財務諸表監査が公認会計士の独占業務だからといって、公認会計士の資格を取ってすぐに自らの資格で企業の監査を請け負うことはまずありません。
監査業務とは通常、チームを組んで行うものであり、監査法人では、その法人の資格によって監査を実施します。
そして、パートナーや社員と呼ばれる責任者を中心とし、その責任者以外はそのスタッフという位置づけで監査業務が行われます。
そのため、公認会計士という資格の有無にかかわらず、試験合格者のままでも監査業務に携わることはできます。
実際、試験合格者の多くは実務経験要件を満たすために、監査法人にて会計監査補助業務につきます。
しかし、試験合格者と公認会計士を比較すると、顧客企業の担当者からの信頼度は大きく異なります。
試験合格者は難関試験を突破したとはいえ、会計監査の実務経験はもちろんのこと、社会人経験も乏しい場合が往々にしてあります。
いくら名刺に試験合格者と記載されていても、実際の会計実務に詳しい証明にはなりません。
監査実務で必要になるものや顧客企業が求めているものは、机上の知識ではなく、確かな業務経験に裏打ちされた知識です。
公認会計士にはプロフェッショナルとして豊富な知識や経験が求められますが、そこにたどり着くためには長い実務経験と絶え間ない勉強の積み重ねが必要です。
試験合格者はスタートラインに立っただけの状態であるため、顧客企業の担当者からすると、試験合格者=監査法人の新人という印象を持ちます。
そのため、「公認会計士」と名刺に記載されていれば、公認会計士として最低限の実務経験があるということが一目で伝わります。
監査法人に就職していれば、基本的に要件を満たせば公認会計士として登録を行うことが一般的です。
まずはキャリアアドバイザーにご相談ください
無料マイナビ会計士に申し込む
キャリアアドバイザーを通じて、ステップアップに成功した転職成功者の方々の事例をご紹介します。
転職をお考えの会計士・試験合格者の疑問や悩み、不安を会計士業界専任キャリアアドバイザーが解消します。
事業会社、監査法人、会計事務所/税理士法人、コンサルティングファームについてをご紹介します。
マイナビ会計士がご紹介する、企業や法人の企業情報や働く方々の声、求人情報などをご紹介します。
復職する際の注意点や転職のタイミング、オススメ求人や転職成功事例をご紹介します。
試験合格後から会計士登録の完了までのスケジュールや流れ、登録後にやるべきことなどをご紹介します。
資格取得のメリットや、活躍できるフィールド、転職市場での価値とニーズについてご紹介します。
監査法人から事業会社やコンサルティングファームへの転職方法やポイントなどをご紹介します。
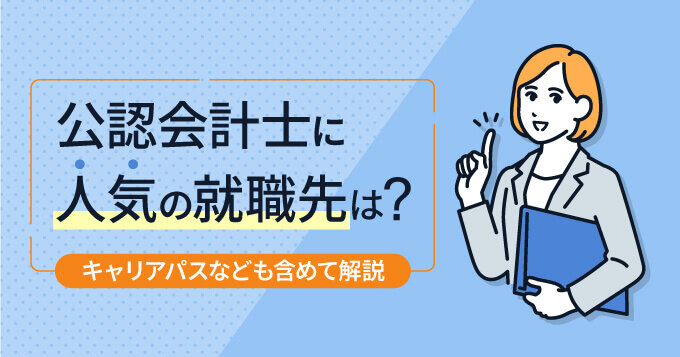
仕事・キャリア
公認会計士に人気の就職先は?キャリアパスなども含めて解説
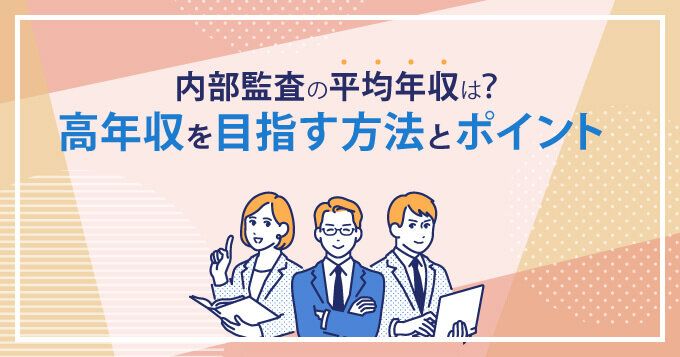
仕事・キャリア
内部監査の平均年収は?高年収を目指す方法とポイント

仕事・キャリア
30代から内部監査への転職は可能?事例やメリット・デメリットを解説

業界情報
【令和6年(2024年) 公認会計士試験第Ⅱ回短答式試験 結果速報】令和6年論文式試験に向けて
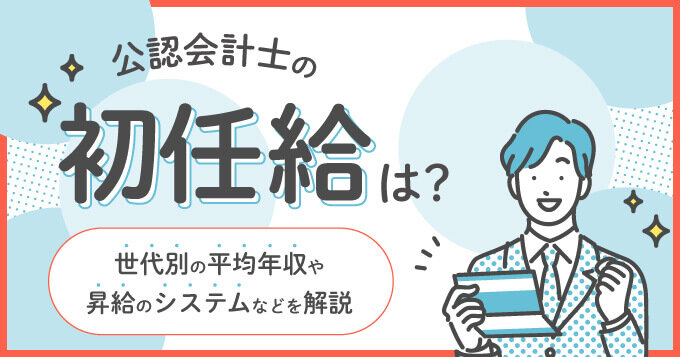
仕事・キャリア
公認会計士の初任給は?世代別の平均年収や昇給のシステムなどを解説
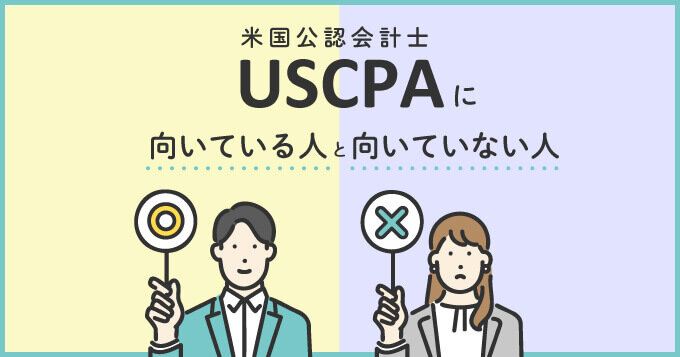
仕事・キャリア
米国公認会計士(USCPA)に向いている人と向いていない人

仕事・キャリア
【状況別】内部監査の志望動機を書くポイント|転職理由やキャリアパスも解説
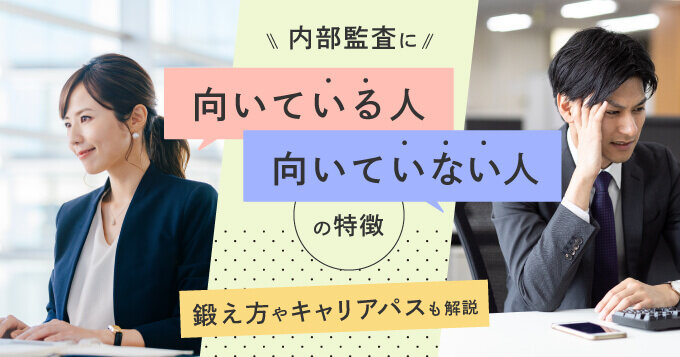
仕事・キャリア
内部監査に向いている人・向いていない人の特徴|鍛え方やキャリアパスも解説

会計士・試験合格者専門の転職エージェントです。細かなサービス内容をご説明します。

マイナビ会計士の具体的なご利用の流れや登録のメリットなどをご紹介します。

転職のプロがあなたの転職をサポート。会計士業界専任のキャリアアドバイザーをご紹介します。

マイナビ会計士の求人の一部は非公開求人です。求人を公開していない理由などをご紹介します。

はじめての転職で失敗しないためのポイントや、マイナビ会計士の強みをご紹介します。

業界内で再度転職をする際に注意すると良いポイントや、マイナビ会計士の強みをご紹介します。

おすすめ別や資格別に実施中の相談会やセミナーのご紹介、当日までの流れなどをご紹介します。

転職支援サービスをさせていただく中で、求職者のみなさまからいただくご質問をご紹介します。
蓄積された実績や、非公開の企業情報などから条件にマッチした求人をご紹介いたします。
面接・応募書類対策・スケジュール調整など、転職成功へ導くため、
マイナビ会計士は転職をサポートいたします。

マイナビ会計士に申し込む