あなたが理想の会計士になるまで、
私たちは全力でサポートいたします。
蓄積された実績や、非公開の企業情報などから条件にマッチした求人をご紹介いたします。
面接・応募書類対策・スケジュール調整など、転職成功へ導くため、
マイナビ会計士は転職をサポートいたします。

マイナビ会計士に申し込む
短答試験財務会計論(簿記)
目次
公認会計士試験でも最も重要な科目と言われる財務会計論。短答式試験における必須受験科目の一つであることに加え、簿記と財務諸表論の2つの分野から出題される科目なので全体像がつかみにくく、どのように勉強を進めるべきか悩む受験生は多いと思います。
そこで、本記事では「財務会計論の中でも、財務諸表論ってどんな試験?」「財務諸表論ってどんな風に勉強したらいいの?」などの疑問について、初学者にもわかりやすく解説したいと思います。公認会計士試験を受験しようと考えていて、短答式試験の科目について詳しく知りたいという方は、是非本記事をご一読ください。
まずはキャリアアドバイザーにご相談ください
無料マイナビ会計士に申し込む
財務会計論とは、「会計学」という公認会計士試験の基礎となっている学問の一分野です。「会計学」は、公認会計士試験の中の重要な位置にあり、短答式では「管理会計論」、「財務会計論」、「監査論」、論文式では「会計学」、「監査論」の科目の中で出題されているものです。
学問としての財務会計論は、企業の経営成績や財政状態などを明らかにすることで、投資家、債権者、その他のステークホルダーに、意思決定に資する情報を提供することを目的としています。そこで、財務会計論の分野は大まかに「簿記」と「財務諸表論」に分かれます。
「簿記」とは、企業の経営成績や財政状態などを明らかにするために、日々の企業の経営活動を商業簿記により記録・計算・整理する分野です。例えば、「会社が掛けで商品を売る」といった行動を、一般に公正妥当と認められた会計基準に沿って記録・計算する方法を学びます。一方、「財務諸表論」とは、会計基準の内容、背景、学説の対立といった理論について学びます。
公認会計士試験は、年二回開催される短答式試験と、年一回開催される論文式試験で構成されています。短答式試験の科目は管理会計論、財務会計論、会社法、監査論の4科目で、全て必修科目となっています。
財務会計論は、短答式試験の中の1科目です。計算問題部分が財務会計論(簿記)、理論問題部分が財務会計論(財務諸表論)と呼ばれています。なお、論文式試験においても、「会計学」の中で「管理会計論」と「財務会計論」がどちらも問われます。そのため、短答式での学習は、論文式試験でも応用することが可能です。
以下では、財務会計論(簿記)の詳細について解説します。
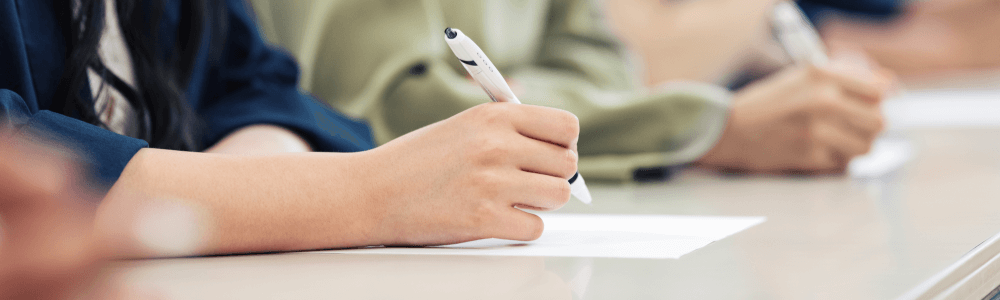
財務会計論は総じてボリュームが非常に多く、短答式試験4科目の中で比較すると、その分量は最大かつ重要です。そのため、いかに所定時間内で正確な回答を導き出すかという「スピード」および「正確さ」が必要となってきます。また、問題文の解釈が困難な部分も多くあるため、単純に会計処理について知っているかどうかというレベルを超えて、各取引における仕訳を切れることが重要です。
財務会計論(簿記)は、上述の通り財務会計論の計算問題部分を指していて、公認会計士の中で最も重要な科目と言われています。その理由は、配点が大きいため、勉強量に比例して点数が上がりやすいため、努力の差が点数に出やすいための二点です。そのため、簿記でしっかりと得点ととることで、公認会計士試験合格にぐっと近づくと言われています。
また、財務会計論(簿記)は、「企業会計原則」等の会計基準に基づいて行われます。そして、会計処理が規定されている内容とその背景、理由を学習するのが財務会計論(財務諸表論)です。簿記から学習を始めた方でも、並行して財務諸表論を学習することで、計算問題に対する理解も深まり、より早く正確に問題が解けるようになります。簿記を学習する際には、常に理論とのつながりを意識することがポイントです。
公認会計士・監査審査会は、毎回の公認会計試験の前に、次回の試験の出題範囲の要旨を示しています。
抽象的な表現ではありますが、例えば、令和4年公認会計士試験の簿記の出題範囲は、「簿記は、企業等の簿記手続の理解に必要な基本原理、仕訳、勘定記入、帳簿組織、決算及び決算諸表の作成について出題する。」「会計諸規則及び諸基準の範囲には、会社計算規則、財務諸表等規則等の他、基本的には企業会計審議会の意見書及び企業会計基準委員会の企業会計基準を含める」などとされています。
財務会計論は、試験時間120分、200点満点の試験で、個別論点が22問(8点/問)、総合問題が6問(4点/問)です。個別論点では計算問題(簿記)と理論問題(財務諸表論)が約半分ずつ、総合問題は全て連結会計の計算(簿記)です。
計算問題は200点満点中約112点ですので、比較的割合が高いと言えるでしょう。

公認会計士試験の短答試験は、必須受験科目である4科目(財務会計論、管理会計論、監査論、企業法)の平均得点が合格基準点を上回っているかどうかで決まります。そのため、財務会計論1科目、ましてや財務会計論(簿記)のみの合格率を計算することは出来ません。
しかし、公認会計士・監査審査会のホームページ上に、各科目の受験者の平均点が掲載されているため、他の科目と比較した難易度を測ることが可能です。財務会計論の平均得点の推移は、以下の表の通りです。
| 平均得点比率 | 2021年(※) | 2020年Ⅱ | 2020年Ⅰ | 2019年Ⅱ | 2019年Ⅰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 47.3% | 46.1% | 38.9% | 42.6% | 44.2% |
| 財務会計論 | 47.0% | 43.7% | 33.8% | 43.0% | 38.1% |
| 管理会計論 | 40.9% | 46.0% | 34.5% | 37.4% | 44.1% |
| 監査論 | 52.3% | 52.2% | 48.2% | 42.9% | 54.3% |
| 企業法 | 47.8% | 43.5% | 44.2% | 46.4% | 46.9% |
| 合格基準点 | 62% | 64% | 57% | 63% | 63% |
(※)新型コロナウイルスの影響で、短答式試験は1回のみの実施
上記の表から、財務会計論は、過去5回の内3回の試験で四科目中ほぼ最低の平均点となっているため、四科目の中では比較的難易度の高い試験と言えます。
また、財務会計論(簿記)は、簿記と呼ばれるだけあって、少なくとも日商簿記検定1級の商業簿記・会計学の知識が必要と言われています。公認会計士試験は簿記の試験の延長線上にありますが、公認会計士試験の方が難易度は高いと言われています。
他の科目と同様、試験範囲は広くボリューム多いために難易度は高いですが、計算問題は練習量さえしっかりこなせば得点が伸びる分野だと言われています。学習量次第という意味では費用対効果が高いと言えるかもしれません。
下記の通り、財務会計論の合格には1,000時間程度必要と言われていますが、その中の600時間程度は簿記に費やす場合が多いようです。そのため、まずは予備校や参考書を利用して時間を継続することが必要です。
簿記の問題は全て計算問題ですので、とにかく圧倒的な回数の計算演習問題を解くことが重要です。公認会計士試験の予備校では、毎日の朝、答練のスケジュールが設定されていることも多いです。独学をしている方でも、自分で毎日時間を決めて答練すると良いでしょう。
また、よく「簿記はスポーツ」とも言われます。繰り返し計算問題を解くことで、会計処理や仕訳を体で覚えることが、合格への第一歩です。
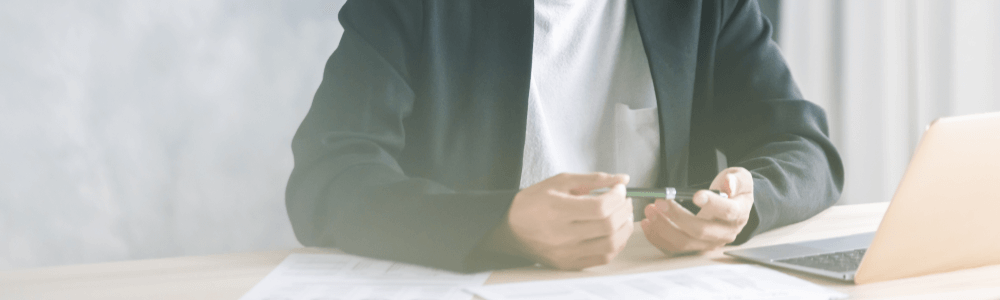
合格には、財務会計論の簿記と財務諸表論を合わせて1,000時間程度の学習時間が必要と言われています。試験範囲には簿記1級の試験内容が丸々含まれるので、1,000時間中400時間程度は簿記の勉強に充てる人もいます。
短答式試験の中では財務会計論の必要勉強時間が最も長く、次いで企業法、管理会計論が並んでいます。このことから、論文式試験を考えても、第一優先で行うべきは財務会計論ということが分かります。
公認会計士試験に合格するための必要学習時間は、3000時間から4000時間と言われています。これは、2年間の学習で試験合格を目指す場合、一日あたり4時間~5時間程度の勉強が必要になります。このことから、財務会計論単体での学習期間を計算すると、2年の間に4ヵ月間~6カ月間程度は財務会計論の学習を行う必要があります。
1年間で短答式に合格、1年間で論文式に合格というスケジュールで進めるのであれば、1年間で4科目(財務会計論、管理会計論、監査論、企業法)を合格レベルまで持っていく必要がありますので、財務会計論には4~6カ月程度の時間を割きつつ、並行して4科目の勉強をしなければならないことに注意してください。
もちろん上記の勉強時間はあくまでも目安であり、より短時間で済んだ・長時間かかったという人もいます。さらに、本番の試験問題との相性で点数が上下する可能性もありますので、時間のみにとらわれるのではなくしっかりした理解を積み重ねることが重要と考えられます。
前述の通り、財務会計論(簿記)の問題は、計算問題のみで構成されています。
勉強のとっかかりとしては、日商簿記検定の勉強から始める人や、公認会計士試験の簿記入門講座からスタートする人が多いようです。計算問題が解けるようになる王道は存在せず、上述の通り、とにかく問題をたくさん解くことが一番の近道です。予備校などのように、毎日答練の時間を取ることが有用です。例えば、「毎日1問総合問題を解く」ことを決めて、たんたんとこなしていく方法をおすすめします。
また、勉強のコツは2点あります。一つ目は、受験生の正答率が低く、かつ出題可能性や重要性の低い計算問題の復習に時間をかけすぎないことです。というのも、財務会計論(簿記)は相対評価なので、周りの受験生の多くが解ける(=誰でも解ける)問題かつ重要性の高い論点を取りこぼさないことが重要だからです。
二つ目は、テキストの例題を仕訳レベルで暗記し理解することです。公認会計士試験の短答式試験とはいえ基礎的な論点や重要性の高い論点は、資格予備校が出しているテキストの例題や章末問題レベルの出題がされることも多々あります。テキストの例題だからといって復習をおろそかにせずに理解と暗記を徹底することが重要です。
実際の財務会計論の試験本番では、まずは最初に11問ある理論問題を解くことをおすすめします。なぜかというと、理論問題は問題文が短く正誤を判断するだけなので解けるかどうかが瞬時に判断可能だからです。まず理論問題を見て、得点できる問題を全てものにすると良いでしょう。
残りの時間で、17問の計算問題を解きます。この時もまずは問題全体を見て、解けそうな問題から解答していきます。他の科目と同様、財務会計論も時間との勝負ですので、捨て問のような難解な計算は極力避けて最短で答えにたどり着けるルートで計算を行うようにしてください。
時間配分は、理論問題を30分程度、計算問題を1時間30分程度とするのが一般的です。問題にざっと目を通したときに、解くべき優先順位をつけることも、事前の模試などで練習しておきましょう。

監査法人に在籍して企業の会計監査を主要業務とする場合には、当然、簿記や財務諸表論に精通している必要があります。例えば、財務諸表がルールに沿って適正に作成されているかを調査する財務諸表監査で、理論への当てはめが容易でない複雑な取引に適用される会計処理が妥当かの判断をする際には、簿記及び財務会計論に対する理解と知識が必要です。
また、M&Aや上場準備監査、IFRS関連の国際業務やその他アドバイザリー業務を提供するにあたっても、財務分析等を行う際や財務モデルを作成する際に財務会計論の知識が必須となります。
一般事業会社等の業務では、例えば経理、財務、税務部門であれば業務の基本となる知識ですし、財務・会計・税務コンサルタントのような職業につく場合でも、財務会計論の知識が役立ちます。このように、財務会計論は会計に関する基本的な内容なので、仮に監査関連業務を行わないとしても、様々なフィールドで活かす事が可能です。
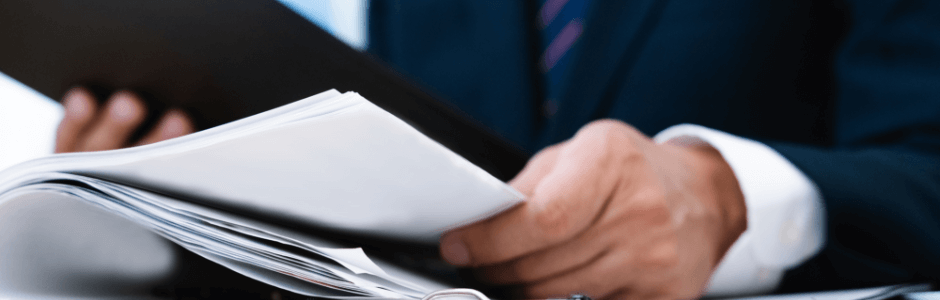
以上の通り、財務会計論(簿記)は、最も長い勉強時間が必要と言われる財務会計論の一部の科目です。会計学や公認会計士試験の中心的な分野であるため、財務会計論(簿記)が得意になることが試験合格への第一歩と言えるでしょう。
試験では時間的制約は大きいですが、計算問題は何度も演習をこなせば確実に点数が伸びる分野です。理論(財務諸表論)とのつながりも意識しながら、こつことと学習をこなしていってください。
本記事を参考に、学習を進められたという方が一人でもいれば幸いです。
まずはキャリアアドバイザーにご相談ください
無料マイナビ会計士に申し込む
まずはキャリアアドバイザーにご相談ください
無料マイナビ会計士に申し込む
キャリアアドバイザーを通じて、ステップアップに成功した転職成功者の方々の事例をご紹介します。
転職をお考えの会計士・試験合格者の疑問や悩み、不安を会計士業界専任キャリアアドバイザーが解消します。
事業会社、監査法人、会計事務所/税理士法人、コンサルティングファームについてをご紹介します。
復職する際の注意点や転職のタイミング、オススメ求人や転職成功事例をご紹介します。
試験合格後から会計士登録の完了までのスケジュールや流れ、登録後にやるべきことなどをご紹介します。
資格取得のメリットや、活躍できるフィールド、転職市場での価値とニーズについてご紹介します。
監査法人から事業会社やコンサルティングファームへの転職方法やポイントなどをご紹介します。

仕事・キャリア
公認会計士は30代・未経験から目指せる?合格率・年収や就職先まで紹介

仕事・キャリア
20代・未経験でも公認会計士は目指せる?メリット・デメリットと成功のコツ

仕事・キャリア
未経験でも会計士のコンサルティングファームで働ける?仕事内容や年収・向いている人を解説

業界情報
会計士試験は何が変わった?2025年6月発表「バランス調整」の内容と受験生がとるべき対応策

仕事・キャリア
公認会計士からPEファンドへ転職するのはおすすめ?役立つ前職のスキル

仕事・キャリア
40代からUSCPAを取得するメリットと、資格を活かしたキャリア戦略

業界情報
【令和8年(2026年) 公認会計士試験第I回短答式試験 結果速報】合格発表後にすべきこと

仕事・キャリア
公認会計士がIPO準備企業ですることは?最新の転職市場やメリットも解説

会計士・試験合格者専門の転職エージェントです。細かなサービス内容をご説明します。

マイナビ会計士の具体的なご利用の流れや登録のメリットなどをご紹介します。

転職のプロがあなたの転職をサポート。会計士業界専任のキャリアアドバイザーをご紹介します。

マイナビ会計士の求人の一部は非公開求人です。求人を公開していない理由などをご紹介します。

はじめての転職で失敗しないためのポイントや、マイナビ会計士の強みをご紹介します。

業界内で再度転職をする際に注意すると良いポイントや、マイナビ会計士の強みをご紹介します。

おすすめ別や資格別に実施中の相談会やセミナーのご紹介、当日までの流れなどをご紹介します。

転職支援サービスをさせていただく中で、求職者のみなさまからいただくご質問をご紹介します。
蓄積された実績や、非公開の企業情報などから条件にマッチした求人をご紹介いたします。
面接・応募書類対策・スケジュール調整など、転職成功へ導くため、
マイナビ会計士は転職をサポートいたします。

マイナビ会計士に申し込む