あなたが理想の会計士になるまで、
私たちは全力でサポートいたします。
蓄積された実績や、非公開の企業情報などから条件にマッチした求人をご紹介いたします。
面接・応募書類対策・スケジュール調整など、転職成功へ導くため、
マイナビ会計士は転職をサポートいたします。

マイナビ会計士に申し込む
論文式試験民法
目次
「民法」は公認会計士試験における選択科目のひとつです。法学部以外の人は、民法について苦手意識を抱いてしまうのではないでしょうか。ただ、要点を押さえて勉強すれば、絶対的な難関でもありません。この記事では、公認会計士試験に出てくる民法の解説をしていきます。
まずはキャリアアドバイザーにご相談ください
無料マイナビ会計士に申し込む
日本国民が一般生活を送るにあたっての、当然の権利についてまとめた法律が「民法」です。民法は相続や商品取引、売買など、主に金銭が関係する活動についてルールを定めています。その範囲は個人間から個人と企業間、企業間など多岐に及びます。民法すべてを学習しようとすれば、その量は膨大になってしまいます。そのため、「民法は難しい」と考えている受験者も多いでしょう。
ただし、公認会計士試験においては、財産権に関する民法しか出てきません。司法書士や弁護士など、法律の専門家の試験と比べれば、出題範囲はかなり狭いといえるのです。
民法は公認会計士試験で選択科目のひとつに設定されています。受験者の9割以上は経営学を選択する傾向にありますので民法を選択する人は少数派だといえるでしょう。
既に司法試験に合格している人や、司法書士、法務部での業務経験がある等、民法を選んでも試験合格上の戦略でマイナスにならないのであれば選択することも問題にはならないでしょう。
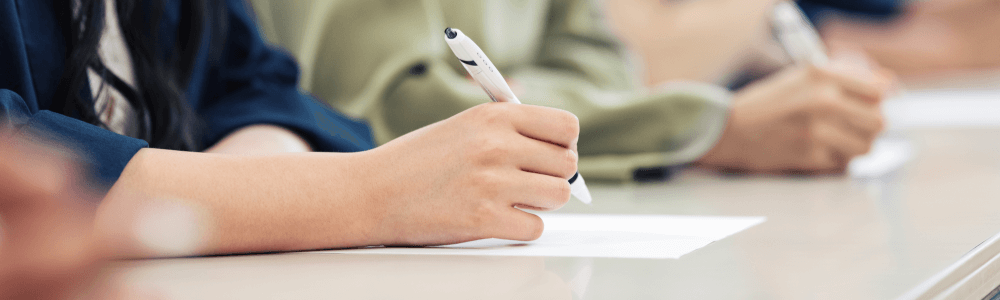
公認会計士試験では、民法で「立法趣旨から用語の定義、各種法律上の論点」などを問われます。いずれも基本的な内容ではあるものの、法律を専門的に勉強してこなかった人にとっては覚えるポイントがたくさんあります。逆をいえば、法学部などで教育を受けてきた受験生には、それほど難しく感じることもありません。さらに、財産や会社法と関係のないテーマはほとんど出題されないので、試験対策を立てやすい科目ともいえます。
注意点としては、出題範囲が広いことでしょう。過去問の内容を丸暗記したとしても、本番で通用するとは限りません。予備校のカリキュラムに沿って効率的に勉強するようにしましょう。
令和3年度試験では、民法の出題範囲はこうなりました。
・民法の分野は、財産法の分野と家族法の分野に大別されるが、このうち財産法の分野、すなわち民法第1編[総則]、同第2編[物権]及び同第3編[債権]並びに関連する特別法を出題範囲とする。
・関連する特別法とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(第1章、第2章、第3章及び第6章)、不動産登記法、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律、仮登記担保契約に関する法律、利息制限法、消費者契約法(第1章及び第2章)、借地借家法、失火ノ責任ニ関スル法律及び製造物責任法である。
家族法(民法第4編[親族]、同第5編[相続])については、家族関係に固有の論点は、当分の間、出題範囲から除外する。また、関連する特別法のうち、不動産登記法における固有の論点は、当分の間、出題範囲から除外する。
民法には「財産法」と「家族法」があります。そして、試験で重要視されているのは財産法のほうです。過去問を見渡しても、財産法を中心に出題するパターンが大半でした。財産法では、個人や法人が所有している財産の譲渡や登記の手続き、消費者間の契約などが問われます。ただ、試験本番で応用問題が出されることはあまりありません。基本的には、専門用語の意味や理論を問われることになります。出題範囲も狭く、予習の見通しをつけやすい科目だといえるでしょう。
民法の問題は論述形式になっています。企業法と同様に一定の事例に応じて、民法の条文を参照しながら記述を行います。法学部などで法律に関する論述を鍛えた人であれば試験形式に大きな抵抗はないでしょう。

民法は公認会計士の試験の選択科目であり、ここでの正解率だけで合否が決まるというわけではありません。全体の中では得点の比重が高いわけでもなく、十分に他の科目で挽回可能です。受験生の多くはより比較的難易度が低いとされている経営学を選んでいますので仮に民法でつまずくことがあれば、経営学を選んだ受験生に差をつけられかねません。つまり、民法で合格が決定づけられるわけではないとはいえ、大きな失態も許されない科目です。
選択科目の中で「民法は難易度が高い」とする人もいます。その理由は、民法が公認会計士の基礎知識からやや離れていると感じられるからです。確かに、財産法は経理や会計の知識がそのまま出てくるわけではありません。他の科目との関連性が低いので、対策が大変だと感じる人もいるでしょう。しかし、民法は出題範囲が狭く、その内容も限られています。もしも大学や大学院で民法を学んできたのであれば、新しい情報はほぼ出てきません。むしろ、高得点を狙える科目ですらあります。
それに、民法に限らず、選択問題は解答がやや簡単になる傾向があります。結論を書けば、民法は多くの人にとってなじみのない科目ですが、得意な人や慣れている人にとっては比較的高得点を狙える科目のひとつでしょう。
民法はTAC等の通信講座や予備校で勉強するのがおすすめです。これらのサービスでは専用のテキストを用意してくれるので、勉強の計画を立てやすくなります。必要最小限の労力で民法の出題範囲をカバーできるため、時間を効率的に使えます。そうやって省略できた時間を、より難易度の高い科目に使うのもいいでしょう。分からないところや疑問点が出てきたとき、相談できる相手がいるのも大きなメリットです。
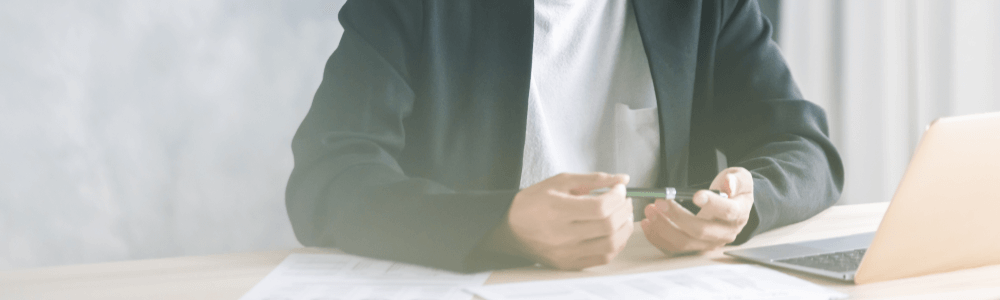
あくまでも目安であるものの、民法の勉強時間は400~500時間程度とされています。他の選択科目では試験のために200~300時間ほどの勉強が必要とされているため、約2倍近くの負担になるでしょう。この勉強時間は、「選択科目で民法を選ぶべきではない」という言説につながっています。民法は範囲が広く、覚える箇所が多いとの意見も少なくありません。ちなみに、司法書士試験では民法を700時間程度勉強するべきともいわれており、このことも民法への苦手意識を招いています。
ただ、実際には民法を選ぶ受験生の多くは、大学や大学院である程度の知識を得ています。それに司法書士試験と違い、公認会計士の試験では民法を深く掘り下げていくわけではありませんので、得意な方であれば3~4カ月前から民法に着手しても、本番には間に合います。ただし、自力で勉強するには非効率的ではあるので通信講座や予備校の力を借りるのが普通です。
民法の勉強では通信講座や予備校が用意してくれる、専用テキストを使うのが理想です。これらのテキストは出題範囲が丁寧にまとめられているので、効率的です。テキストを理解したら問題集を解き、間違えた個所を復習していくようにします。
民法を勉強するコツは、いたずらに勉強範囲を広げないことです。時間に余裕があれば、ついテキスト以外の範囲にも手を広げたくなるでしょう。しかし、そもそも選択科目は配点がそれほど高いわけではないので、高得点を獲得できたとしても合否を決定づけられるわけではありません。選択科目は平均以上の正解率を目指し、他の科目で勝負をかけるのが合格の秘訣です。もしも本番までに余裕ができたと思ったら、別の科目に力を入れるのが得策です。
民法は基礎的な内容をテキストで勉強するのが定石です。民法で得点比率が若干下がったとしてもより配点の高い科目で取り返せばまだ合格の可能性は残ります。
重要な論点を完璧に論述できるように、テキストと答練をひたすら解くことがベストです。

公認会計士の試験で民法を選ぶメリットは法律の専門的資格や学習をした経験のある方にとっては「実務のプラスアルファになること」でしょう。もちろん、公認会計士の重要な仕事である監査業務と、民法はあまり関係がないともいえるでしょう。
しかし例えば、会計に加えて民法の素養があれば、例えばM&Aアドバイザリー業務における株式譲渡契約書の交渉において、民法の知識を活用して弁護士とのコミュニケーションを円滑に進めることも可能でしょう(例:買収対象会社の債権の時効に関する項目、表明保証等)。
民法はビジネスマンとしての公認会計士にとって差別化できる知識となり、直接的に監査業務で民法を利用することがなくても、そこで得た知識を参考にするケースはありえるのです。法律関連業務を行わないとしても、民法の学習内容を活かし、将来的に業務で活かす事が出来ます。
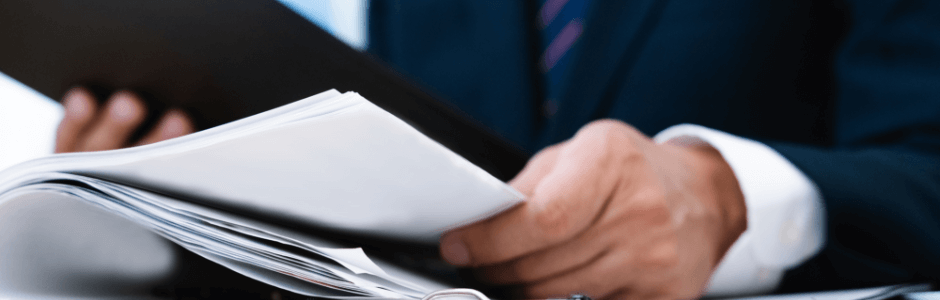
公認会計士が民法を幅広く応用するチャンスは、それほど多くないかもしれません。しかし、もともと法律の素養がある方なら、民法を選択科目とした場合は出題範囲を絞りやすいというメリットがあります。
まずはキャリアアドバイザーにご相談ください
無料マイナビ会計士に申し込む
まずはキャリアアドバイザーにご相談ください
無料マイナビ会計士に申し込む
キャリアアドバイザーを通じて、ステップアップに成功した転職成功者の方々の事例をご紹介します。
転職をお考えの会計士・試験合格者の疑問や悩み、不安を会計士業界専任キャリアアドバイザーが解消します。
事業会社、監査法人、会計事務所/税理士法人、コンサルティングファームについてをご紹介します。
復職する際の注意点や転職のタイミング、オススメ求人や転職成功事例をご紹介します。
試験合格後から会計士登録の完了までのスケジュールや流れ、登録後にやるべきことなどをご紹介します。
資格取得のメリットや、活躍できるフィールド、転職市場での価値とニーズについてご紹介します。
監査法人から事業会社やコンサルティングファームへの転職方法やポイントなどをご紹介します。

仕事・キャリア
公認会計士は30代・未経験から目指せる?合格率・年収や就職先まで紹介

仕事・キャリア
20代・未経験でも公認会計士は目指せる?メリット・デメリットと成功のコツ

仕事・キャリア
未経験でも会計士のコンサルティングファームで働ける?仕事内容や年収・向いている人を解説

業界情報
会計士試験は何が変わった?2025年6月発表「バランス調整」の内容と受験生がとるべき対応策

仕事・キャリア
公認会計士からPEファンドへ転職するのはおすすめ?役立つ前職のスキル

仕事・キャリア
40代からUSCPAを取得するメリットと、資格を活かしたキャリア戦略

業界情報
【令和8年(2026年) 公認会計士試験第I回短答式試験 結果速報】合格発表後にすべきこと

仕事・キャリア
公認会計士がIPO準備企業ですることは?最新の転職市場やメリットも解説

会計士・試験合格者専門の転職エージェントです。細かなサービス内容をご説明します。

マイナビ会計士の具体的なご利用の流れや登録のメリットなどをご紹介します。

転職のプロがあなたの転職をサポート。会計士業界専任のキャリアアドバイザーをご紹介します。

マイナビ会計士の求人の一部は非公開求人です。求人を公開していない理由などをご紹介します。

はじめての転職で失敗しないためのポイントや、マイナビ会計士の強みをご紹介します。

業界内で再度転職をする際に注意すると良いポイントや、マイナビ会計士の強みをご紹介します。

おすすめ別や資格別に実施中の相談会やセミナーのご紹介、当日までの流れなどをご紹介します。

転職支援サービスをさせていただく中で、求職者のみなさまからいただくご質問をご紹介します。
蓄積された実績や、非公開の企業情報などから条件にマッチした求人をご紹介いたします。
面接・応募書類対策・スケジュール調整など、転職成功へ導くため、
マイナビ会計士は転職をサポートいたします。

マイナビ会計士に申し込む