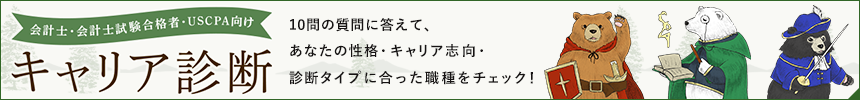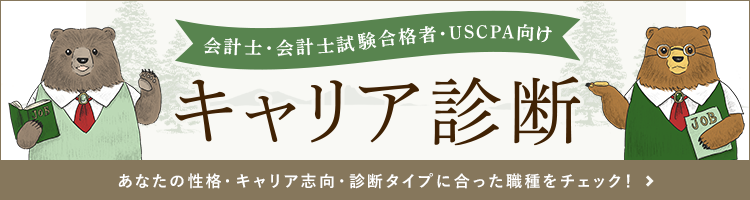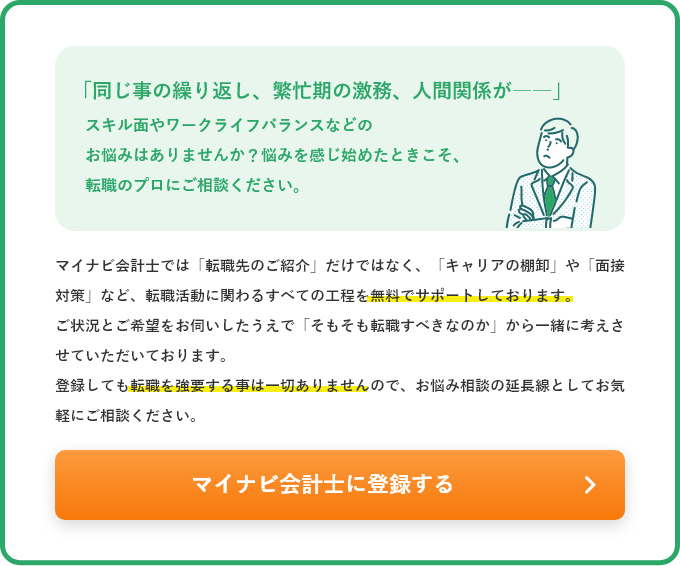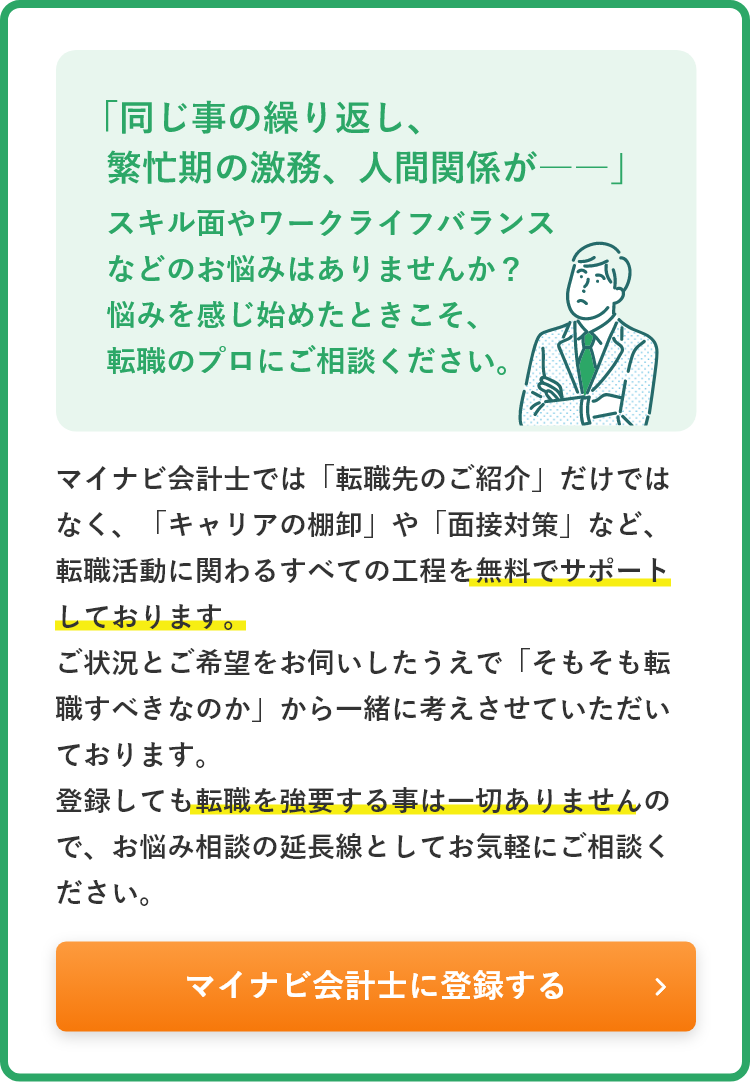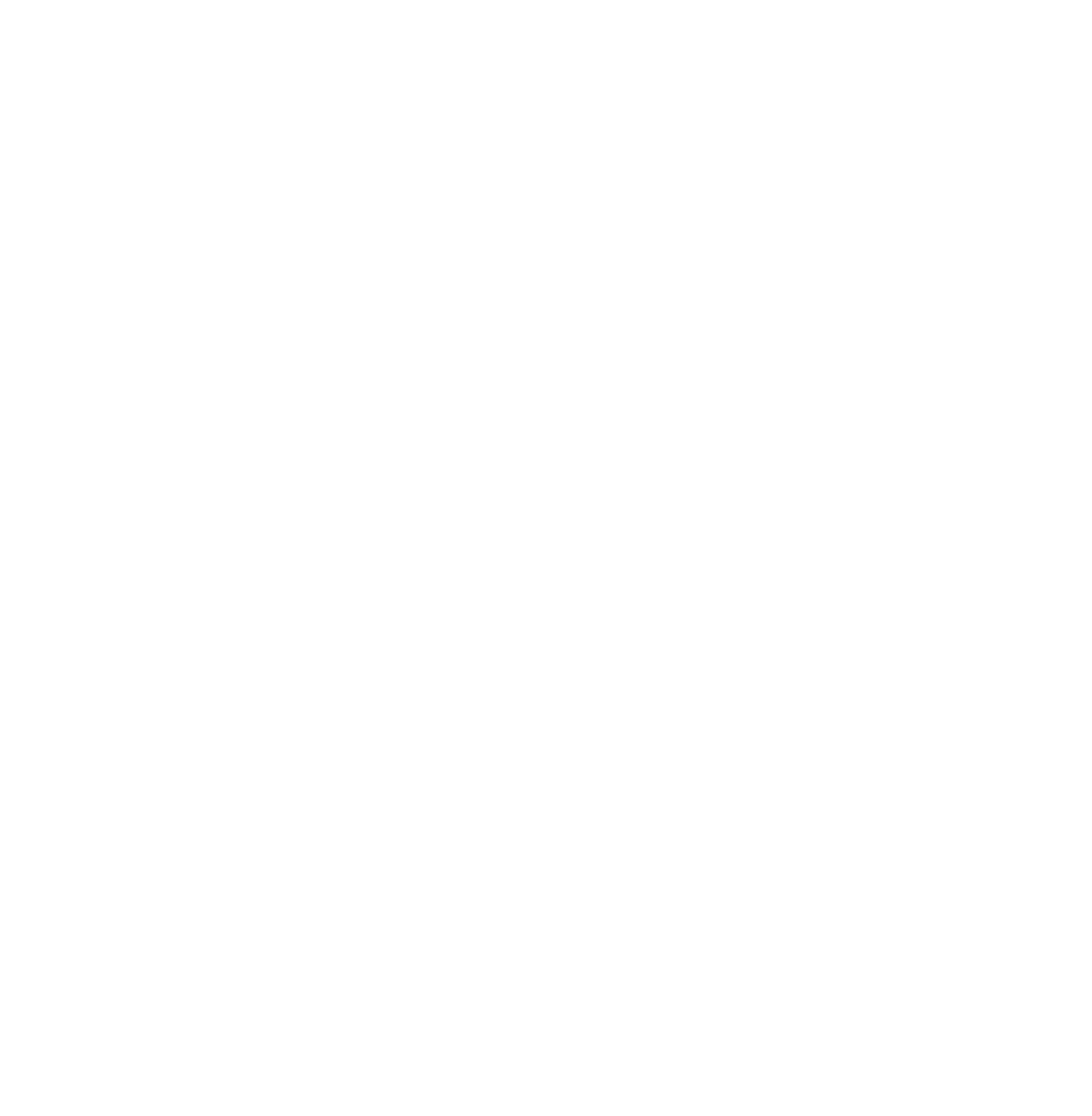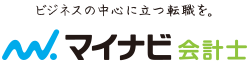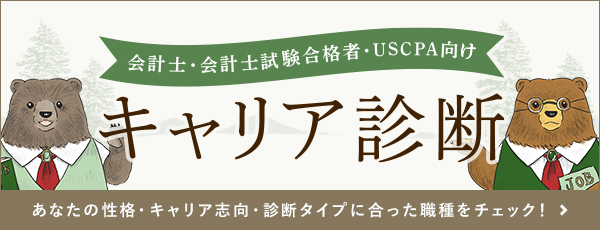内部監査に向いている人・向いていない人の特徴|鍛え方やキャリアパスも解説
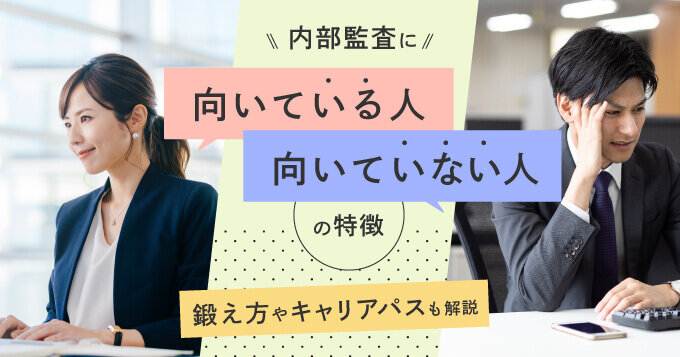
「内部監査が自分に合っているのか確信が持てない」と気になりお調べですね。内部監査は、企業のリスク管理、ガバナンス、内部コントロールのプロセスを評価する専門的な職務です。不正や不祥事を未然に防止する体制構築に不可欠な存在ですが、これには多岐にわたる知識とスキルが必要となります。
そのため、自分の強みや弱みを理解していないと、求められる業務に対して最適なアプローチを取ることが難しくなり、効率的に仕事を進めることができなくなるかもしれません。結果として仕事のパフォーマンスだけでなく、やりがいや満足度も低下する可能性があります。
そこで、この記事では、内部監査に向いている人・向いていない人の特徴を詳しく解説します。また、内部監査の仕事内容や必要な知識、スキルの磨き方にも触れるため、ぜひ最後までご一読ください。

マイナビ会計士編集部
マイナビ会計士は、公認会計士・試験合格者・USCPAの方の転職サポートを行なう転職エージェント。業界専門のキャリアアドバイザーが最適なキャリアプランをご提案いたします。Webサイト・SNSでは、公認会計士・公認会計士試験合格者・USCPAの転職に役立つ記情報を発信しています。
目次
そもそも内部監査とは
内部監査とは、企業の内部統制が適切に機能しているかを評価する業務のことです。内部統制とは、企業がその業務を法令遵守、倫理規範の遵守、リスク管理の徹底といった原則に基づき、持続可能かつ責任ある方法で行うために定められた内部統制システムやガバナンス構造の総体を指します。
内部監査では企業内部の人間を内部監査人とし、この内部統制が正しく機能しているのかを調べて、不正や不祥事を未然に防止するために行う監査を行います。
内部監査の主な役割は、以下のとおりです。
- 内部統制の有効性と効率性の評価
- リスク管理プロセスの評価
- 業績目標の達成度の評価
- 法令遵守の確認
一方で外部監査は、外部の専門家が企業に対し、財務諸表が公正かつ適切に表示されているかを評価するためのものです。主に、企業のステークホルダー(株主、債権者、投資家など)に対して、企業の財務状況が正確に報告されていることを保証する役割を果たします。なお、こうした違いや内部監査の基本については、ぜひ下記ページもご覧ください。
関連記事
監査の基本!内部監査の基礎知識
内部監査の仕事内容
内部監査の仕事内容は、以下のとおりです。
- 経営活動の監査
- 内部統制の評価と改善
- リスク管理の支援
- 法令遵守の確認
- フォローアップ
抜擢された内部監査人は、詳細な財務レビューや運営プロセスの精査を行い、内部統制の実効性を評価します。これにより、企業の資産保護を図りつつ、経営の効率化を推進します。さらに、不正行為の予防や検出、法令遵守の徹底など、潜在的リスクを早期に特定し、それらを最小限に抑えることで、企業の持続可能な成長を支援する重要な役割を担うことになるでしょう。
内部監査の仕事内容だけ見ると、複雑に感じるかもしれません。確かにそれぞれの監査は細かいですが、大まかには以下の流れで業務を進めます。
- 監査計画の作成:監査対象となる部門やプロジェクトを決定し、監査の目的と範囲を定める
- 監査の実施:決定した監査対象に対して、文書の確認や関係者へのヒアリングなどを行う
- 監査報告書の作成:監査の結果をまとめ、監査結果と改善提案を含めた監査報告書を作成
- フォローアップ:改善提案が適切に実施されているかを確認し、フォローアップする
このように、内部監査は企業の各部門やプロセスを詳細に調査します。その後、問題点や改善点を見つけ出した結果や改善策を経営陣に報告・提案するのが基本です。しかし、その一方で、高度な専門知識と分析力が求められるため、自己啓発の意識も必要とされます。では、内部監査に求められる知識・スキルを見てみましょう。
内部監査に求められる知識・スキル
内部監査は、企業の透明性を確保し組織の成長を支える重要な職務であり、その遂行者には主に以下の知識とスキルが求められます。
- 財務・会計の知識
- 法務に関する知識
- 社業への理解と知識
- 対人スキル
- 実務スキル
財務・会計の知識
まず、内部監査における「財務・会計の知識」は、企業の経営状況を正確に把握し、適切な意思決定をサポートするために不可欠です。具体的には、以下が挙げられます。
- 財務報告の作成と解析
- 予算策定
- コスト管理
- 財務リスクの評価
それぞれは、内部監査のプロセスである「監査計画の作成」「監査の実施」「監査報告の作成」の各所で活用されます。また、財務報告の正確さを保証するため、アメリカで制定されたSOX法に基づいて日本でも作られた「J-SOX法」についての理解も非常に重要です。
法務に関する知識
次に、内部監査の際にはリスクを適切に管理するため、「法務の知識」も欠かせません。リスクとは、法律違反や不正な行動、事故、自然災害、市場の変動など様々なものがあります。そのため、関連する知識としては以下が挙げられるでしょう。
- 法律や規制の解釈
- 法的リスクの評価
- 法令遵守に必要なポリシーや手続きの策定
先ほどの財務・会計の知識と同様に、内部監査の担当者はこうしたリスクを見つけ出して、それらがどれほど重要かを判断し、適切な対応策を立てます。また、コンプライアンスの確保を徹底することで、企業の信用や社会からの評価を上げることができるだけでなく、法的な問題や経済的な損失を未然に防ぐことにも繋がります。
社業への理解と知識
意外に見落としやすいのが、「社業への理解と知識」です。内部監査におけるこの評価と改善の作業は、企業がより高い成果を出し、競合他社との差をつける手立てとなるものです。例を挙げると、以下の対応する事業に関連する広範な知識が該当します。
- 企業の業務プロセス
- 業界の動向
- 競合状況
- 製品やサービスの特性
内部監査担当者は、各部門の業務に関するデータや情報を集め、分析を行い、そのプロセスがどれだけ効果的で効率的か、合理的かを検証します。そして、先に触れたリスクや問題点、改善すべき箇所を見つけ出し、プロセスをより良くするための提案も実施するためにも、こうした知見が必要です。
対人スキル
「対人スキル」も、内部監査の業務を遂行する上で必要不可欠なスキルの1つです。主に、監査対象者とのコミュニケーション、情報収集、対立解決、チーム管理など、他者との関わりを円滑に進めるための能力を指します。例としては、客観性と偏見のない独立性や観察力に加えて以下が挙げられるでしょう。
- コミュニケーション
- ファシリテーション
- マネジメント
- コーチング
- リーダーシップ
内部監査の過程で重要になるのは、監査対象となる部署や経営層と信頼を築き上げることです。また、チームで行う仕事であるため、同僚や上司との円滑なコミュニケーションも欠かせません。適切な距離感でヒアリングし、中身のある、そして説得力のある報告書を作成するには対人スキルが求められます。
実務スキル
最後に、「実務スキル」は、内部監査の効率性と効果性を高めるために必要なスキルです。主に、業務を遂行する上で必要となる以下の技術や能力を指します。
- プレゼンテーションスキル
- ライティングスキル
- タイムマネジメントスキル
内部監査業務においては、単に文章を作成するだけではなく、専門的な知見をもとにした情報の整理・分析・伝達が求められます。そのためには、業務プロセスや内部統制システムに関する深い理解をベースに複雑な情報を効率的に整理し、それを分析する実務スキルが不可欠です。結果、専門的な視点と洞察力を活かし、組織に対する有益な提言を実現できます。
内部監査に向いている人に当てはまる8つの特徴
内部監査に向いている人に当てはまる特徴には、以下の8つが挙げられます。
- 経営に興味・関心がある人
- 優先順位をつけて働ける人
- コミュニケーションや連携が得意な人
- 論理的に物事を考えられる人
- 物事を俯瞰して見られる人
- 法律や規則を守る姿勢がある人
- 豊富な実務経験や経営者視点がある人
- 支援を得意とする人
- AIやデータアナリティクスに抵抗がない人
すべてに当てはまる必要はなく、また該当しないからといって適性がないとは言えません。あくまでもよく見られる傾向の1つとして、ぜひ参考にしてください。
経営に興味・関心がある人
内部監査で働くことでその視野を広げ、経営に関する深い理解を得られることから、経営に興味・関心がある人に向いていると言えます。企業のビジョンや戦略を理解し、それに基づいて意思決定を行う能力を養えるためです。
内部監査では、企業の業績やリスク管理、コンプライアンスなどを評価するため、経営の視点からの分析が求められます。また、多くの企業の経営状況を把握しつつその問題点を指摘し、解決策を提案することも良い経験となります。
このことから、将来的に経営陣として働きたい、自分の会社を立ち上げたいなど、経営に携わるキャリアプランを目指している人にとって、内部監査はキャリアプランを実現するための大きな一歩となるでしょう。
優先順位をつけて働ける人
優先順位をつけて働ける人も、内部監査に向いていると言えます。内部監査は多くのプロジェクトを同時に進行させる必要があり、それぞれに対して適切な優先順位をつける能力が求められるためです。
実際の業務では、企業に創設された部門やプロジェクトを監視・評価し、それぞれ異なるリスクや課題を見抜く必要があります。そして、リスクや課題に対して適切な優先順位をつけ、効率的にプロジェクトを進行しなければなりません。
- 複数のタスクを同時に管理する
- タスクの重要性や緊急性を判断する
- 効率的なタスクの進行順序を決定する
などが得意な場合は、内部監査における業務の煩雑さにも十分に対応できるでしょう。
コミュニケーションや連携が得意な人
内部監査では、コミュニケーションや連携が得意な人も向いているでしょう。企業の様々な部門と連携し、また、監査結果を関係者に伝えるためにコミュニケーション能力は不可欠です。
内部監査は改善案を見つけては指摘・指導の繰り返し、いわば「粗探し」とも取られやすい仕事です。どれだけリスク管理やガバナンスの改善を目指すためとはいえ、折衝や明確で効果的なコミュニケーションができなければ、提案を快く受け入れてもらえないでしょう。
そのため、他人とのコミュニケーションを楽しめる、またはチームでの作業を好む人や、他人の意見を尊重し、自分の意見を適切に伝える能力が高い人に向いていると言えます。
論理的に物事を考えられる人
内部監査においては、論理的に物事を考えられることも向いている人の特徴です。実際の業務では、企業の業務プロセスや内部統制の有効性を評価するために、多くの情報を分析する必要があります。
そのため、情報を整理しつつ原因と結果の関係を理解し、効果的な解決策を導き出す論理的な思考力が求められます。このことから、これまでに特定の問題解決の経験がある人や、データから打ち出された信頼性の高い提案を続けてきた人は、特に適していると言えるでしょう。
物事を俯瞰して見られる人
内部監査はその業務の細かさとは裏腹に、物事を俯瞰して見られることも向いている人の特徴です。1つの業務やリスクに対しての改善案に限らず、全体視野を持つことで部分的な視点では見えない問題や改善点まで発見できるためです。
実務では、業務プロセスや内部統制の有効性において、あくまでも部署・部門を単独ではなく、企業全体として捉えて評価するために全体を俯瞰します。自分自身の主観や先入観に囚われず、事実に基づいて判断すること、これが公正かつ正確な監査結果につながるのです。
このように、「細かい問題」から「大きな区画の全体像を見て」から問題を解決できる、などの物事を俯瞰して見られる人は、内部監査でも十分なやりがいを感じやすいでしょう。
法律や規則を守る姿勢がある人
内部監査は、法律や規則を守る姿勢がある人にも向いています。企業が法律や規則を遵守しているかを確認するために、就業規則や社内規程などのルールを理解し、それに基づいて業務を行う性質を持つからです。
また、企業倫理や社会的規範に沿った行動・活動を行うことも求められます。こうした姿勢を持つ人は、自然に法律や規則に敏感になれるため、変更にも迅速に対応しつつ企業を適切に評価できるでしょう。まわりに流されず独立性を保ち、とはいえ一定の柔軟性を兼ね備えている場合、他人に良い影響を与えることができます。
豊富な実務経験や経営者視点がある人
内部監査においては、豊富な実務経験や経営者視点がある人にも向いています。内部監査の業務では、組織のリスクマネジメントや内部統制、ガバナンスプロセスを評価し、改善策を提案します。また、組織の経営目標達成に向けた付加価値の提供も求められる業務です。
これらの業務を遂行するためには、組織全体の業務プロセスやリスクを理解し、それに基づいて評価や改善策を提案する能力が必要です。
- データ分析や会計監査の経験が豊富
- 経営層とのコミュニケーション経験がある
- 過去に経営者やマネジメントの経験がある
など、豊富な実務経験や経営者視点によって裏打ちされることで説得力も高まり、内部監査の役割を効果的に果たして組織の成長と改善に貢献できるでしょう。
支援を得意とする人
他にも、内部監査には支援を得意とする人も向いています。他の部署やプロジェクトを支援する視点は、評価や改善策の提案につながりやすいためです。また、組織内の多様なステークホルダー間でのコミュニケーションや協力も促進できます。
こうした支援が得意な人は、高いコミュニケーション能力や協調性によって、聞き手の立場に立って情報を伝えつつ信頼関係を構築しやすいです。組織内の変更を促進し、それに伴う不安や抵抗を軽減するためのサポート戦略を立てて実行も支援できます。組織内での建設的な変化を促進し、組織の目標達成に寄与できる点を踏まえても非常に向いていると言えます。
AIやデータアナリティクスに抵抗がない人
最後に、AIやデータアナリティクスに抵抗がないという人も内部監査に向いています。会計業務の領域においては、従来の手作業によるデータ入力作業から大きく進化を遂げた「クラウド会計ソフト」の導入が進んでいます。
さらには、AIおよびRPA技術による作業の効率化、データ分析やアナリティクスによる深い分析と洞察も求められる環境です。そのため、基本を理解できるだけに限らず、実際に活用して業務を効率的に行うためにもこうした分野に明るい必要があります。
もちろん、導入しているツールや手法は企業ごとに異なるものです。そのため、技術の概観を理解しつつ、その活用することを恐れない人材であることが向いている人の特徴と言えるでしょう。
関連記事
内部監査の求人情報
内部監査に向いていない人に共通する4つの特徴
一方で、内部監査に向いていない人に共通する人の特徴には、以下の4つが挙げられます。
- コミュニケーションや連携が苦手な人
- 指摘・指導に抵抗感がある人
- 全体像を把握するのが苦手な人
- ITリテラシーが低い人
向いている人と同様に該当したから適性がないというものではなく、意識的に伸ばせば十分に解決できるものです。あくまでも、合わないかもしれないという例であることにご留意ください。
コミュニケーションや連携が苦手な人
まず、コミュニケーションや連携が苦手な人は、内部監査には向いていないかもしれません。内部監査の業務は単に黙々と作業をこなすだけではなく、組織内の多くの人と関わりや、ヒアリングを行うことが求められるからです。
内部監査では、組織の各部門から情報を集め、それを基に監査を行います。そのため、各部門の人々と良好な関係を築き、適切なヒアリングを行う能力が求められるでしょう。また、信頼関係がなければ、監査結果を受け入れてもらうことは難しくなります。
指摘・指導に抵抗感がある人
また、指摘・指導に抵抗感がある人も、内部監査の業務に苦手意識を持つかもしれません。内部監査では立場に関係なく、あらゆる人に対し指摘を行うことが求められるからです。指摘・指導では、経営者ならびに上司を含む組織の上層部に対しても、公平かつ客観的な評価を提供することを要求されます。
たとえ苦手意識があったとしても、組織の透明性を高めてリスクを管理し、全体としてのパフォーマンスを向上させるために不可欠です。抵抗感を抱く人もいるかもしれませんが、責務の一環として割り切れる気持ちの強さが必要でしょう。
全体像を把握するのが苦手な人
内部監査では、全体像を把握するのが苦手な人も向いていないことがあります。内部監査では、細かい部分に注目するだけでなく、物事全体を概観する能力が求められます。
個々の業務やプロジェクトの詳細に目を通すだけでなく、それらが全体としてどのように機能しているのか、つまり全体の流れや構造を理解しなければなりません。そのため、個別のプロセスや成果において、組織全体の成績や戦略的目標にどのような影響をおよぼしているのかを考える癖をつけると良いでしょう。
ITリテラシーが低い人
最後に、ITリテラシーが低い人も内部監査に向いていない可能性があります。昨今では、以下の観点からITリテラシーを求められる場面が多いからです。
- データ分析
- システム監査
- ITリスク管理
内部監査では、組織の業績やリスクを評価するために、大量のデータ分析が必要です。また、組織のITシステムの適切な運用を監査するためには、システムの仕組みを理解する必要もあります。
さらには、GDPRやCCPAなどのサイバーセキュリティの脅威や、データ漏えいのリスクを評価し、それに対する対策を立てるためにもITリテラシーがその基盤となるものです。昨今では、ITパスポートを筆頭に関連資格が増えたり、書籍も出版されたりしているため、自主的な学習を継続しましょう。
内部監査に必要な知識やスキルを磨く方法
では、内部監査に向いている人、向いていない人を踏まえて、どうすれば成長できるのでしょうか。内部監査に必要な知識やスキルを磨く方法を、以下の2つに分けて紹介します。
- 資格を取得する
- スキルを磨ける企業で働く
資格を取得する
まず、内部監査に向いている人材であることを伝える際に役立つのが資格の取得です。専門性を証明できるだけでなく、自身のスキルを高めるためにも有効な手段となります。例えば、以下は内部監査に関する資格のなかでも一般的なものです。
- 公認内部監査人(CIA):国際的な資格。基本的な知識からリスク管理、ガバナンス、内部統制まで幅広い知識を証明できる
- 内部監査士(QIA):内部監査に特化した資格。基本的な知識や技術、内部統制の理解などを証明できる
それぞれの資格を取得するタイミングは、内部監査のキャリアを本格的にスタートさせる前、または内部監査の業務に携わり始めた初期段階が最適です。資格取得には一定の時間と労力が必要ですが、その労力は自身のスキルアップとキャリアアップに直結します。
また、資格の取得はあくまでも1つの手段です。そのため、学習中であってもしっかりとその内容を伝えることができれば、十分なアピールポイントとなります。資格について詳しくは、下記ページも参考にしてください。
スキルを磨ける企業で働く
次に、内部監査または関連する業務を行っている企業で働くことで、実務面のスキルを高めることができます。未経験や資格がない状態であっても、基本的な業務から始め、徐々に難易度の高い業務に挑戦することで内部監査の知識や技術を深めることができます。
また、内部監査の業務と並行して、リスク管理やコンプライアンスなどの業務も経験して視野を広げることも可能です。このように、キャリアプランの1つとして悩んだ際には、まず働いてみることも検討しましょう。
内部監査の知識や技術は、企業の業種や規模に関わらず、幅広く活用できます。そのため、内部監査の経験を活かして新たな業界や職種に挑戦することで、自身のキャリアをさらに広げることもできます。少しでも不安を感じた際には、マイナビ会計士へご相談ください。現在の状況、技術や経験、さらにはキャリアプランを踏まえて柔軟にご提案いたします。
内部監査に向いている人に関するFAQ
最後に、内部監査に向いている人に関するFAQへ回答します。
- 内部監査はきついですか?
- 内部監査のやりがいは?
- 内部監査は出世コース?閑職・左遷先?
- 内部監査の年収は?
- 内部監査は子育てと両立できる?
- 内部監査から目指せるキャリアパスは?
- 内部監査の将来性は?
内部監査はきついですか?
内部監査の仕事は、コミュニケーション能力が高い人にとっては特にきついとは感じないでしょう。特に、他部署から別の部署に対して指摘・指導をためらう場合や、監査結果に対する反発がある場合などは、コミュニケーション能力が試される瞬間です。
また、内部監査の仕事は、企業の業務プロセスや内部統制を評価し、リスク管理、ガバナンス、内部統制の改善を目指す役割を果たします。そのため、一部の人にとっては難易度が高いと感じるかもしれません。
これらを踏まえると、コミュニケーション能力が高く、他人との関係構築を楽しむことができる人、また、複雑な問題を解決することに喜びを感じる人にとって、内部監査はやりがいのある仕事です。
内部監査のやりがいは?
内部監査のやりがいは、組織全体に貢献できること、社会的な使命感を持って働くことができること、そして自己成長や成果を実感できることにあります。
内部監査は、組織全体の業務効率やリスク管理の改善に寄与でき、組織の信頼性や持続可能性にも貢献できます。自分の提案が組織の成長につながるという実感は、内部監査の仕事を通じて得られる大きな達成感と、相応のやりがいを感じられるでしょう。詳しくは、下記ページもご覧ください。
関連記事
公認会計士が感じている仕事のやりがいは?
内部監査は出世コース?閑職・左遷先?
組織の運営における問題を未然に防いで業務効率の向上を図るなど、経営陣に対して有益な洞察と提案を提供するため、決して閑職や左遷先ではなく、組織の成功に不可欠なポジションと言えます。
内部監査は、組織のリスク管理、ガバナンス、内部統制の効果を評価し、組織の改善に貢献する重要な役割を果たすものです。それぞれの役割を通じて、内部監査は組織の運営における問題を未然に防ぎ、業務効率の向上を図ります。このように、組織の成長や競争力強化に直結し、組織の出世コースとも言える重要なポジションです。
内部監査の年収は?
内部監査の年収は、マイナビ会計士が有する求人調べではおおよそ400万円から1,000万円です。内部監査の職務は、組織のリスク管理やガバナンスの評価、内部統制の効果の評価など、組織の運営における重要な役割を果たします。そのため、その責任と専門性を反映した年収が設定されています。
具体的な年収は、組織の規模や業界、地域、経験年数などにより異なるため、具体的な数値を知りたい場合は、下記から求人情報をチェックしてみてください。
内部監査は子育てと両立できる?
内部監査の職務は、子育てと両立可能です。ただし、職場の環境や制度、そして個々の時間管理能力に大きく依存します。内部監査は、組織内の様々な部署やプロジェクトを監査するため、業務の柔軟性も持っています。そのため、必要に応じて業務時間を調整したり、リモートワークを活用したりすることも可能です。
また、一部の企業では、育児休業、短時間勤務、リモートワークなど、育児と仕事の両立を支援するための制度を設けています。しかし、それぞれの制度を活用するだけでなく、自身の時間管理能力も重要となります。しばしば複雑で時間を要するため、効率的に業務を進めるためのスキルも高めておきましょう。気になる方は、下記ページもぜひ参考にしてください。
内部監査から目指せるキャリアパスは?
内部監査の職務から目指せるキャリアパスは、主に以下の2つです。
- 経営幹部
- 内部監査のスペシャリスト
組織全体の運営やリスク管理、内部統制、ガバナンスプロセスなどの知識と経験は、経営幹部としてのキャリアを目指す上で非常に有用です。一方、内部監査のスペシャリストとしてのキャリアパスを目指す場合、その専門性を深めることが求められます。また、法務に関する知識や社業への理解も必要とされます。
ただし、あくまでも2つは例であり、その他にも多くのキャリアパスが存在するものです。そのため、スタートアップやIPOをめざすベンチャーなど、新たなキャリアパスを模索することも可能です。詳しくは、下記ページもご覧ください。
内部監査の将来性は?
内部監査の将来性は、非常に高いと言えます。なぜなら、組織のリスク管理、統制体系の強化、ガバナンスの改善、およびコンプライアンスの確保という重要な役割を担っているからです。
近年、企業の経営環境は急速に変化しており、その中でリスク管理の重要性が増しています。企業の成長や存続には、リスクを適切に管理し、それに対応する能力が求められます。そして、内部監査は、そのリスク管理を支える役割を果たすものです。そのため、内部監査の専門性と経験を持つ人材の需要は、今後も増えていくと考えられます。将来性について詳しくは、下記ページもご覧ください。
まとめ
内部監査は、財務・会計の知識、法務に関する知識、経営への理解、対人スキル、そして実務スキルを求められる仕事です。そのため、経営に興味があり、優先順位をつけて働くことができ、連携やコミュニケーションが得意である等、特定の特質を持つ人が向いていると言えます。
一方、コミュニケーションが苦手だったり、指摘や指導を嫌がったり、全体のビジョンを把握するのが難しい人、ITリテラシーが低い人は、内部監査の業務を進める上で苦労するかもしれません。知識やスキルは、資格取得やスキルを磨ける企業での実務経験を通じて行うと良いでしょう。
内部監査の仕事は全体像を見渡し、企業の成長と安定に貢献するやりがいとともに、知識だけではなく適性も必要となるため、一定の厳しさも伴う職種です。自分自身の成長を追求しながら、組織全体の向上に貢献する内部監査の仕事に興味がある場合は、ぜひ挑戦してみてください。
マイナビ会計士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
マイナビ会計士とは?
マイナビ会計士は会計士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。