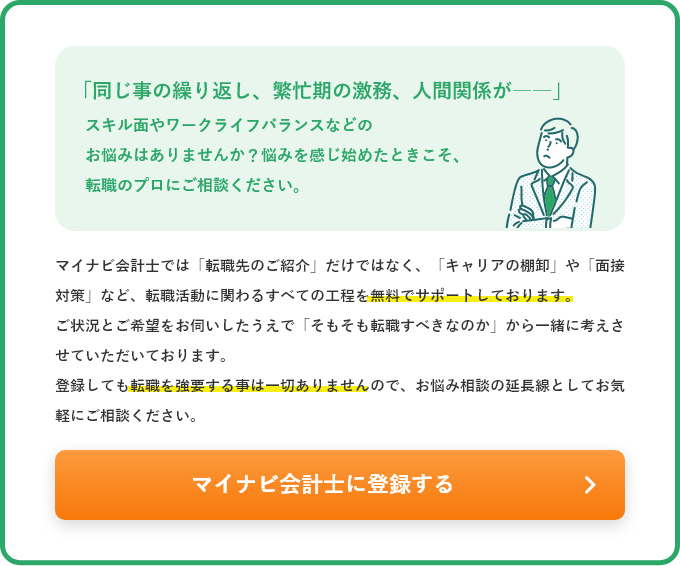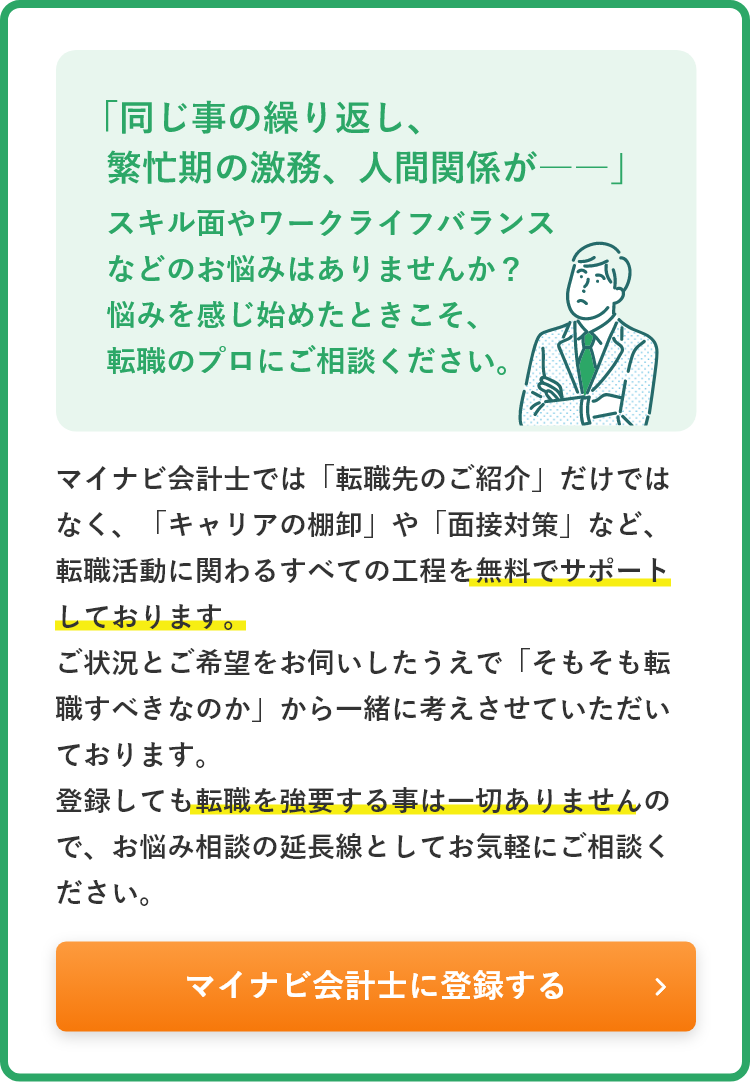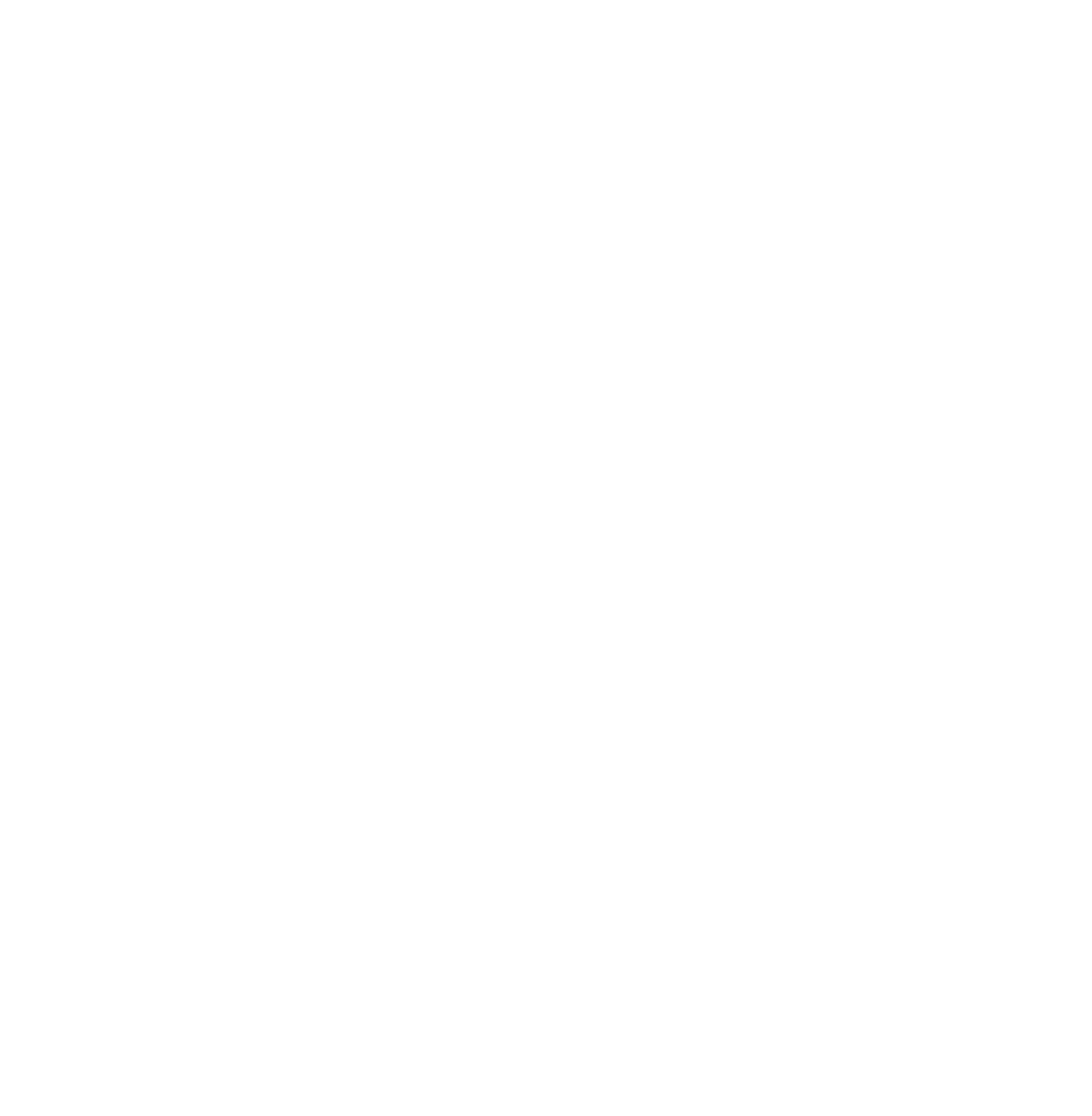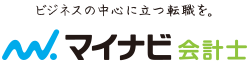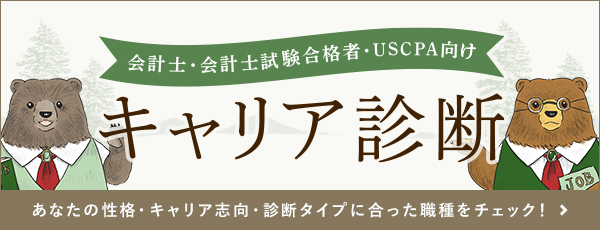公認会計士を維持するために必要なCPD制度とは

公認会計士に登録すると、研修などを受講して継続的に単位を取得しないといけません。その制度が継続的専門能力開発制度、いわゆるCPDと言われるものです。 従来CPEと言われていたものを、不適切な受講等を契機に新たなプロジェクトチームを立ち上げて2023年4月より新たな制度としてCPDができました。ここではCPD制度の概要、取得しないといけない単位数、取得方法などを紹介していきます。
関連まとめ記事
公認会計士試験合格後の流れ・やるべきこと【まとめ】
目次
CPDとは何か
まずは、公認会計士協会が実施しているCPDについて、制度の概要などについて解説します。
CPDの制度概要
公認会計士協会では、公認会計士の使命及び職責を全うし、監査業務等の質的向上を図ることを目的に、会員に対して研修の履修を義務付け、資質の維持・能力の向上を図り、自主的かつ能動的に能力開発を行うため、CPDの制度を実施しています。CPDは「Continuing Professional Development」の略で、継続的専門能力開発制度と呼ばれているものです。
公認会計士法第1条の2において、常に品位を保持し、その知識及び技能の習得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならないとされており、それが制度化されたのがCPD制度となっています。もともと1998年4月から任意参加でスタートした研修制度は、2004年4月から公認会計士法第28条において法定義務化されました。
CPDにおける単位取得の方法は
CPDでは3年間で120単位を取得する必要がありますが、その取得方法はさまざまです。一番多いのが、公認会計士協会が運営するCPD Onlineでのe-Learning受講です。そのほかにも、公認会計士協会が実施する集合研修会や自己学習、著書の執筆、セミナー講師を行うことで単位を取得することができます。
CPDに必要な単位数は?
次に、CPDにおいて必要な単位数についてご紹介します。
直近3年間で合計120単位が必要
公認会計士は、当該事業年度(4/1〜3/31)を含む直前3事業年度の合計で120単位を取得しなければなりません。また、もう一つの条件として、1年間で最低20単位以上の取得が必要となります。平均的には毎年40単位となっていますが、1年間で最低は20単位であるため、それを満たせば問題ありません。
合わせて、事業年度内で取得する必須単位数が設定されており、必須研修科目として「職業倫理」2単位及び「税務」2単位を取得する必要があります。さらに、法定監査に業務従事する人は「監査の品質及び不正リスク対応」6単位(うち、2単位以上は不正事例に該当する研修)の単位取得が義務付けられています。
組織内会計士の取得単位は?
CPD制度には、公認会計士としての業務を行わない又は行わないと見込まれる場合、必要な単位数を免除、あるいは軽減する措置があります。ただし、組織内会計士は公認会計士の名称使用の有無にかかわらず軽減することはできますが、免除をすることはできないとされています。
申請に関しては必要書類を提出するか、協会のウェブサイトより申請することが可能です。申請は毎年必要で、各事業年度の8月末まで提出期限になっています。
CPDを取得するには
具体的にCPDを取得する方法や、取得できなかった場合などに解説します。
CPDの取得方法
監査法人に所属していれば、監査法人内の研修やe-Learningを受講することで単位取得が簡単にできます。なお、費用に関しても無料です。
一方、独立したり一般事業会社で働いたりしている人は、そのような研修がありません。そのため、公認会計士協会の開催する集合研修会や、それを収録したDVDやe-Learningの受講などにより単位取得することが可能です。ただし、これらには費用が発生する場合もあります。また、そのほかには自己学習(CPDの指定記事や専門書の読書など)、著書の執筆、セミナーの講師を行うなどがあります。
具体的な内容は
具体的に、上述の研修などを受けると、どれだけの単位が取得できるのか確認しておきましょう。集合研修であれば1時間受講するごとに1単位が与えられ、1時間を超える研修なら30分以上は切り上げられて1時間としてカウントされます。一方、研修会の講師では2倍となり、1時間ごとに2単位与えられます。また、自己学習は読書2時間で1単位が与えられ、1冊あたりの上限として5単位が与えられます。
そのほか、著書の執筆であれば、4,000字以上という前提があり、4,000字ごとに1単位が与えられます。
CPDの単位を取得できなかった場合は?
CPD単位を取得できなければ、第1段階として履修に関して指示を受け、その指示を受けたことに関して公示されます。さらに、第2段階としては指示に違反した旨を公表されることになります。
その次の段階として、3年以上連続で0単位となる研修未受講者は登録抹消の対象となります。この制度は2023年4月に改正された公認会計士法に伴い、研修の義務不履行者に対して、登録抹消という仕組みが取り入れられました。
まとめ
公認会計士を維持するために必要となる、CPD制度について解説しました。公認会計士が使命及び職責を全うし、監査業務等の質的向上を図るためにCPD制度が義務化されました。3年間で合計120単位を取得する必要があり、監査法人で働いていれば監査法人内の研修等で稼ぐことは可能です。しかし、独立していたり事業会社に転職したりした場合は、自分で公認会計士協会などが主催する研修などを受けなくてはいけません。CPDの制度を理解し、公認会計士を維持するために各研修などを受講しましょう。
マイナビ会計士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
マイナビ会計士とは?
マイナビ会計士は会計士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。