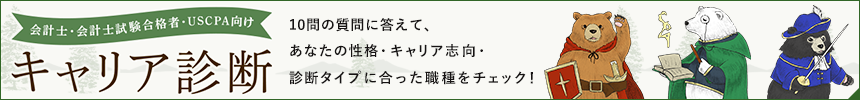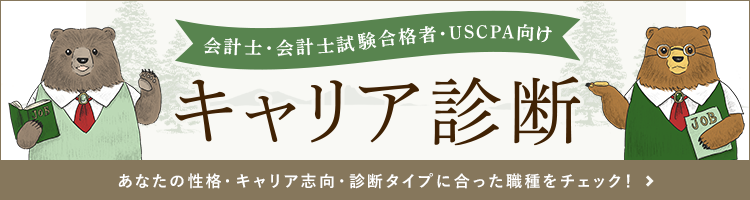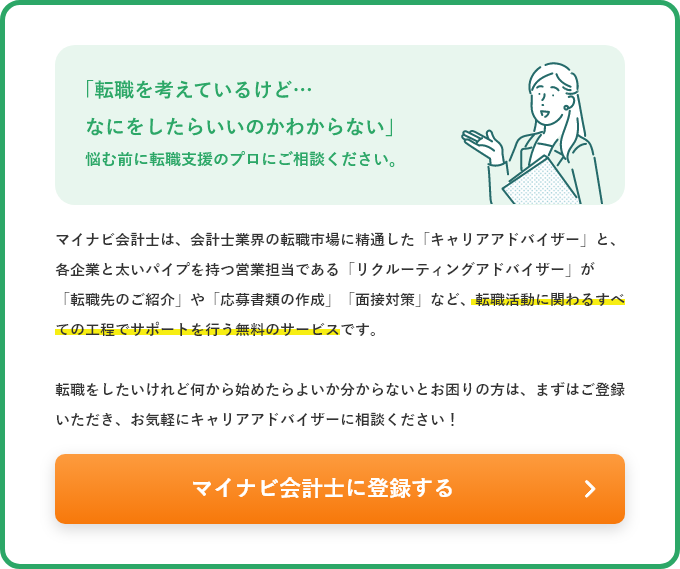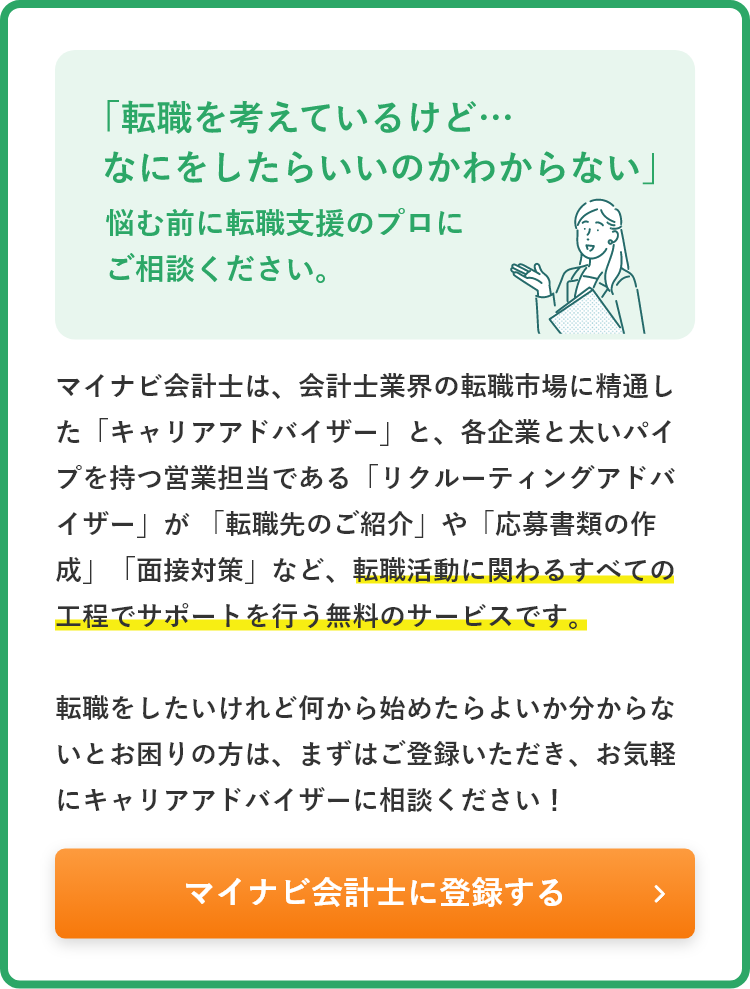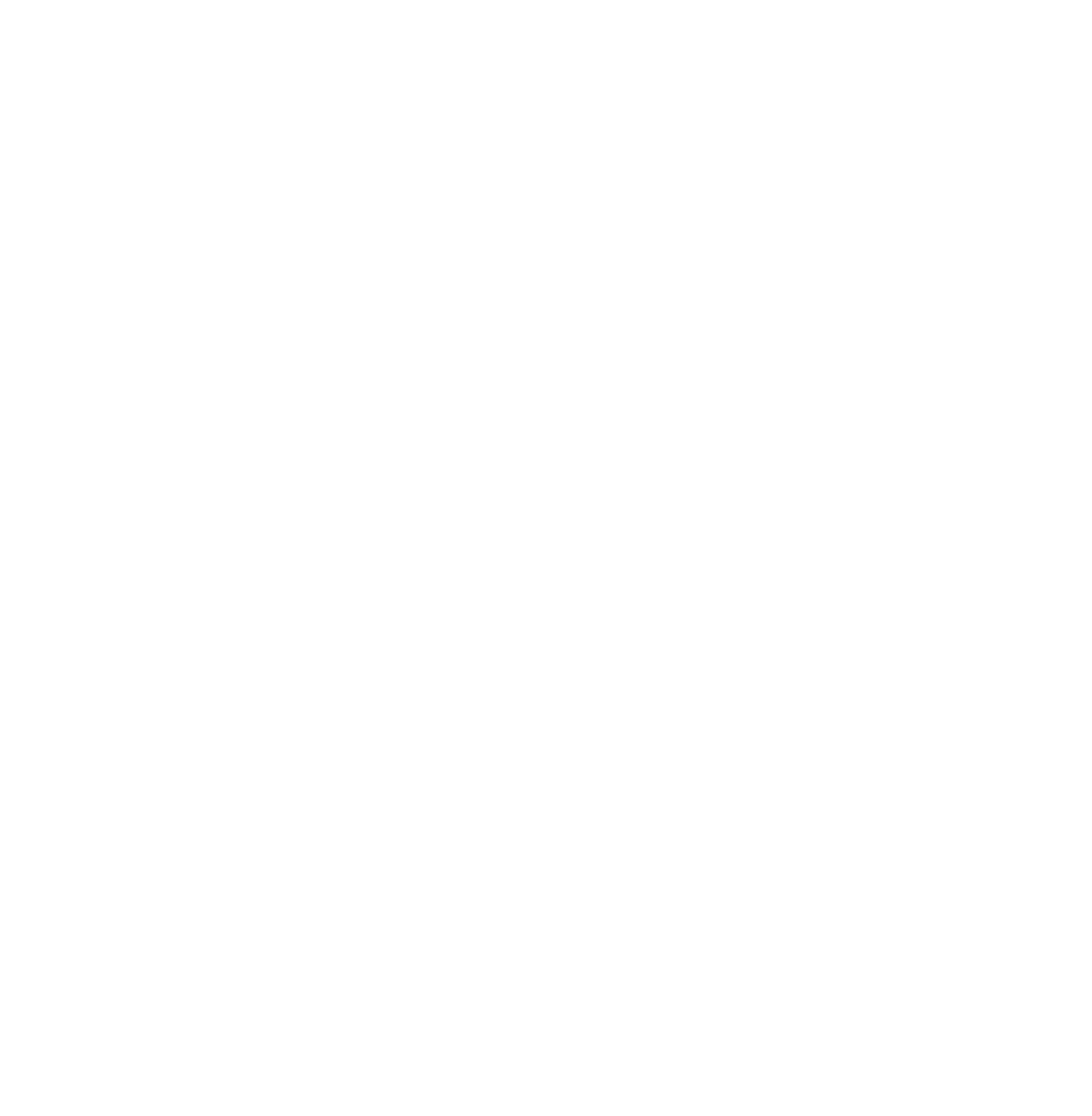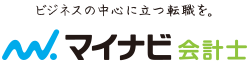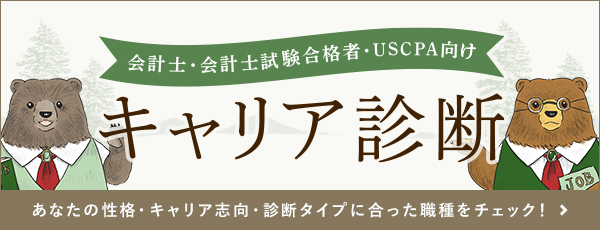監査とはなにか?基礎知識や目的について解説

監査とは、企業などの法人の活動とその結果に関する法令や社内規程の遵守、正確性、妥当性を判断し、報告することです。監査報告はIR情報として提供されます。
監査を行う側の立場や対象によって分類され、目的や関連性もさまざまです。本記事では、監査の基本的な仕組みから働く際に取得したい資格まで解説します。
転職をお考えの方、転職市場に精通したキャリアアドバイザーがアドバイスいたします。転職活動の成功には、キャリアアップを実現する転職先の選定が大切です。まずはマイナビ会計士にご相談ください。

マイナビ会計士編集部
マイナビ会計士は、公認会計士・試験合格者・USCPAの方の転職サポートを行なう転職エージェント。業界専門のキャリアアドバイザーが最適なキャリアプランをご提案いたします。Webサイト・SNSでは、公認会計士・公認会計士試験合格者・USCPAの転職に役立つ記情報を発信しています。
目次
監査とは
監査とは、企業や組織の財務情報が適正に作成されているかを、独立した第三者の立場から検証・保証する業務のことです。
主に、財務諸表が一般に公正妥当と認められる会計基準にしたがって作成されているか、経済的実態を適切に表示しているかを確認します。なお、監査の意義や根幹を成す制度の概要については、下記ページで詳しくお伝えしています。
関連記事
監査とは?意義や制度の概要について解説
監査基準を基本に行われる
監査は、監査人が従うべき実務指針を示すとともに、監査の品質を一定水準以上に保つ役割を果たす『監査基準』という明確なルールに基づいて実施されます。
基準には、監査人の独立性や職業的専門家としての正当な注意、監査計画の策定、監査証拠の入手方法など、監査業務の全般にわたる規範が定められています。だれが監査を行っても、一定の品質を確保できる仕組みが整えられているのです。
監査はだれがする?
監査は、客観性と公平性を確保するため、帳簿を作成した人以外の独立した立場の人が行います。主に、公認会計士や監査法人に所属する専門家が中心となって監査業務を担当するのです。
大規模な上場企業の場合、通常は監査法人のなかでチームが組まれることもあります。チームには、経験豊富なパートナーや公認会計士、公認会計士試験合格者などが含まれ、それぞれの専門性を活かして監査を進めていきます。なお、公認会計士が担う業務や流れは、下記ページもご覧ください。
監査の目的
監査の目的は、企業活動における健全性と適正性の確保です。内部統制を適切に機能させることでリスクを軽減し、経営目標の達成や不祥事の防止を図ったり、財務諸表の信頼性を確保するために以下の項目を重点的に確認したりします。
- 貸借対照表と損益計算書の内容
- 売掛金・買掛金の残高
- 現金・預金・借入金の残高
- 各種引当金の計上額と妥当性
また、不正や誤謬を早期に発見・是正して、投資家や債権者など、企業の利害関係者の利益を保護する役割も果たしています。特に近年では、企業の社会的責任(CSR)への関心が高まる中、コンプライアンス体制の整備や、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みについても、監査の観点となっています。
監査は行う立場で3つに分類される(三様監査)
監査は、だれが行うかによって3つの異なる立場から実施されます。これを「三様監査」と呼び、以下の3つに分類されます。主に、会計監査人監査の財務諸表監査の結果が出る四半期ごとのタイミングで、三様の監査人が協議する場を設けられることが多いようです。
- 内部監査
- 外部監査
- 監査役監査
三様監査は、異なる立場の監査人によってそれぞれの目的のために実施されます。以下で、それぞれの監査の種類を解説します。
内部監査
内部監査とは、組織に属する内部監査人が行う監査のことです。2006年のJ-SOX法の施行により、すべての上場企業で内部統制の評価や内部統制報告書の作成が義務化され、内部監査の実施が必要になりました。
主な業務は、組織におけるガバナンス・プロセス、リスク・マネジメントとコントロールの妥当性、有効性の評価を行い、改善提案まで行うことです。内部監査人は組織内において公正かつ独立の立場を保ち、合法性および合理性の観点から監査を実施します。
経営者の右腕として、組織の健全な発展を支える役割を担っており、組織内部の監査部門で内部監査人として働く公認会計士も増えています。より詳しくは、下記ページをご覧ください。
外部監査
外部監査とは、独立した組織から独立した第三者による監査のことです。法令で定められた基準にしたがって実施されるため、「法定監査」とも呼ばれます。
法定監査は、会社法により定められた法定監査は該当する企業にとっては義務であり、実施しない場合は上場廃止などのペナルティがあります。また、都道府県、政令指定都市などの地方自治体に対する法定監査もあり、こちらは会計以外の事務処理全般が対象です。
外部監査の業務は主に監査法人に所属する公認会計士が担当し、例えば決算書の数値が適切に計上されているか、会計基準に準拠しているかなどを厳密にチェックします。被監査会社との利害関係を持たないことにより、投資家や債権者など外部のステークホルダーの信頼を確保する役割を果たすのです。
外部監査についてより詳しくは、下記ページをご覧ください。
関連記事
監査の基本!外部監査の基礎知識
監査役監査
監査役監査とは、株主総会で選任された監査役が取締役に対して行う監査のことです。取締役の職務執行の適法性と妥当性を監査し、株主の利益を守ることが主な目的とします。監査役もしくは社外監査役として、公認会計士を監査役に選任するケースが多いです。
会社法では、株式公開企業、資本金5億円以上または負債額200億円以上の株式会社において、3名以上の監査役(うち最低1名は常勤)が必要と定められています。そのため、監査役と社外監査役で構成される、独立した権限を持つ監査役会を設置し、監査役監査を実施しなければなりません。
監査役監査の業務には、一般に適法性監査と呼ばれる、取締役の職務執行が法令・定款を遵守しているかを監査する業務監査と、定時株主総会に計算書類を提出する前に行われる会計監査があります。また、2002年の法改正により、連結計算書類も監査役監査の対象になりました。より詳しくは、下記ページをご覧ください。
関連記事
監査の基本!監査役監査の基礎知識
監査対象の違いでは4種類に大別できる
ここまでは、監査を行う立場で分類される『三様監査』をお伝えしました。そのほかにも、監査は対象によって以下の4種類へ大別するケースもあります。
- 会計監査
- 業務監査
- IT監査
- その他(システム・ISO監査)
会計監査
会計監査とは、企業が作成した財務諸表に対して、公認会計士または監査法人が行う監査をさします。財務諸表監査ともいわれ、中立、公正な監査意見を表明できる、利害関係のない第三者の立場である外部監査人が行います。また、監査役監査、内部監査でも会計監査が必要です。
業務では、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を精査し、会計記録の正確性、会計基準への準拠性、内部統制の有効性などを確認します。会計監査のより詳しい仕事内容や種類は、下記ページもご覧ください。
業務監査
業務監査とは、財務諸表とそれにかかわる会計業務を対象とする会計監査に対し、会計業務以外の業務を対象とする監査のことです。経営、購買、生産、販売などのすべての部門における業務が対象です。また、連結対象の子会社や海外事業所、場合によっては外部委託している業務も監査対象になります。
業務監査には、内部監査人によって行われる内部監査と、監査役が取締役の業務を対象に行う監査があります。実際の仕事では業務の指摘に限らず、業務改善の提案も行う特性上、経営効率の向上やコスト削減にも直結する役割を担います。より詳しい業務内容について詳しくは、下記ページをご覧ください。
関連記事
監査の基本!業務監査の基礎知識
IT監査
IT監査とは、会計監査の一環として財務諸表と会計システムを照らし合わせて、正確性・妥当性を確認する監査のことです。適正に財務諸表を記載し、会計システムを運用しているかの確認・評価を目的としています。
同じ目的で実施する「システム監査(後述)」と混同しやすいですが、IT監査は法令で義務付けられ、監査範囲・監査人は会社法に定められた監査です。主に、ソフトウェアに関する会計処理やIT関連の商品・製品に関する知識など、特定の領域の知識を活かすことができます。より詳しくは、ぜひ下記ページもご覧ください。
その他(システム・ISO監査)
その他として、監査とつく代表的な種類がシステム監査とISO監査です。どちらも法令に定められたものではないことから、公認会計士でなくても実施できる監査の種類となります。
システム監査は、情報処理システム全般に関する監査で、システムの信頼性や経営への貢献度を評価します。現代の企業活動において情報システムは不可欠であり、適切な活用や情報漏えい防止のために監査を実施するものです。
ISO監査は、国際標準化機構(ISO)が定めた規格に基づき、組織の品質管理システムなどが規格要求事項を満たしているかを確認する監査です。認定を受けた審査登録機関(認証機関)が実施し、製品やサービスの品質向上、業務の標準化、文書化を目的としています。
将来性は?なぜ監査が必要なのか
現代では監査対象が海外にまでおよぶことから世界中で活動する企業の数だけ監査ニーズがありますし、企業の不正会計や粉飾決算が社会問題として取り上げられることも多く、将来性も極めて高いといえます。
また、企業における経済活動が行われる限り、財務諸表の信頼性を担保して投資家や取引先などのステークホルダーを保護する「監査」の需要は続きます。信頼性が確保されることで、投資家は安心して投資の判断を行うことができ、取引先は安定した取引関係を築くことができるからです。
昨今では、従来の会計知識に加えてIT技術やデータ分析のスキルも求められるようになってきました。このように、監査の領域は常に進化し続けており、需要は今後も拡大していくと考えられます。
監査が義務付けられている企業の例
監査法人や公認会計士が監査を行う際は、法律で明確に定められた以下の企業を対象とします。
- 大会社
- 監査等委員会設置会社
- 会計監査人を設置した会社(任意)
将来的に監査でどのような企業(クライアント)を扱うのかを知る参考にしてください。
大会社
大会社とは、会社法で定められた規模要件を満たす株式会社のことです。資本金が5億円以上、または負債総額が200億円以上の企業を対象としており、定時株主総会で承認された貸借対照表の数値に基づいて判断されます。
例えば、3月決算の企業が2023年3月期の貸借対照表で初めて負債総額200億円を超えた場合、2023年6月の定時株主総会での承認後から「大会社」となり、2024年3月期から会計監査人による監査が必要です。
規模が大きいことから、業務では監査役(社内の人材)と会計監査人(第三者)が別々に監査を実施し、情報共有しつつ進めるケースが多い傾向にあります。
監査等委員会設置会社
監査等委員会設置会社とは、2015年の会社法改正で導入された新しい機関設計の形態のことです。取締役3名以上(その過半数は社外取締役)で構成される監査等委員会が、取締役の業務執行を監査・監督します。
監査等委員会設置会社を採用した場合、会社法により会計監査人による監査が義務付けられています。主に、監査等委員と会計監査人が連携して監査の業務を進めるのが一般的です。
会計監査人を設置した会社(任意)
法律上の要件に該当しない企業でも、定款に定めることで任意に会計監査人を設置できます。企業の規模に関係なく選択可能な制度で、行うかどうかは任意となります。
ただし、一度会計監査人を設置すると、監査は法定監査として扱われ、正当な理由なく中止できません。とはいえ、監査役(または監査等委員)と会計監査人が独立して監査を実施し、財務情報の信頼性が高まることで、企業価値の向上にもつながります。
このことから、任意設置を選ぶ企業の多くは、将来の株式上場を見据えていたり、取引先からの信用力向上を目的としていたりするケースが多いでしょう。
監査を行うのは『監査法人』が基本
監査を担う仕事に就く場合には、監査業務の中心を担う監査法人がメインとなります。監査法人とは、公認会計士が共同で設立する特別法人で、主に企業の会計監査を行う組織のことです。日本には200以上の監査法人が存在しますが、その中でも上場企業の監査業務収入の約8割を占めているのが大手監査法人です。
監査の対象は財務諸表が中心ですが、内部統制の評価やシステム監査なども行います。また近年では、コンサルティングやアドバイザリー業務など、監査以外のサービスを手がける監査法人も増えてきました。より、監査法人について詳しくは、下記ページも参考にしてください。
有名なのはBIG4監査法人
監査法人の中でも特に有名なのが「BIG4」と呼ばれる、有限責任監査法人トーマツ、EY新日本有限責任監査法人、PwCあらた有限責任監査法人、有限責任あずさ監査法人の4大監査法人です。日本を代表する大企業の多くをクライアントに持ち、特に東証一部上場企業の監査を数多く手がけています。
また、充実した研修制度や福利厚生を備え、年収も他の監査法人と比べて高水準です。一方で業務は責任も重く、特に3月決算期の繁忙期は激務となることも少なくありません。とはいえ、大手企業の監査経験を積めることや、将来のキャリアの選択肢が広がることから、多くの公認会計士が目指す就職先となっています。
BIG4監査法人について気になった方は、ぜひ下記ページもご覧ください。
監査を担う監査法人の年収
監査法人での年収は、役職や経験年数によって変動します。特に大手監査法人(BIG4)では、着実なキャリアアップとともに年収も上昇していく傾向にあります。
| 役職 | 経験年数 | 年収目安 |
|---|---|---|
| スタッフ | 0〜3年 | 300〜500万円 |
| シニア | 4〜7年 | 600〜700万円 |
| マネージャー | 8〜14年 | 800〜1,000万円 |
| パートナー | 15年以上 | 1,500〜3,000万円 |
シニアからマネージャーの時期は、多くの公認会計士が転職を考えるタイミングとなっています。理由は、マネージャーへの昇進で管理職となり残業代が支給されなくなる一方、責任は大きく増すためです。
監査法人での働き方は、若手のうちから一般企業と比べて高い年収が期待できる一方で、キャリアステージごとに重要な選択を迫られる職種といえます。詳しい年収や傾向については、ぜひ下記ページをご覧ください。
関連記事
監査法人勤務の会計士の年収
監査を行う企業で働く際に大変に感じやすいケース
監査として働くことで高い年収を狙える一方で、実際の業務では以下の2つが大変に感じやすいケースとしてよく挙げられます。
- 内部統制がうまく機能していない
- デジタル化が進んでいない
ただし、上記の課題に直面することは、むしろチャンスと捉えることができます。なぜなら、改善提案を通じてクライアントの経営品質向上に貢献できるからです。
監査人として働く醍醐味は、まさにこうした課題を1つひとつ解決していく過程にあります。以下で、もう少し詳しく見ていきましょう。
内部統制がうまく機能していない
内部統制の機能不全は、監査を行う上でもっとも頭を悩ませる課題の1つです。理事長による法人財産の私物化や、関係者への不適切な利益供与といった不正から、単純な計算書類の作成ミスまで、さまざまなリスクが潜んでいます。
このような状況下では、監査の実施自体が困難になり、最悪の場合、監査意見を表明できないケースも十分に想定できます。しかし、こうした状況こそ内部統制の改善提案を通じて、クライアントの経営基盤強化に貢献するという「監査人としての真価」が問われるやりがいのある場面でもあります。
デジタル化が進んでいない
監査対象となる企業では、まだ紙ベースでの帳票管理が主流となっているケースもあります。データが電子化されていないため、サンプリングや分析に多大な時間と労力を要します。結果として、本来注力すべき監査手続きに十分な時間を割けないことも少なくありません。
一方で、DXの提案を通じてクライアントの業務効率化に貢献できるという側面もあります。また、紙ベースの資料を丹念に確認する過程で、システムでは見落としがちな異常や不正の兆候を発見できることもあるでしょう。このように、一見するとデメリットに思える状況も、プロとしての成長機会として捉えることは十分にできます。
監査業務の不安や激務については、ぜひ下記ページもご覧ください。
監査で働く際に取得したいおすすめの資格
では、監査の業務を担うには、どのような資格が必要となるのでしょうか。現場で活躍するためにぜひ持っておきたい資格の代表例として、以下の4つを紹介します。
- 日商簿記
- 公認会計士
- 内部監査人(CIA)
- 米国公認会計士(USCPA)
日商簿記
日商簿記は、2級以上の取得を目指すことで、企業会計の基本的な仕組みを体系的に理解できます。簿記の知識は、財務諸表の作成プロセスを理解する上で不可欠であり、監査時の異常値の発見にも役立つことから監査業務の入門資格として最適です。
3級から始めて段階的にステップアップできる点も魅力で、独学での合格も十分可能です。監査の現場では、仕訳から財務諸表作成までの一連の流れを理解していることが求められますが、日商簿記の学習を通じてこの知識を確実に身につけることができます。
公認会計士
公認会計士は法定監査を実施できる唯一の資格であり、監査法人でのキャリアを築く上で必須となります。試験科目には、会計学、監査論、企業法、租税法などが含まれ、合格後は実務補習と実務経験を経て正式な公認会計士として登録できます。
試験の合格率は例年10%前後で難易度が高いですが、監査法人での監査業務はもちろん、企業のCFOや経営コンサルタントとしても活躍できるほど合格後のキャリアの選択肢は広いです。また、年収も他の資格と比較して高水準であり、キャリアの安定性も確保できます。
内部監査人(CIA)
内部監査人(CIA: Certified Internal Auditor)は、内部監査の国際資格として世界的に認知されている資格です。企業の内部監査部門で働く際に特に有用で、リスク管理やガバナンスに関する専門的な知識を証明できます。
資格取得には、学士号と実務経験が必要ですが、内部統制やリスク評価の体系的な知識を習得できる点が魅力です。海外企業を対象とした内部監査担当者として活躍したい場合、CIAの取得はアドバンテージとなります。特に、J-SOX対応や内部統制報告制度への対応力が評価してもらえるでしょう。
米国公認会計士(USCPA)
米国公認会計士(USCPA)は、内部監査人と同様に海外企業も対象とする監査人を目指す方に向いた資格です。合格後は、米国企業の監査や、日本企業の米国会計基準による財務諸表監査などに携わることができます。
また、日本の公認会計士資格とあせて取得できれば、より幅広い監査業務に対応できます。グローバル化が進む現代では、USCPAの需要は年々高まっており、キャリアの可能性を広げる資格として検討できるでしょう。
監査に関するよくある質問(FAQ)
最後に、監査に関する疑問や不安を解消するため、以下ではよくある質問へ回答します。
監査役とは?
監査役とは、取締役の職務執行をチェックし、監査報告書の作成・報告を責務とする会社法上の機関のことです。株主の利益を守るため、経営者の不正等を防ぐ役割を担っています。例えば、大会社では監査役の設置が義務付けられており、独立した立場から経営の健全性を確保します。
関連記事
監査役とは?公認会計士が携わる業務を解説
監査が行われる時期の目安は?
3月決算の会社の場合、6月後半から7月に新年度の監査契約を結び、監査がスタートします。期中監査は秋頃から開始され、期末監査は決算期後の4月から5月にかけて実施されるのが一般的です。監査報告書の提出は株主総会前までに行われます。
監査が入るとは?
税務署や監査法人などの外部機関が、企業の帳簿や証憑書類をチェックするために来訪することを指します。特に税務調査の文脈で使用されることが多く、コンプライアンスの観点から重要な手続きとなっています。
内部監査では何を見る?
内部監査では、企業の経営目標達成に向けて、リスクマネジメントやガバナンスプロセスの観点から業務遂行状況や組織体制を評価します。主に、業務の効率性、法令遵守状況、内部統制の有効性などを確認し、改善提案を行います。
任意監査と法定監査の違いは?
任意監査は法的な強制力がなく、企業が自主的に依頼する監査です。一方、法定監査は法律で義務付けられた監査で、主に大会社や上場企業が対象となります。規模や目的に応じて適切な監査形態を選ぶことが大切です。
往査とは何ですか?
往査とは、監査人が被監査会社の事業所や工場などへ直接赴いて行う監査のことです。現場での実地確認により、より正確な実態把握が可能となり、監査の実効性を高めることができます。
監査と往査の違いは?
監査は包括的な概念で、事務所での書類確認なども含みます。一方、往査はクライアント先に出向いて行う監査に特化した用語です。両者は補完関係にあり、効果的な監査のために使い分けられます。
実査とは何ですか?
実査は、資産の実在性を確認するため、公認会計士が現物を直接確認する監査手続きです。例えば、現金や有価証券、棚卸資産といった実物を確認するなどにより、帳簿上の記録と実際の資産が一致しているかを検証します。
まとめ
公認会計士は、独占業務である監査を通して企業などの適法性、正当性、合理性を担保する役割を担います。公認会計士の有資格者は、財務における外部監査、監査役監査、内部監査、どのポジションでも監査人になれます。
監査には情報開示による透明性の確保のほかに、組織の内部統制の強化、組織の問題点を洗い出し、適切に対処するといった目的があります。それぞれの監査に目的と役割があり、三様監査には連携も必要です。どの監査に携わるかで仕事の進め方も異なります。監査の意義と基礎知識を理解しておきましょう。
マイナビ会計士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
マイナビ会計士とは?
マイナビ会計士は会計士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。