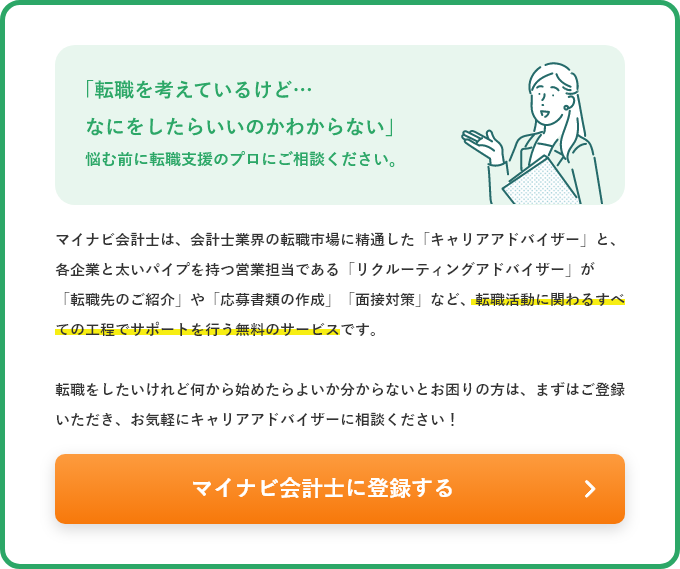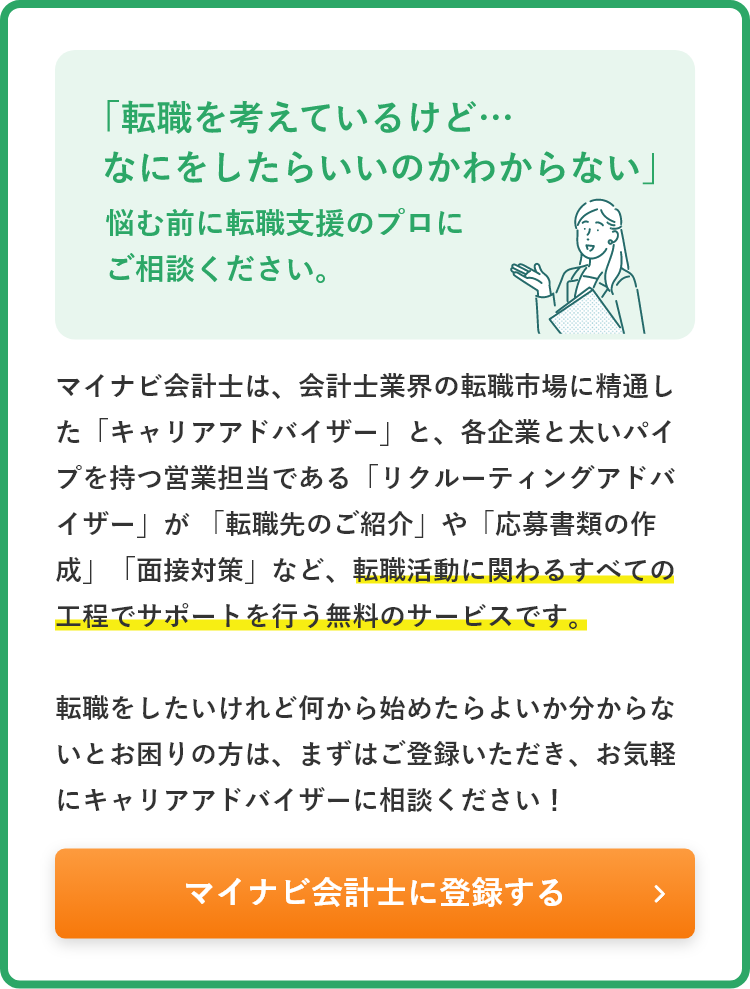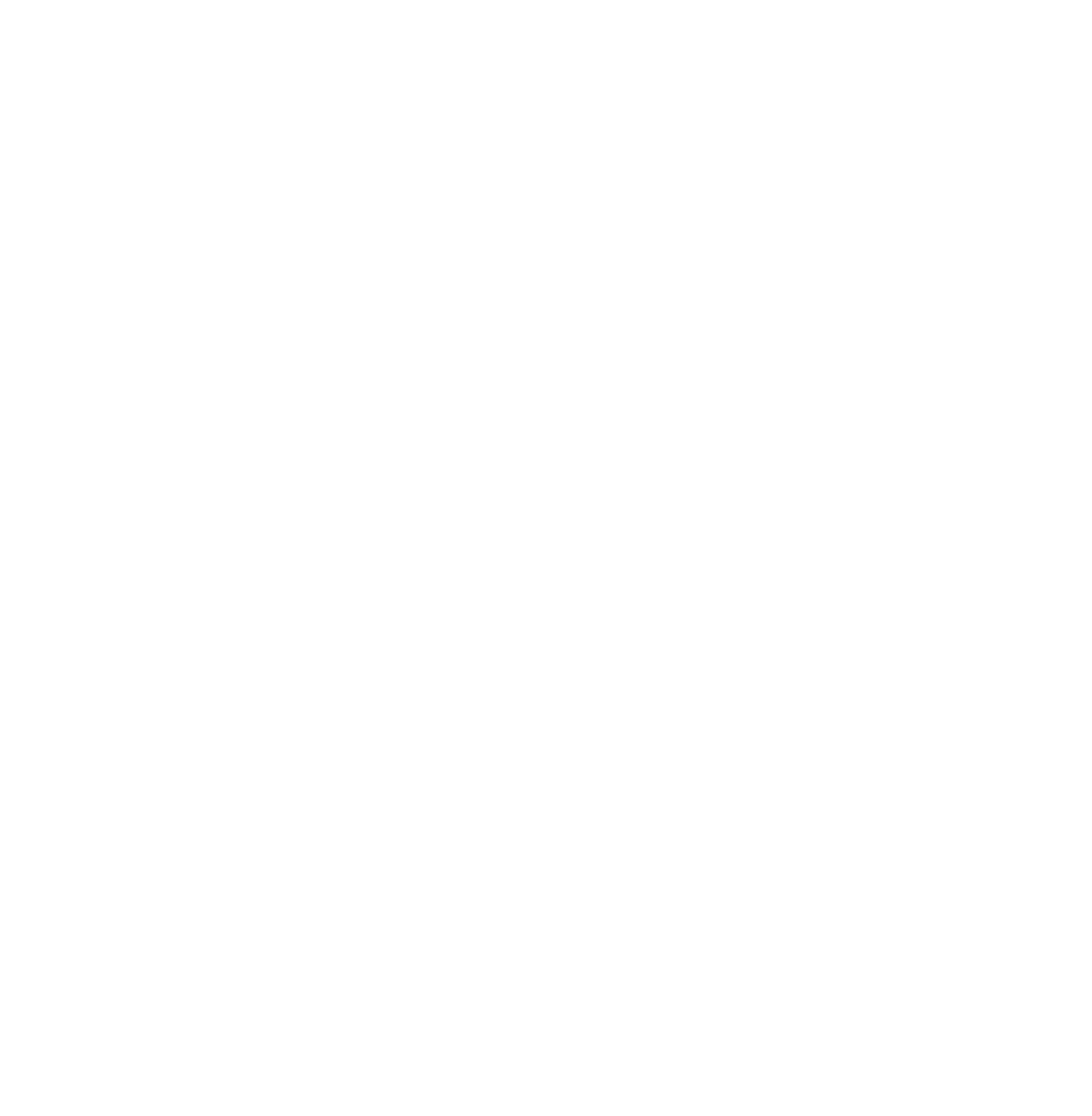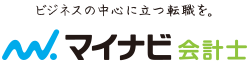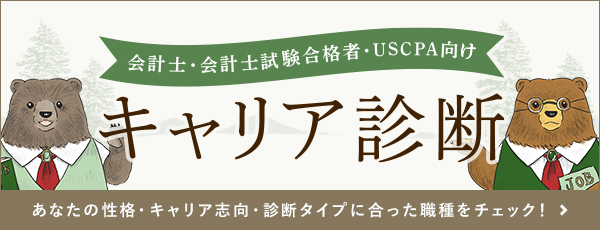監査とは?意義や制度の概要について解説

監査業務は公認会計士の独占業務ですが、外から見ただけでは、なかなかその趣旨が分からないこともあるでしょう。
そこで、監査の意義や制度の概要、監査意見とは何かについて、ここで解説します。

マイナビ会計士編集部
マイナビ会計士は、公認会計士・試験合格者・USCPAの方の転職サポートを行なう転職エージェント。業界専門のキャリアアドバイザーが最適なキャリアプランをご提案いたします。Webサイト・SNSでは、公認会計士・公認会計士試験合格者・USCPAの転職に役立つ記情報を発信しています。
監査の必要性
会計監査の意義
会計監査の意義は会計情報の信頼性を確保し、当該会計情報を使用する外部の意思決定者(投資家やプロフェッショナルファームの人間など)にとって有用な投資意思決定に資する財務情報を提供することにあります。
これをもって資本市場の発展に寄与することができ、国民経済の健全な発展に資するものとされているのです。
会計監査を行うには、今日の複雑かつ不確実な事業環境の中で作成された財務諸表を、外部の客観的な立場から検証する必要があり、相当程度の会計監査に関する専門知識が求められます。
そのため、難関と呼ばれる国家試験である公認会計士試験に合格した人による監査が必須です。
財務諸表およびそれらにより構成される財務報告が、一般に公正妥当と認められる会計基準に則り作成されていること。
また、経済的実態が適性に表示されていることを外部から担保することが、会計監査の意義になるでしょう。
日本での制度化の歴史
日本における会計監査制度の歴史は、米国や欧州のそれに比べると新しいものです。
まず、明治時代に入って間もない1890年に商法制定がなされ、飛んで戦後1948年に公認会計士法が成立しました。
翌1949年には「企業会計原則」が発布され、JICPA(日本公認会計士協会)が任意団体として創立されています。
さらに、1951年には証券取引法(現在の金融商品取引法)に基づく公認会計士による上場企業の監査が開始され、これが上場企業に関する会計監査元年になっているのです。
1963年には「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則」が公布され、1967年には公認会計士法で認可された監査法人第一号設立となりました。
1974年には商法に基づく公認会計士による監査開始、1975年「連結財務諸表原則」公布されています。
そして、1998年以降に会計ビッグバンという一大現象があり、連結財務諸表原則の見直し(中間連結財務諸表を含む)、連結キャッシュフロー計算書の作成基準、税効果会計に係る会計基準の導入、研究開発費等に係る会計基準の導入、退職給付に係る会計基準の導入、金融商品に係る会計基準の導入等が行われました。
監査の種類
金商法監査
金融商品取引法第193条の2に基づき、公認会計士若しくは監査法人によって行われる監査のことです。
東京証券取引所など国内の証券取引所に株式を上場している会社は、金融商品取引法に基づく公認会計士監査を受けることが義務付けられています。
会社法監査
会社法の規定により作成される「計算書類」が、適法に作成されているかどうかについて行われる監査のことを指します。
大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)は、必ず会社法監査を受けなければなりません。
なぜなら、このような規模感の大きい企業は少なくとも利害関係者に与える影響が大きいと考えられ、計算書類の監査を会社法により義務づけているためです。
計算書類は貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表の4つからなり、全ての株式会社が作成する義務があります。
なお、上場会社は連結計算書類(連結貸借対照表・連結損益計算書等)も作成する必要がある点にも留意してください。
その他監査(自己査定監査等)
自己査定監査は銀行等の金融機関において行われるもので、貸出金の債権区分を検討する監査を指します。
債権区分によっては貸倒引当金の積み増しが必要になる可能性もあり、銀行にとっては重要な意義があります。
監査で行う内容
一般的な監査手続きの種類
一般的な監査手続きには、メーカー等の事業会社で行われる棚卸資産の立会、資産の実査、現金の残高確認、分析的手続き、会計上の見積に関する監査等が挙げられます。
棚卸資産の立会は、メーカーの工場等で在庫の実物が存在するかどうか日程を決めて実施するものです。
実務では、工場の経理担当者と現場担当者を巻き込んで行われることがあるでしょう。
地方出張が多くなる監査手続きの一つでもあり、新人会計士が関与する手続きです。
資産の実査は資産の実在性を確かめるために、監査人が帳簿に計上されている資産の現物を実際に確かめる手続きとなります。
現金や有価証券を対象として行われ、期末時点における資産の評価の妥当性をもカバーできる監査手続きです。
現金の残高確認では、決算日など特定の日の残高の実在性を証明する有力な監査証拠となります。
そのため、金融機関との取引や売掛金などの債権、倉庫業者に保管されている棚卸資産等々、さまざまな財務諸表項目を対象に実施される監査手続きです。
分析的手続きは特定の勘定科目に関して比率や趨勢等を検証することにより、異常な数値や傾向の有無を検証することが可能です。
例えば、売上高に対する販管費の比率等を過去数年にさかのぼり検証して、異常な動きが無いかどうかを検証します。
会計上の見積に関する監査は、減損会計、退職給付会計、税効果会計等の比較的難易度が高く、重要性が高い項目に対して実施されます。
そのため、スタッフではなくシニア以上の経験のある会計士が担当することが多いでしょう。
会計上の見積という名前がついているのは、減損会計では資産の将来キャッシュフローの見積が必要になるし、退職給付会計においても引当金の金額の見積が必要になるためです。
見積に関しては会計監査人のみならず、他の外部専門家(割引率や将来キャッシュフローの価値に関してバリュエーションの専門家の採用等)が必要になる場合もあります。
監査報告について
監査報告はここでは会計監査人による監査報告を指し、期末監査の結果を監査報告書にまとめたものです。
監査報告書には、長文式監査報告書と短文式監査報告書があります。
一般投資家や株主に対しては、監査の概要や結論のみを記載した短文式監査報告書が用いられます。
長文式監査報告書は、監査の過程で発見された会社の経理上の問題点や改善すべき点などを述べたもの。
監査対象の企業の経営者に提出され、投資家等の外部には公表されません。
金融商品取引法、および会社法における公認会計士監査では、財務諸表の適正性に関する意見が表明されることになります。
なお、監査意見の類型は下記に記載する通りです。
監査意見
監査報告書においては監査意見が表明されるが、監査意見のパターンは下記4つである。
無限定適正意
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準にしたがって、会社の財務状況を「すべての重要な点において適正に表示している」旨を監査報告書に記載する意見です。
なお、上場会社の監査報告書における監査意見は、ほとんどが無限定適性意見となります。
限定付適正意見
一部に不適切な事項はあるものの、それが財務諸表等全体に対してそれほど重要性がないと考えられる場合、当該不適切事項を記載して会社の財務状況は「その事項を除き、すべての重要な点において適正に表示している」と監査報告書に記載する意見です。
不適正意見
不適切な事項が発見され、それが財務諸表等全体に重要な影響を与える場合には、不適正である理由を記載して会社の財務状況を「適正に表示していない」と監査報告書に記載することになります。
意見不表
重要な監査手続きが実施できず、結果として十分な監査証拠が入手できない場合、その影響が財務諸表等に対する意見表明ができないほどに重要と判断した際には、会社の財務状況を「適正に表示しているかどうかについての意見を表明しない」旨及びその理由を監査報告書に記載します。
なお、実務上はこのような事態はほとんどありません。
まとめ
会計監査は、資本市場の健全な発展に寄与するためのインフラストラクチャーです。
その詳細について、ご説明しました。
監査の種類や手続き、監査意見に関しても、専門性の高いことがご理解いただけたのではないでしょうか。
この内容を参考に、監査に対する知識を深めてください。
マイナビ会計士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
マイナビ会計士とは?
マイナビ会計士は会計士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。