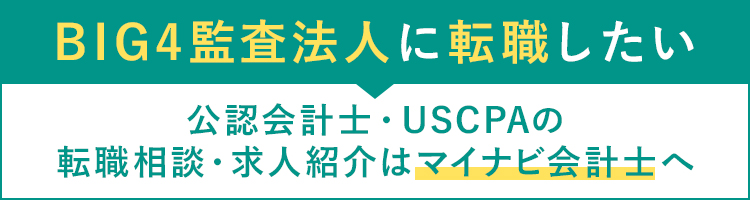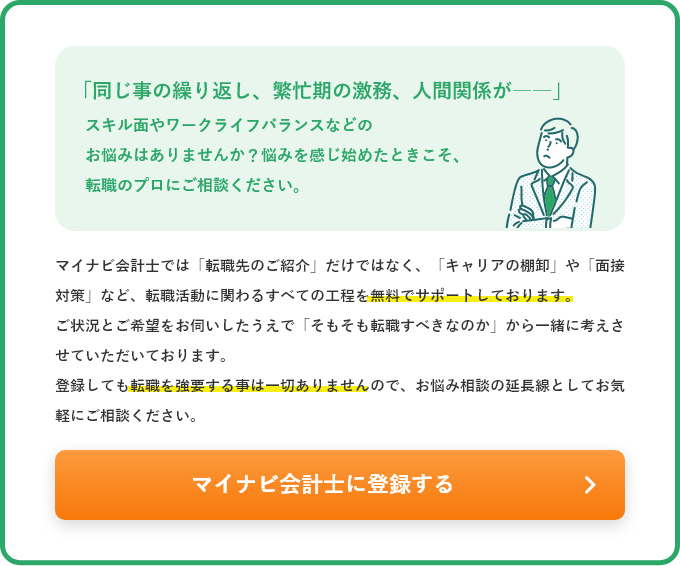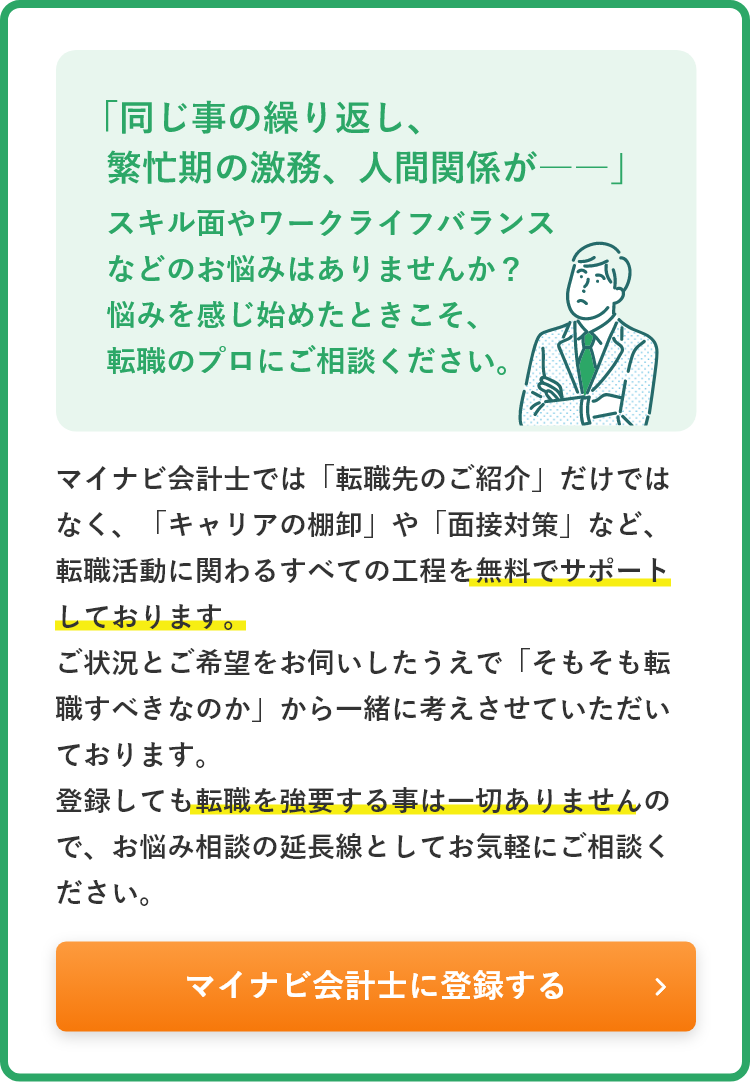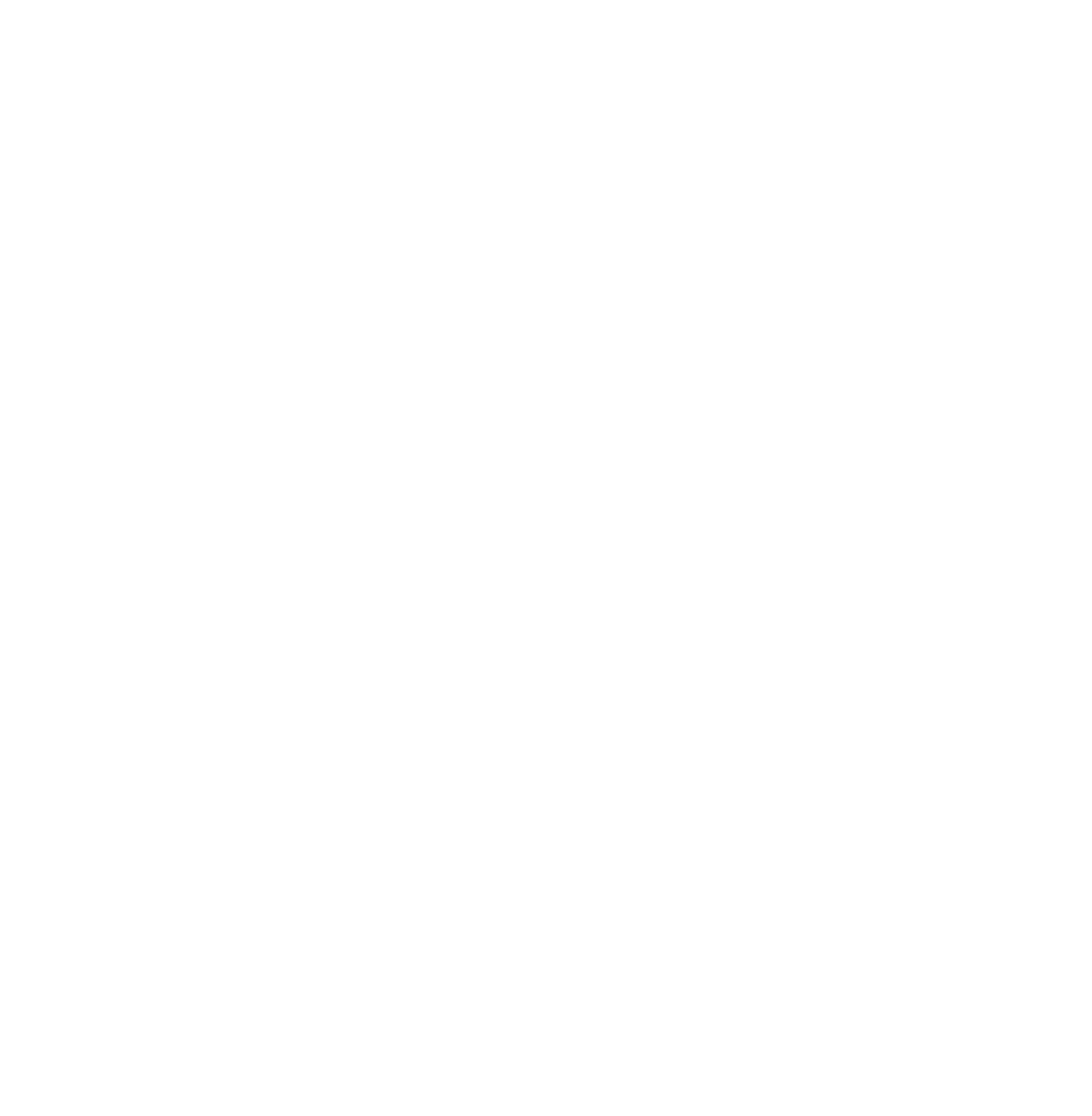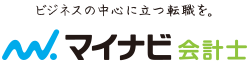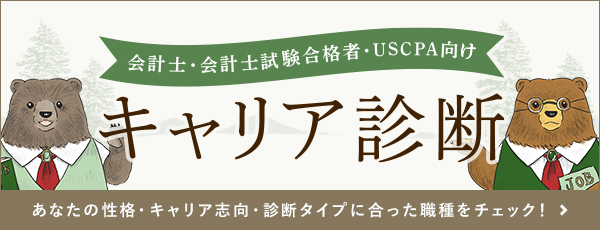監査法人はどんなところ?転職難易度や向いている人をご紹介
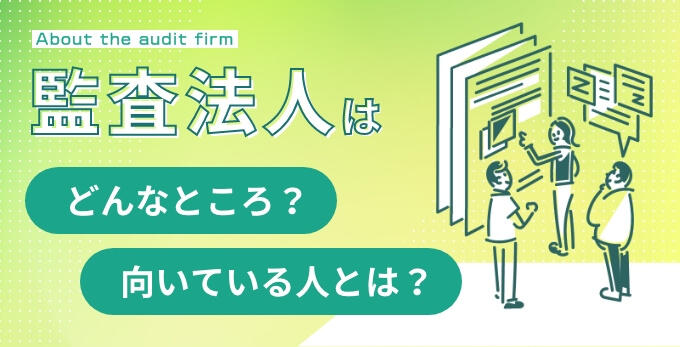
公認会計士試験に合格した後、その約8割の方が大手監査法人に就職すると言われています。しかし、医者や弁護士に比べて公認会計士を題材にしたテレビドラマ等はほとんどなく、監査法人についてはなかなかイメージしにくいかもしれません。そこで、監査法人がどのような組織なのか、どんな人が監査法人での勤務に向いているかを詳しく説明します。
このようなお悩みはありませんか?
- 会計士を目指して勉強をしているが、監査法人の仕事について具体的なイメージを持てていない
- 監査法人から監査法人へ転職するにあたって、どのようなことに気をつければ良いのか知りたい
- 監査法人は激務と聞くが具体的にどの程度忙しいのか、会社によって違うのかなど分からない
上記のような転職に関するお悩みや不安をお持ちの方は、
マイナビ会計士のキャリアアドバイザーにご相談ください。

マイナビ会計士編集部
マイナビ会計士は、公認会計士・試験合格者・USCPAの方の転職サポートを行なう転職エージェント。業界専門のキャリアアドバイザーが最適なキャリアプランをご提案いたします。Webサイト・SNSでは、公認会計士・公認会計士試験合格者・USCPAの転職に役立つ記情報を発信しています。
目次
監査法人ってどんな組織? 何をする?
監査法人とは"会計監査"を行う法人で、監査証明業務の他に非監査業務やコンサルティング業務なども担います。日本には中小規模を含めると200以上の監査法人がありますが、代表的な「4大監査法人(Big4)」で、上場企業における監査業務収入の8割程度のシェアを有しているとされています。
監査業務とは
監査業務とは、各企業の透明性と健全性を保つために、重要な役割を果たすものです。業務には様々な種類があり、具体的には下記が挙げられます。
- 会計監査:企業の財務情報が適切に記録・報告されているかを検証する
- 内部統制監査:企業の内部統制が適切に機能しているかを評価する
- 税務監査:企業の税金の申告等が適切かどうかを確認する
- 情報システム監査:会計に関連するITシステムの適切な運用とセキュリティを検証する
- 環境監査:企業が環境規制や基準を遵守しているかを検討する
- コンプライアンス監査:企業が法律や規則を遵守しているかを確認する
紹介したのは一部で、実際には監査業務だけでなく、コンサルティング業務も担うことがあります。その範囲は、経営の改善からITシステムの適正な運用、人事の改善、マーケティングの強化、財務の効率化など、広範囲におよびます。
こうした監査業務によって、企業が健全に運営されていることを保証し、信頼性の高い情報を提供できます。つまり、投資家やステークホルダーに対する信頼を強化する役割を果たすことが、監査法人で求められる監査業務だということです。
4大監査法人(BIG4)とは
世界的に活動している大きな会計事務所(Big4)と提携している日本監査法人を、4大監査法人(BIG4)と呼びます。4大監査法人は東証1部の上場企業と同程度の規模かつ、大きなクライアントが多く、研修制度や福利厚生が充実している点が共通のメリットです。それぞれ、法人ごとの特徴を以下にまとめました。
| 監査法人 | Big4の提携先 | 社風やイメージ |
|---|---|---|
| 有限責任あずさ監査法人 | KPMG | 女性に人気でおしゃれな印象 |
| EY新日本有限責任監査法人 | アーンスト・アンド・ヤング(EY) | クライアントは老舗の日本企業が多い。安定志向で優等生タイプの方向き。 |
| 有限責任監査法人トーマツ | デロイトトウシュトーマツ | コンサルティングなどの被監査業務にも強い。ノリがよく体育会系。 |
| PwC Japan監査法人 | プライスウォーターハウスクーパース(PwC) | 国際色が強い |
準大手監査法人とは
監査法人と言えば、多くの人が思い浮かべるのは「大手監査法人」ですが、業界内で準大手監査法人という言葉もよく耳にします。
準大手監査法人としてよく名を挙げられるのは、「仰星監査法人」「三優監査法人」「太陽有限責任監査法人」「東陽監査法人」の4つの法人です。業界全体の中で見れば、大手に次ぐ規模を誇る存在として位置づけられています。
また、一般的な大手監査法人の社員数は約180人から600人程度ですが、準大手の社員数は約30人から約100人弱と、大手よりは少なめです。また、常勤職員数でも、大手が約3,500人から約8,000人に対し、準大手は約200人から約800人弱となっています。
そのため、準大手監査法人は大手と比べて社員数が少ない分、一人ひとりの責任が重く、業務の幅も広いと言えます。しかし、それは逆に自身のスキルを磨き上げる絶好の機会であり、自身の成長を促す貴重な経験になるとも捉えられるでしょう。
参考:令和5年版モニタリングレポート(公認会計士・監査審査会)
監査法人の組織
監査法人での職階は以下の通りです。
- スタッフ(1~4年目)
- シニアスタッフ(5~8年目)
- マネージャー(9~11年目)
- シニアマネージャー(12~14年目)
- パートナー(15年目以降)
監査法人での最終キャリアはパートナーを目指すことになりますが、マネージャー以上は管理職となり、全員が昇格できるわけではありません。そのため、スタッフやシニアスタッフのうちに大手監査法人を退職して、中小監査法人やコンサル会社、税理士法人や事業会社などに転職する方も多くなってきています。
監査法人で働いている人は
公認会計士試験を合格すれば、監査法人に就職するのがよくある流れでした。そのため、監査法人で働いているのは公認会計士試験を合格した人、あるいは公認会計士となった人だったのです。
しかし、新制度の導入や社会的な要請に伴う業務量の増加、または事業会社などへの人材流出により、監査法人の人手不足が問題となってきました。そこで、公認会計士が必要となるのは監査報告書であるため、それ以外の公認会計士以外ができる業務を公認会計士に限らず採用し、業務の平準化を進める流れになったわけです。その結果、現在は監査法人で公認会計士以外の人も働くようになりました。
監査法人の働き方
監査法人では、監査チームやクライアント単位といったプロジェクト単位で仕事することが多くなります。プロジェクトごとに一緒に仕事するメンバーや環境が変わるのも、監査法人勤務の特徴と言えるでしょう。
監査法人の働き方はプロジェクトごとに異なり、繁忙期や決算などの場合によっては、長時間労働になることもあります。しかし、会社の財務諸表の適正性を担保することで社会に貢献でき、新しい知識や経験を積むことができるため、成長できる働き方ができる場所と言えるでしょう。
監査法人への転職難易度は
監査法人への転職難易度は、どのタイミングで何を求めて転職するのかによって異なります。20代では求められるものはあまり多くありません。公認会計士の試験に合格している、あるいは、公認会計士の資格を取得すれば転職できる可能性が高まるでしょう。
30代ですと、年代が前半か後半によって難易度が異なります。30代前半であれば、実務経験がなくとも職歴があれば転職できる可能性があるでしょう。一方、後半になると前職で成果を出したりしているなど、何らかの実務経験を求められる場合があります。
さらに40代になると、大手監査法人への転職はハードルが高まります。ですが社会人としてのキャリアが強みになる場合もありますので、自身の強みやアピールの仕方をしっかりと考えることで成功への道が見えてくるでしょう。
監査法人で働いた場合の年収イメージ
監査法人で働いた場合の年収はどれくらいなのでしょうか。Big4の平均年収を紹介しながら、具体的に監査法人での年収のイメージを持ってもらうため、求人のリンク先を紹介します。
監査法人で働く人の平均年収
一般的に、公認会計士の平均年収は627万円と言われています。しかし、監査法人で働く場合、その数値はさらに上昇し、特に"Big4"と呼ばれる4大監査法人では、その数値はさらに高まります。具体的な年収を比較してみましょう。
| 監査法人 | 平均年収 |
|---|---|
| PwC Japan有限責任監査法人 | 810万円 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 806万円 |
| EY新日本有限責任監査法人 | 770万円 |
| 有限責任あずさ監査法人 | 763万円 |
これらの年収は、監査業務の専門性と厳格さ、および企業の財務健全性を評価する重要な役割を反映しています。監査法人で働く公認会計士は、クライアント企業の財務諸表を詳細に分析し、会計基準に適合しているかを確認します。その結果を監査報告書にまとめ、企業が法令や会計基準を遵守しているかを公にするという専門性を持つため、転職市場で高い評価を得ています。
ただし、年収だけが働く価値ではありません。大手監査法人で働くと、業界のトップ企業と直接関わる機会があり、専門的なスキルを磨くことができます。また、組織の経営に深く関与し、企業の将来を左右する重要な決定に寄与することもあるはずです。公認会計士として監査法人で働く場合、こうした要素はキャリアアップに大きなメリットとなります。そのため、年収だけでなく、働く環境やスキルアップの機会、働きがいを全体的に評価して最良の選択を下すことが大切です。
関連記事
監査法人勤務の会計士の年収
監査法人の求人のリンク先
監査法人では、合格者向けの求人と転職者向けの求人に分かれます。合格者向けの求人では公認会計士試験の合格が条件となる場合が多く、中には短答式試験合格者でも問題ないというものもあります。
一方、転職者向けの求人では公認会計士試験合格のみならず、これまでの経験などが求められるでしょう。年齢が上がるほど、求められる経験のハードルは上がります。例えば現場責任者の経験、海外の駐在経験などがあると転職しやすくなります。具体的な求人情報は、以下のリンク先を参照ください。
関連求人:監査法人の転職・求人情報
監査法人勤務が向いている人
公認会計士のなかでも、監査法人勤務が合わないという人は一定数います。では、どのような人が監査法人勤務に向いているのか、下記の4つに分けてその特徴を紹介します。
- 人と話すのが好きな人
- 柔軟に仕事ができる人
- ワークライフバランスを求めたい人
- 数字分析が得意な人
人と話すのが好きな人
監査チーム内やクライアントの経理担当だけでなく、役員や社長、他部署の方など、さまざまな方からヒヤリングする機会があります。クライアントの内部情報を把握し、誤りなどを正確に見極めて適切な監査を行うためには、経営者や経理担当者との対話が不可欠だからです。また、監査結果を報告する際も、その結果を適切に伝えるためのコミュニケーション能力が求められます。そのため、人とのコミュニケーションが得意だと仕事がしやすいでしょう。
柔軟に仕事ができる人
監査法人ではプロジェクト単位で仕事するため、プロジェクトごとで柔軟な対応が求められます。クライアントの業種や規模、問題点などは案件ごとに異なるため、一方的なアプローチでは対応しきれません。大手企業の監査では、広範な業務範囲と1つ1つの論点が複雑な財務情報の解釈が求められます。一方で、中小企業の監査では、大企業と比較して業務範囲は狭く、特定の業界に特化した知識や経験が必要になることもあります。往査するクライアントにより異なるため、柔軟に仕事ができる人は、監査法人での業務に適していると言えます。
ワークライフバランスを求めたい人
監査法人ではリモートワークや時短勤務、非常勤勤務など多様な働き方ができ、福利厚生などもしっかりしています。近年では、特に育児中の社員のサポート体制整備や、コロナ禍によるリモートワークの導入なども進められています。そのため、結婚や出産などでライフステージの変化が多い女性でも、比較的働きやすい環境といえるでしょう。
数字分析が得意な人
監査をしていく中では、財務情報をもとに分析し、正確に判断しなくてはいけません。そのため、数字分析が得意な人は、業務がスムーズに進めやすくなります。また、数字分析の中では論理的な思考力も必要です。ロジックが強く、数字関連にも強みを持っている人は、監査法人での仕事が向いているでしょう。
監査法人勤務で大変なこと
次に、監査法人勤務で大変に感じられがちなことを4つ紹介します。
- 株式投資ができない
- 繁忙期はとっても忙しい
- 書類作成などの地味な仕事も多い
- 環境変化が多い
株式投資ができないことがある
監査の過程では、一般の従業員も見ることができないような、会社の内部情報を入手することがあります。そのため、インサイダー取引の防止を目的に、株式投資には制限が設けられています。監査法人ごとにルールの違いはありますが、スタッフでも日本に限らず、クライアントの関係する株式が取引できません。さらにマネージャー以上の職階になると、日本国内の株式について売買を一切禁止されてしまうこともあるでしょう。
繁忙期はとっても忙しい
日本は3月決算会社が多いので、4月~5月にかけてかなりの繁忙期になります。繁忙期中は毎日終電、土日も仕事で、GWも基本は仕事になるでしょう。一方で、夏休みや冬休みなどは一般の会社員よりも長めに取ることができ、タイミングも自由に決められることもあります。
書類作成など地味な仕事も多い
監査業務では、監査調書や審査書類と呼ばれる作成書類がたくさんあります。クライアントや監査チーム内での調整業務など、地味な作業も多くなるでしょう。しかし、クライアントによっては国内外の出張が多くあり、大企業の社長や役員の方と話す機会も少なくありません。そのように貴重な経験ができる点は、逆にメリットと感じる方が多いでしょう。
環境変化が多い
監査法人では特に若手の頃、幅広い経験を積むためにさまざまな監査チームにアサインされることになります。そうなると接するメンバーは異なりますし、対応する会社も変わります。そして、チームが変われば雰囲気が変わり、会社が変われば担当者が異なるため、対応方法なども変えなくてはいけません。監査法人内で異動することもあり、環境変化が多いということをデメリットと感じる人もいるでしょう。
監査法人以外で公認会計士が活躍できる場所
監査法人などで2年以上の監査実務経験を積み、実務補習所の修了考査にも無事に合格すると、公認会計士として登録することができます。実は、このタイミングで監査法人に残るか、それとも転職するか悩む方が少なくありません。そこで、監査法人勤務以外で会計士が活躍できるフィールドも少し紹介します。
- 独立開業
- 一般企業の役員
- 組織内会計士
独立開業
公認会計士になると「税理士」や「行政書士」としても登録できるため、独立して会計事務所を開業することが可能です。監査の仕事は一人ではなかなか難しいので、独立後は税務やコンサルの仕事をされる方が多いでしょう。また、独立した会計士同士でチームを組み、中小規模のクライアントの監査業務を行う方もいます。
一般企業の役員
監査法人退職後に上場企業の取締役や監査役、社外役員に就任する方も少なくありません。役員と聞くと年配の方をイメージするかもしれませんが、最近はベンチャー企業なども増えており、30~40代の役員も多く公認会計士の需要も増えています。
組織内会計士
現在はIFRS(国際会計基準)や収益認識基準など、会計基準が複雑化しています。また、四半期レビューや内部統制監査など企業の監査対応も大変なため、これに向けて企業内で働く会計士も増えているようです。
まとめ
監査法人は、公認会計士が集まっている組織です。多少独特な文化もあるため、一般企業などでの勤務経験がある方は、最初のうち戸惑うことがあるかもしれません。ただし監査法人は、公認会計士試験に合格後ほとんどの方が一度は経験する場所と言えるでしょう。まずは監査法人で経験を積み、必要な知識と経験を獲得した後に、別のフィールドで活躍を検討してみるのも良いのではないでしょうか。
マイナビ会計士では、業界専門のキャリアドバイザーが一人一人に合ったキャリアプランをご提案いたします。監査法人に興味がある方、監査法人後のキャリアに悩んでいる方がいましたら、マイナビ会計士にぜひご連絡ください。
マイナビ会計士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
マイナビ会計士とは?
マイナビ会計士は会計士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。