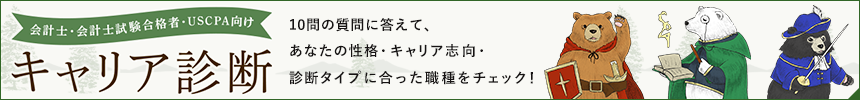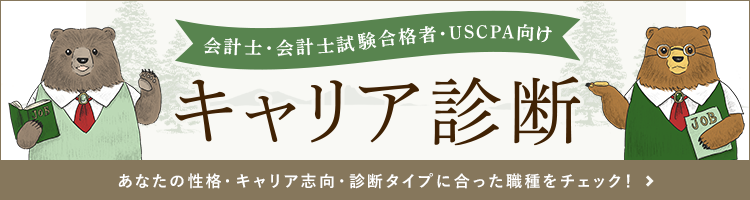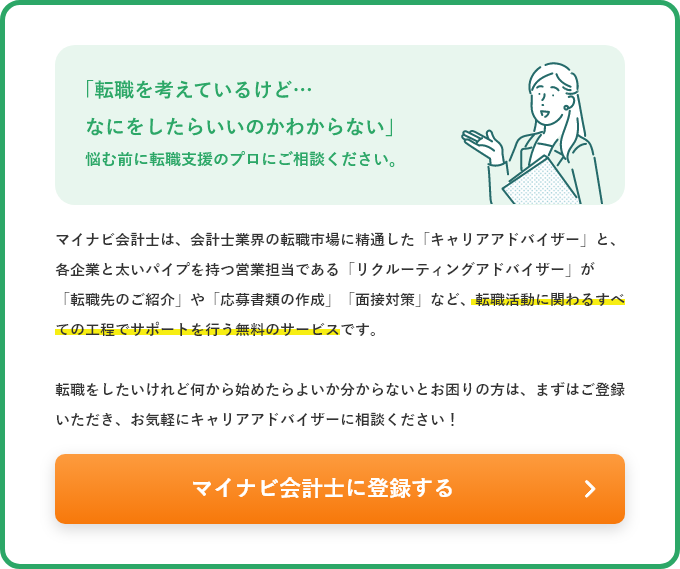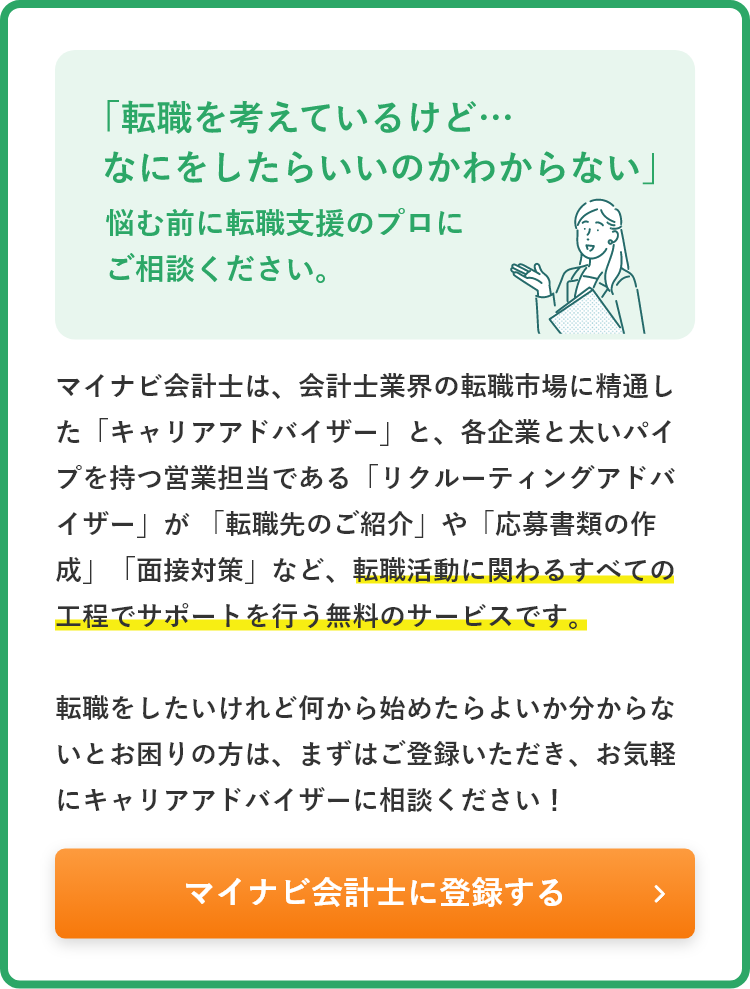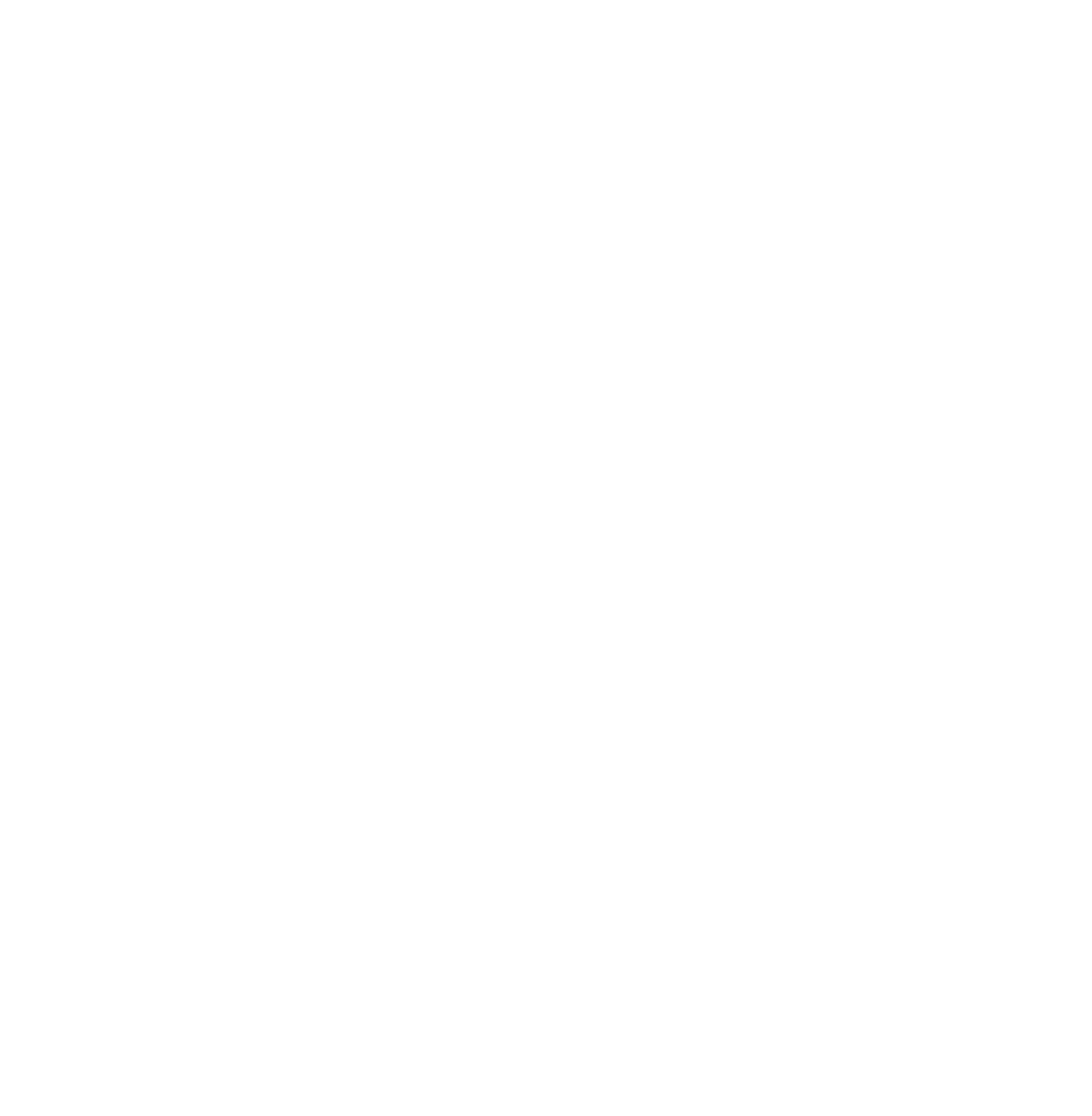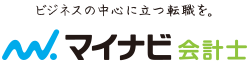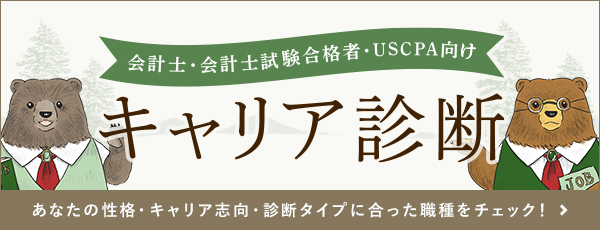公認会計士が行う内部統制とは?
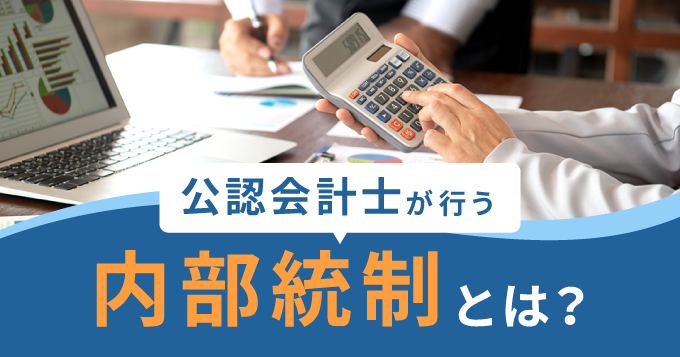
内部統制報告制度(J-SOX)により、内部統制は監査と並ぶ公認会計士の主な業務のひとつとなっています。企業の公正性を重視する傾向は高まり続け、内部統制監査、内部統制のコンサルティング、企業内の内部監査など、内部統制に対応する人材のニーズも高まっています。そこで、この記事では、公認会計士が行う内部統制の概要や目的、内部統制監査に携わる役職の例、そして会計士が行う内部統制について詳しく解説します。
公認会計士には、内部統制を含めて多くのキャリアパスが存在します。企業とどのように関わっていくかを考えると、自らが目指すべき姿を見つけられるでしょう。マイナビ会計士では、こうしたキャリア形成のアドバイスやサポートを行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

マイナビ会計士編集部
マイナビ会計士は、公認会計士・試験合格者・USCPAの方の転職サポートを行なう転職エージェント。業界専門のキャリアアドバイザーが最適なキャリアプランをご提案いたします。Webサイト・SNSでは、公認会計士・公認会計士試験合格者・USCPAの転職に役立つ記情報を発信しています。
内部統制とは
内部統制は、企業の持続的な成長と社会的信用の保持を目指し、その組織内に確立されるべき体制やルールです。企業の各レベルに位置するすべてのスタッフが関与する経済活動全般におよびます。
疑似取引や経理上のミス、重大な法令違反といったリスクから企業を保護し、それらが発生したときには速やかに「修正措置をとる体制を整備する」のも内部統制の重要な役割です。ここからは、より詳しく内部統制について下記にわけて紹介します。
・内部統制の概要
・内部統制の目的
内部統制の概要
内部統制とは、企業などが健全に事業活動を遂行するためのルールや仕組みであり、企業を構成する役員および全従業員によって整備、運用されるプロセスです。下表の6つの基本的要素で構成されます。
経営方針に基づいた具体的な行動規範が定められ、役員および従業員に対して周知徹底が求められます。過度な権限の集中や付与を避け、相互牽制の機能も含まれます。事業活動に関わる組織内外のすべての業務が対象となり、外部の委託先にも遵守を求める場合があります。
内部統制の充実により、企業では業務の適正化や効率化、リスク管理が実現されます。また、ディスクロージャー全体の信頼性や証券市場の信認向上など、市場全体の利益にも貢献する社会的に意義ある業務です。
| 内部統制の基本的要素 | 概要 |
|---|---|
| 統制環境 | 内部統制を支える基盤。経営者の意向や姿勢、経営方針、戦略などの組織と事業活動のビジョンや方向性の明示と事業推進のための機構や権限、規則などを定める。 |
| リスクの評価と対応 | 組織目標の達成を阻害するリスク要因を識別し、分析および評価、当該リスクに適切に対応するすべてのプロセス。 |
| 統制活動 | 経営者の指示命令の適切に実行するために定められた方針および手続き。一般的に組織全体の方針(全社統制)と組織内の各部門(活動単位)の方針(業務処理統制)が定められる。 |
| 情報と伝達 | 必要な情報を識別し、把握・処理された情報の組織内外の関係者相互への適切な情報伝達を確保する仕組みとプロセス。 |
| モニタリング(監視活動) | 内部統制が有効に機能していることを、内部監査などを通して継続的に評価する。 |
| IT(情報技術)への対応 | 組織目標を達成するため、組織の内外で業務の実施においてITに対応する。 |
内部統制の目的
金融庁の企業会計審議会第15回内部統制部会は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」において、内部統制の目的を以下の4つ規定しています。前項の6つの基本的要素は、以下の4つの目的を達成するためにあり、これらは健全な事業活動および財務計算書を適正に作成するための体制の構築、運用をめざすものといえます。
<内部統制の4つの目的>
①事業活動の目的の達成のため、業務の有効性及び効率性を高める
②財務報告の信頼性を確保する
③事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進する
④資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行われるよう図る
<ココまでのまとめ>
・内部統制とは、企業などが健全に事業活動を遂行するためのルールや仕組み。
・内部統制には4つの目的があり、その目的を達成するために6つの基本的要素がある。
内部統制監査に携わる役職の例
内部統制監査に携わる役職の例は、下記が挙げられます。役職を理解することで、内部統制の全体像が見えてくるため、それぞれぜひ確認してください。
・経営者
・取締役会・監査役会
・内部監査人
・従業員
経営者
経営者は、企業の最高指導者として、すべての組織活動について責任を持ちます。経営者の役割と責任は多岐にわたりますが、そのひとつとして、内部統制の整備と運用があります。内部統制の具体的な方針は取締役会によって決定されますが、それを基にした具体的な施策の策定と実行、そしてそれらの結果を評価するという一連の業務が経営者の役割です。
内部統制は、事業活動を適切に行うための「ルール」や「仕組み」であり、例えば、会計情報の信頼性を保つための財務報告のルールや、情報漏洩を防ぐための情報セキュリティの仕組みなど、企業活動全般を対象としています。これらを適切に設計し、適用することが、経営者に求められる内部統制の整備と運用と言えるでしょう。
取締役会・監査役会
取締役会は、経営者の仕事を監督し、内部統制に関する基本的な方針を決定する役割を担います。経営者が策定した内部統制の施策が企業の目指す方向と合致しているか、効率的に運用されているかを評価し、必要に応じて改善を求めるのも取締役会の役割です。
一方、監査役または監査委員会は、内部統制の整備や運用について独立した視点から監視・検証する役割と責任があります。取締役や執行役の業務の適正性を確認するために、内部統制の運用状況をチェックし、不備があれば修正を求めるといったことにも対応します。
内部監査人
内部監査人は、企業が設けた内部統制の運用状況を評価し、その改善を促進する役割を持ちます。具体的には、内部統制が適切に運用されているかを確認し、適切でないと判断した場合は、それを改善するための提案を行うなどです。
また、内部監査人は常に内部統制の目的をより効果的に達成するための視点で業務に取り組みます。つまり、単に問題を指摘するだけでなく、それを解決するための提案を行い、企業全体の改善に寄与する役割があると言えるでしょう。
従業員
従業員も内部統制の重要な担い手であり、組織全体の一員として内部統制の運用に一定の役割を持ちます。たとえば、各自の業務を適切に遂行するためのルールを理解し、それを守ることが求められるなどです。
また、そのルールが業務遂行に不都合や問題を生じさせていないかを把握し、必要であれば改善提案を行うという役割も担います。問題があると判断した場合、適切な改善提案を行い、内部統制の改善と企業全体の業績向上に寄与することも大切です。
会計士が行う内部統制
では、具体的に会計士が行う内部統制にはどのような業務が含まれるのでしょうか。具体的に、下記の4つに分けて詳しく解説します。
・内部統制報告書とは
・内部統制監査と内部監査の違い
・内部統制監査と財務諸表監査の違い
・内部統制監査と会計監査の違い
内部統制報告書とは
金融商品取引法により、上場企業を対象とする内部統制報告制度(J-SOX)が定められ、すべての上場企業は内部統制が有効に機能していることを評価した「内部統制報告書」と「内部統制監査報告書」を公表することが義務となりました。内部統制報告書は、財務計算書を適正に作成するための体制が整備されていることを証明し、内部統制監査報告書は内部統制報告書が適正であることを証明するものです。
内部統制監査報告書において、意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった場合は意見不表明となりますが、内部統制監査報告書の意見不表明は上場廃止基準には抵触しません。
| 内部統制報告書 | 経営者自らが自社の内部統制が有効に機能していることを評価した報告書。 |
|---|---|
| 内部統制監査報告書 | 内部統制報告書に対する監査人の意見を記載した報告書。「無限定適正意見」「不適正意見」「限定付適正意見」「意見不表明」のいずれかで意見表明する。 |
内部統制監査と内部監査の違い
内部監査とは、内部統制が有効に機能しているかをチェックする仕組みのひとつで、内部統制の基本的要素である「モニタリング(監視活動)」に該当します。企業内の監査担当者が監査を行います。
公認会計士は内部統制報告制度による内部統制監査を行いますが、これは企業側が作成した内部統制報告書が適正であるかを検証するものです。
公認会計士は、内部統制監査の知見を活かして内部統制のコンサルティングに携わることもあります。内部統制の整備・構築から各部門・内部監査部門の教育、構築した仕組みの評価と是正対策の提示、内部統制報告書の作成など、内部統制対応を全般的に支援する業務です。
内部統制監査と財務諸表監査の違い
内部統制監査と財務諸表監査は、それぞれ異なる目的や規格で行われる監査ですが、どちらも会社の情報の信頼性を高めるために重要な役割を果たしています。
まず、財務諸表監査は、財務諸表が国際基準や日本基準(財務諸表を作る際に守らなければならないルールや方法)に沿って作られているかどうかをチェックします。財務諸表が国際基準や日本基準に沿っているということは、会社の情報が世界中で比較できるということを証明できます。
一方、内部統制監査は、会社の内部統制(会社の目標を達成するために必要な仕組みや活動)が適切に機能しているかどうかをチェックするものです。内部統制が適切に機能しているということは、会社の情報が正確で安全だということを伝えられます。
このように、内部統制監査と財務諸表監査は目的や企画が異なるものの、信頼性を高めるという点においての重要性は同じだと言えるでしょう。
内部統制監査と会計監査の違い
内部統制監査と会計監査は、どちらも企業の財務報告に関する監査ですが、目的や方法が異なります。違いを表にまとめると以下のようになります。
| 項目 | 内部統制監査 | 会計監査 |
|---|---|---|
| 目的 | 内部統制の有効性を評価する | 財務報告の信頼性を評価する |
| 方法 | 自己評価 | 第三者評価 |
| 対象 | 内部統制 | 財務報告 |
| 確認事項 | 業務の流れやルール、チェック体制など | 会計基準や法令の遵守、事実の根拠、財政状況や業績の反映など |
内部統制監査は、企業が自ら行う監査で、財務報告に関する内部統制の有効性を評価します。一方で、会計監査は、企業が外部の公認会計士や監査法人に依頼する監査で、財務報告の信頼性を評価するものです。両者は相補的な関係にあり、企業の財務報告をより信頼できるものにするために重要な役割を果たしています。
<ココまでのまとめ>
・公認会計士には、内部統制監査、内部統制のコンサルティングなどの業務がある。
・内部統制監査と、財務諸表監査や会計監査は目的や企画、方法が異なる。
内部統制監査の基本的な流れ
内部統制監査の基本的な流れは、以下の通りです。
・内部統制の整備状況を確認する
・内部統制の運用状況を確認する
・不備への対応を行う
・整備状況に対する評価を行う
・最終的な不備の集計を行う
・「開示すべき不備」に当たるかの判断を行う
・内部統制報告書を作成する
・監査法人や公認会計士などの外部監査を行う
・内部統制報告書および内部統制監査報告書を公表する
このように、内部統制監査は、企業の内部統制の有効性を評価し、改善を図るための重要なプロセスです。内部統制の整備状況や運用状況を確認することで、企業のリスクを低減し、経営の健全性を向上することが大切です。
内部統制監査で確認するポイント
内部統制監査は、下表にまとめた6つのポイントをチェックすることで、企業の財務諸表が正しく作成されていることを確認します。
| チェックポイント/th> | 内容 |
|---|---|
| 実在性 | 資産や負債が実際に存在するかどうか |
| 網羅性 | すべての取引や事象が記録されているかどうか |
| 権利と義務の帰属 | 資産や負債が正しい者に帰属されているかどうか |
| 評価の妥当性 | 資産や負債の価値が正しく評価されているかどうか |
| 期間配分の適切性 | 取引や事象が正しい期間に計上されているかどうか |
| 表示の妥当性 | 財務諸表が正しく表示されているかどうか |
それぞれ6つの項目は、企業の財務諸表の正確性を確認するために使用されます。また、総じて、企業のリスク管理やコンプライアンス体制の向上にも役立つものとなるでしょう。
内部統制監査であると便利な資格
内部統制監査の世界では、多くの資格が存在し、それぞれ異なる専門知識やスキルを証明する手立てとなります。そこで、内部統制監査であると便利な資格を、下記の3つ紹介します。
・公認相武監査人
・公認不正検査士
・公認情報システム監査人
公認内部監査人
公認内部監査人(CIA)とは、米国に本部を置くIIA(内部監査人協会)が認定する資格のひとつで、内部監査の専門家としての国際的なスキルと知識を証明するものです。内部監査や内部統制に関わる仕事に携わっている、またはそのような職種を目指している方にとって、専門知識を評価するための基準として有効です。
公認内部監査人の資格では、内部統制の能力を証明できる一方で、整備や運用、評価について深い理解を持つことが求められるでしょう。内部統制監査の初心者でも、公認内部監査人の資格を取得することで、自身のキャリアアップにつなげられます。
公認不正検査士
公認不正検査士 (CFE) は、米国に本部を置くACFE(公認不正検査士協会)が認定する資格で、「不正の防止・発見・抑止」の専門家であることを証明できます。不正対策が重要視される業種に従事している方や、法務部やコンプライアンス部で働いている、または働くことを希望している方にとって特に有益な資格です。
たとえば、不正行為の兆候を見つけ出し、その後の調査を進めて適切な対策を提案する能力を持つことが求められるなどです。公認不正検査士の取得は、企業のリスク管理に大きく貢献できることを示せるよい選択肢となります。
公認情報システム監査人
公認情報システム監査人 (CISA)は、米国に本部を置くISACA(情報システムコントロール協会)が認定する資格で、「情報システム監査・セキュリティやコントロール」の専門家であることを示せるものです。IT監査や内部監査に従事したい方、またはそのような職種を志す方にとって選択肢のひとつとなります。
情報システムの監査には、ITとビジネスの知識が必要不可欠ですから、どちらの分野も学べる資格は非常に有効でしょう。具体的には、情報システムの設計、実装、運用の適切さを評価し、それがビジネス目標にどの程度貢献しているかを評価する能力を証明できます。公認情報システム監査人の資格を保持することで、ITとビジネスの橋渡しをするプロとして活躍できます。
内部統制部門への転職は専門性が鍵
内部統制部門への転職を考えているなら、専門性の確立が不可欠です。特定の領域での深い知識と技術は、その職場で成功を収めるための鍵となるからです。内部統制部門では、財務報告の信頼性や業務プロセスの効率性、法令順守など、企業全体の健全な運営を支える重要な役割を果たします。
このため、内部統制の仕組みやその評価方法、リスク管理の手法などについての深い理解が求められますし、企業の業務プロセスやITシステム、会計知識など、内部統制が関わる多岐にわたる領域の知識も必要です。
内部統制の実務経験を積むことはもちろん重要ですが、専門的な資格を持つことも有効な手段です。前述した「公認内部監査人(CIA)」、「公認不正検査士(CFE)」、「公認情報システム監査人(CISA)」などの資格は、自身の専門性を証明し、内部統制部門への転職やキャリアアップにつながります。また、国際的な認知度を持っているため、海外企業とのビジネスの機会も広がるかもしれません。
したがって、内部統制部門への転職を考えている方は、特定の領域での専門性を深めるために、特化した実務経験を積めるキャリアプランを立てたり、適切な資格取得に挑戦したりするとよいでしょう。
内部統制に関する転職Q&Aや成功事例
さいごに、内部統制に関する転職Q&Aや成功事例を下記に分けて紹介します。
・【転職Q&A】内部統制コンサルタントの具体的な業務内容と資質ややりがいを知りたい
・【転職成功事例】やりがいある内部統制の仕事へ
【転職Q&A】内部統制コンサルタントの具体的な業務内容と資質ややりがいを知りたい
https://cpa.mynavi.jp/career_faq_mt/InternalControl/424.html
Q1;内部統制コンサルタントの業務内容は?
クライアントの業種、規模、現状などで異なりますが、内部統制対応に関する全般的なサポートが役割であると考えておくとよいでしょう。
<内部統制コンサルタントの主な業務>
1)内部統制の構築・評価に関するスケジューリング
2)内部統制ツールの提供
3)効率的な文書化プロセスの立案および実行サポート
4)内部統制の整備運用評価のサポート
5)監査法人との折衝サポート
6)セミナー開催など関係者の知識のブラッシュアップなど。
Q2;内部統制コンサルタントに求められる資質は?
1、優先順位をつけて業務を効率的に進める能力
内部統制コンサルタントが手がける業務は幅広く、満足できる結果を出すためには優先順位をつける能力が不可欠です。また、ストレスをためこんで体調を崩さないためにも重要な能力です。
2、コミュニケーション能力
監査法人、クライアントの各部署など、各方面との折衝が大切な仕事です。相手の話を上手に聞きながら、自分から発信するコミュニケーション能力が必要です。物事を的確に伝える話し方を心がけられるとよいでしょう。
3、「本当の改善につなげる」という強い意志
内部統制コンサルタントの仕事は、クライアントに本当の意味での改善を提供することです。常にクライアントにとっての最善の方法を客観的に模索し、提案・実行につなげるのがコンサルタントのもっとも大切な役割といえます。
【転職成功事例】やりがいある内部統制の仕事へ
https://cpa.mynavi.jp/case_mt/company/343.html
●プロフィール
| 34歳男性 | 転職前 | 転職後 |
|---|
| 業種 | 事業会社 | 事業会社 |
|---|---|---|
| 職種 | 経理 | 内部統制 |
| 年収 | 750万円 | 800万円 |
●転職の理由
公認会計士として監査法人で監査業務、会計アドバイザリー業務を経験した後、自分の経験、スキルを企業の成長につなげたいと考え、事業会社の経理職に転職。経理業務が中心で経験を活かせず、より専門的な見地から企業に貢献できるポジションを希望し、再び転職を決意。
●転職成功の経緯
最後の転職となることをめざし、“やりがいのある業務”の明確化を重視。前回の転職時から年齢、経験社数が増えたことで書類選考の通過に苦戦したが、面接の選考通過を向上させるべく面接対策を強化した。経歴や強み、弱み、志望動機を研ぎ澄ませた結果、無事に志望企業の内定を獲得。
<ココまでのまとめ>
・年齢、経験社数が増えても、経験や強みを活かして転職に成功できる。
まとめ
企業における内部統制の重要性は高まり続けており、監査法人に転職して最初に経験した業務が内部統制監査という会計士の方も増えているのではないでしょうか。将来のキャリア形成を視野に入れながら、会計士としてどのような道を選択するかは、人生におけるターニングポイントとなります。
マイナビ会計士ではあなたの強みや人柄をしっかり企業さまにお伝えし、初めての転職を成功させるお手伝いをいたします。まずはご相談から、ぜひお問い合わせください。
マイナビ会計士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
マイナビ会計士とは?
マイナビ会計士は会計士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
こんにちは。マイナビ会計士の記事をご覧いただき、ありがとうございます。
あなたにおすすめの記事をご紹介いたします。
注目コンテンツ
-
キャリアアドバイザーを通じて、ステップアップに成功した転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
転職をお考えの会計士・試験合格者の疑問や悩み、不安を会計士業界専任キャリアアドバイザーが解消します。
-
事業会社、監査法人、会計事務所/税理士法人、コンサルティングファームについてをご紹介します。
-
復職する際の注意点や転職のタイミング、オススメ求人や転職成功事例をご紹介します。
-
試験合格後から会計士登録の完了までのスケジュールや流れ、登録後にやるべきことなどをご紹介します。
-
資格取得のメリットや、活躍できるフィールド、転職市場での価値とニーズについてご紹介します。
-
監査法人から事業会社やコンサルティングファームへの転職方法やポイントなどをご紹介します。
新着記事
-

仕事・キャリア
公認会計士は30代・未経験から目指せる?合格率・年収や就職先まで紹介
-

仕事・キャリア
20代・未経験でも公認会計士は目指せる?メリット・デメリットと成功のコツ
-

仕事・キャリア
未経験でも会計士のコンサルティングファームで働ける?仕事内容や年収・向いている人を解説
-

業界情報
会計士試験は何が変わった?2025年6月発表「バランス調整」の内容と受験生がとるべき対応策
-

仕事・キャリア
公認会計士からPEファンドへ転職するのはおすすめ?役立つ前職のスキル
-

仕事・キャリア
40代からUSCPAを取得するメリットと、資格を活かしたキャリア戦略
-

業界情報
【令和8年(2026年) 公認会計士試験第I回短答式試験 結果速報】合格発表後にすべきこと
-

仕事・キャリア
公認会計士がIPO準備企業ですることは?最新の転職市場やメリットも解説
サービス紹介
-

マイナビ会計士とは?
会計士・試験合格者専門の転職エージェントです。細かなサービス内容をご説明します。
-

ご利用の流れ
マイナビ会計士の具体的なご利用の流れや登録のメリットなどをご紹介します。
-

キャリアアドバイザー紹介
転職のプロがあなたの転職をサポート。会計士業界専任のキャリアアドバイザーをご紹介します。
-

非公開求人とは
マイナビ会計士の求人の一部は非公開求人です。求人を公開していない理由などをご紹介します。
-

はじめての転職の方へ
はじめての転職で失敗しないためのポイントや、マイナビ会計士の強みをご紹介します。
-

2回目以降の転職の方へ
業界内で再度転職をする際に注意すると良いポイントや、マイナビ会計士の強みをご紹介します。
-

個別転職相談会・セミナー
おすすめ別や資格別に実施中の相談会やセミナーのご紹介、当日までの流れなどをご紹介します。
-

よくあるご質問
転職支援サービスをさせていただく中で、求職者のみなさまからいただくご質問をご紹介します。
あなたが理想の会計士になるまで、
私たちは全力でサポートいたします。
蓄積された実績や、非公開の企業情報などから条件にマッチした求人をご紹介いたします。
面接・応募書類対策・スケジュール調整など、転職成功へ導くため、
マイナビ会計士は転職をサポートいたします。

マイナビ会計士に申し込む