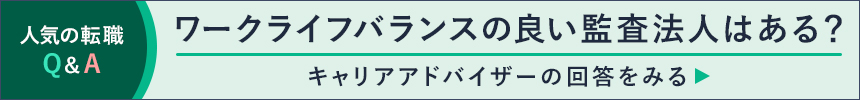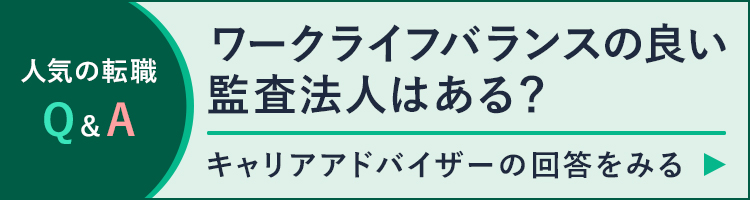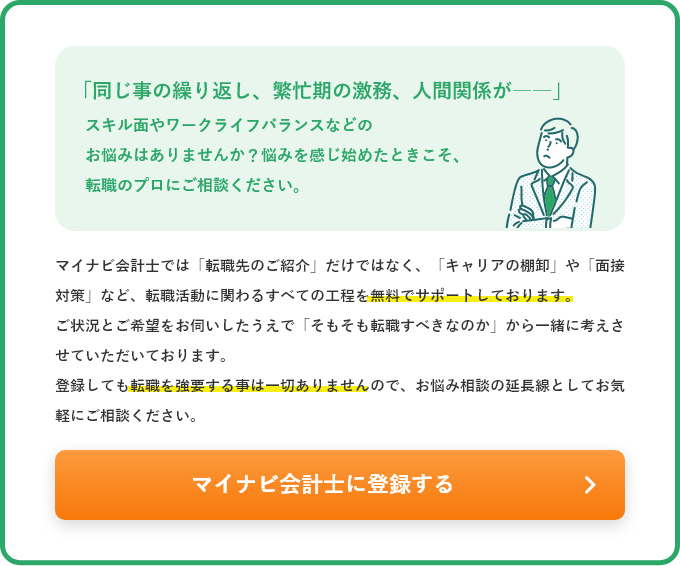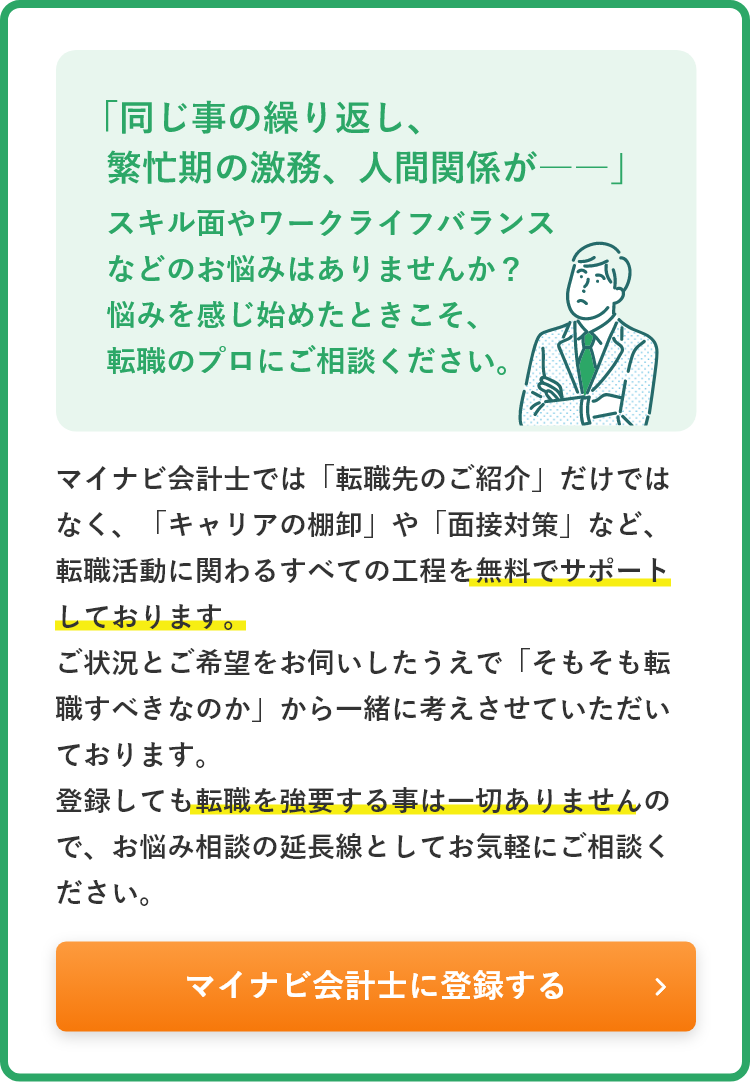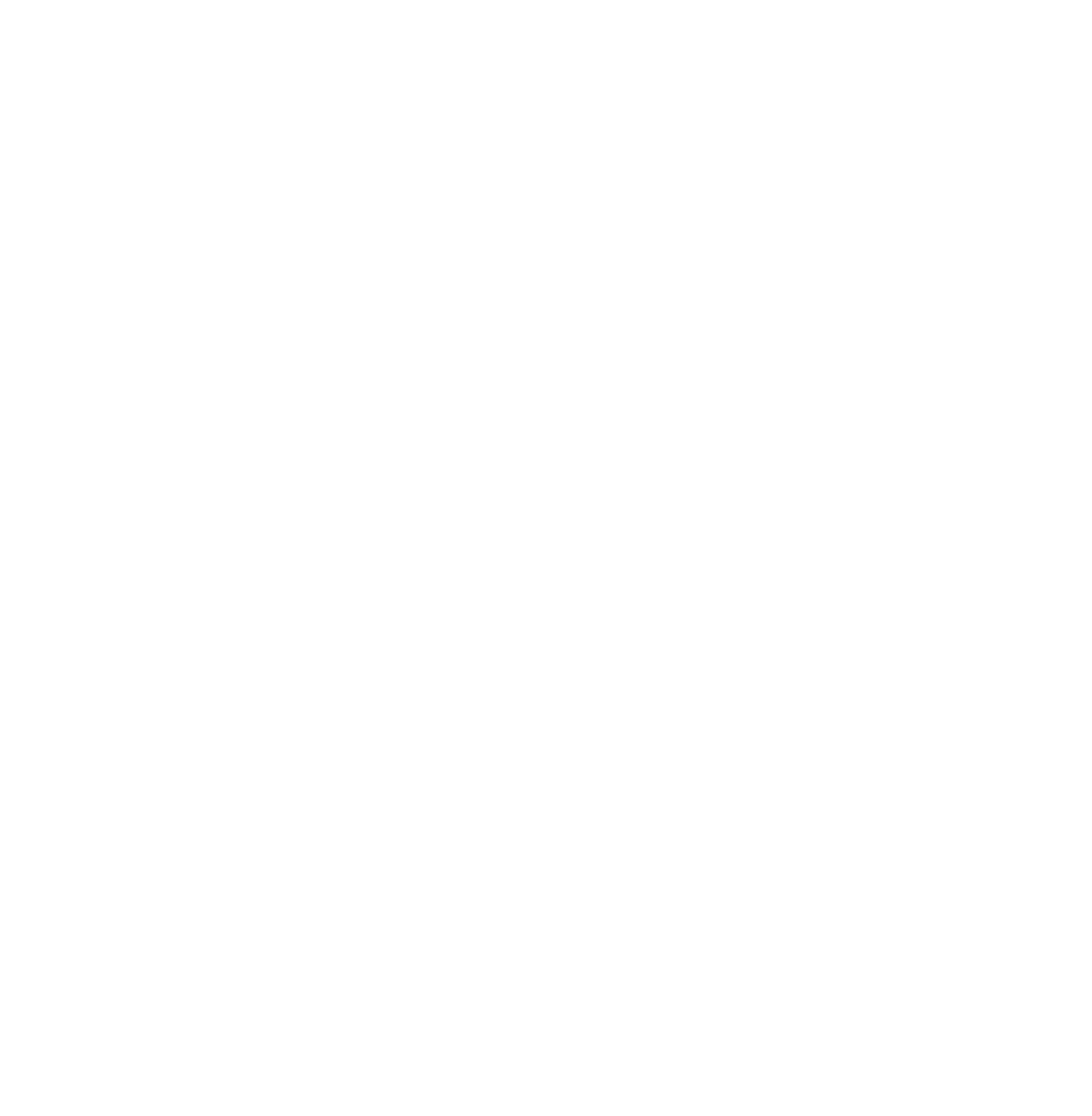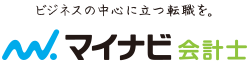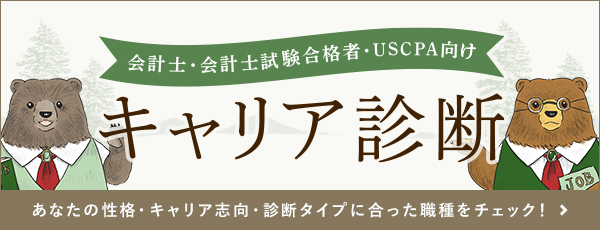会計士が独立を考えるなら税務の知識・スキルは必須
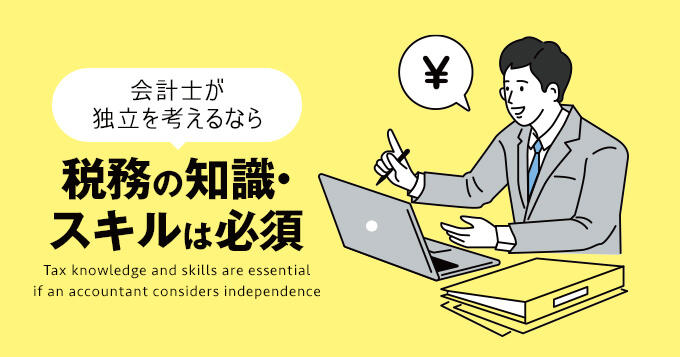
公認会計士の皆さまのなかには、独立開業をめざしている方もいらっしゃるでしょう。独立すると、自分の裁量で仕事ができる半面、会社のブランドや組織力を頼れなくなります。会計以外の知識やスキルを身につけ、仕事の幅を広げることが独立後のリスク軽減につながります。そのなかでも、必須ともいうべき税務についてまとめました。

マイナビ会計士編集部
マイナビ会計士は、公認会計士・試験合格者・USCPAの方の転職サポートを行なう転職エージェント。業界専門のキャリアアドバイザーが最適なキャリアプランをご提案いたします。Webサイト・SNSでは、公認会計士・公認会計士試験合格者・USCPAの転職に役立つ記情報を発信しています。
独立前に考えておくべき「税務」との向き合い方
税理士の独占業務、税務業務とは
税理士の独占業務である税務業務は、納税に関する業務です。法人・個人とも納税は義務であり、さまざまな税金を納めています。税務書類の作成や代理申請などの税金に関する業務全般が、「税務業務」と呼ばれています。納税手続き以外に、適法の範囲内で節税する方法を提案するのが税務コンサルティングです。相続や事業承継の際には、特に重視される役割です。
会計士は申請すれば税理士として登録できる
税務業務は税理士の独占業務ですが、公認会計士は税理士として登録することができます。ご存じのとおり、公認会計士試験の必須科目には租税法が含まれ、合格後の実務補習所でも各種税法について詳しく学びます。さらに、公認会計士として登録する際の修了考査にも租税法の科目があります。そうした点から、税務業務を行うために必要な能力は担保されているという認識にたち、公認会計士は税理士登録が認められています。
独立するなら「税務」の知識は必須
公認会計士が独立する場合、企業などの法人が顧客のメインになります。法人にとって税務署への対応は不可欠であり、会計処理の先には必ず納税があります。監査法人では、監査という視点だけで仕事ができるかもしれませんが、独立して、クライアントの会計処理に責任を負う立場になれば、納税や財務に関する配慮を求められます。そのためにも、独立を考えているなら、税務に関する知識は必須と言えます。
<ココまでのまとめ>
・税務業務は、正しく納税するための支援と節税へのアドバイス
・公認会計士は税理士として登録することができる
・法人向けの会計業務では、納税やそれに伴う財務への配慮も求められる
「税務はわからない」まま、独立してやっていけるか?
クライアントにとっては、会計も税務も同じ仕事
専門職である公認会計士や税理士の皆さまは、それぞれの独占業務について、有資格者として、専門領域に関する自負や責任感をお持ちの方が多いです。しかし、クライアントである企業にとっては、会計も税務も「経営」という流れの中で関連する業務であり、切り離して考えられることはありません。
税務がわからない、できないが機会損失に
中小企業のクライアントでは、公認会計士と税理士を個別に契約するケースは少ないといってよいでしょう。特に小規模事業者は、税務を優先して、顧問税理士に経理業務の代行から税務申告まで、丸投げしているケースも多いです。独立後にIPOやM&Aなどに特化するのでなければ、中小企業をクライアント候補として想定しておくべきでしょう。税務がわからないようでは、中小企業のニーズに応えられず、仕事を逃してしまう可能性があります。
税務の知識不足がクライアントの不利益につながる可能性
前述のとおり、会計処理の先には必ず税務申告があります。会計処理によって、納税額が多くなったり、税務署から計上ミスを過少申告と判断されて重加算税が課されてしまったりといったケースもあります。企業にとって、納税額によって純利益が増減するだけでなく、税法違反というリスクにもつながります。税務の知識不足は、クライアントの不利益につながる可能性があります。
<ココまでのまとめ>
・会計も税務も「経営」の中では一連の業務
・税務がわからないと、仕事のチャンスを逃してしまう可能性がある
・税務知識の不足が、クライアントに不利益や損害を与える可能性がある
独立準備として身につけておくべき
関連記事
会計士が独立に向けてのやるべき準備とは?
身につけておくべき税務の知識
現職で税務申告などの業務を経験できればベストですが、できない場合でも所得税(法人・個人)の仕組みや確定申告については、最低限の知識として理解しておく必要があります。特に確定申告などは、制度としては知っていても、申告手続きなどで戸惑うこともあるようです。また、業種別や地域による税制優遇などのさまざまな情報収集も必要です。
税理士登録にもある程度の時間がかかります。転職や独立を考えるとき、事前準備としてそうした手続きも調べておくとよいでしょう。
転職先で異なる、得られる知識やスキル
独立にあたって、監査法人での経験だけでは不安と感じる場合は、転職することで実務を経験できる可能性があります。会計や税務業務などの実務だけでなく、事務所の運営や営業のやり方など、独立までに知っておくべきことは多岐にわたります。
転職先の業務内容や規模によって、得られる知識やスキルは異なります。いずれのケースも腰を据えて経験を積む必要がありますので、中長期的な視点でキャリアプランを考えて取り組むことをおすすめします。
・一般的な会計業務を中心とする会計事務所
財務や経営アドバイスなどの会計業務のほか、経理代行や決算などの進め方や税務業務を経験できる可能性があります。事務所によっては、クライアントとのつき合い方や新規クライアントの開拓、事務所の運営を経験できる可能性もあります。
・投資、M&Aなどの特定分野に特化した会計事務所
特定分野の経験を積むことができ、その分野を独立後の強みとして活かせます。投資会社や金融機関、弁護士、不動産鑑定士などほかの士業との連携も多いため、独立後につながる人脈を築けるチャンスもあります。
監査法人での経験と税務の知識で独立後も安心
監査を通じて、多くの企業経営や会計処理のケースを知っていることは、会計士としての強みになります。また、高いコンプライアンス意識、ときにクライアントにとって耳の痛い指摘ができる公正な視点などは、顧問会計士としても望ましいといえます。
監査法人での経験に加えて、税務知識があれば、クライアントの経営をワンストップで支えることができるので、仕事の幅はぐっと広がります。
<ココまでのまとめ>
・最低限、身につけるべき知識は、所得税と確定申告
・一般的な会計事務所では“全般的な知識”、専門化した会計事務所では“強み”が身につけられる
・監査法人の経験と税務知識で、経営をワンストップで支えることができる
まとめ
会計士が独立するとき、一般的な会計の知識とスキルだけでは、残念ながらリスクが大きいです。多くの法人にとって会計と税務は切り離せない業務であり、税務がわからないと、仕事の幅が狭くなってしまうからです。 独立を視野に入れるなら、税務の知識は間違いなくあったほうがよいのですが、監査法人では、会計士が税務を担当する機会は少ないといえるでしょう。必要なスキルアップができる転職を、独立までのステップアップとして考えてはいかがでしょうか。
マイナビ会計士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/会計士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/会計士)
マイナビ会計士とは?
マイナビ会計士は会計士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
カテゴリから記事を探す
会計士業界専門転職エージェント
担当のキャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。